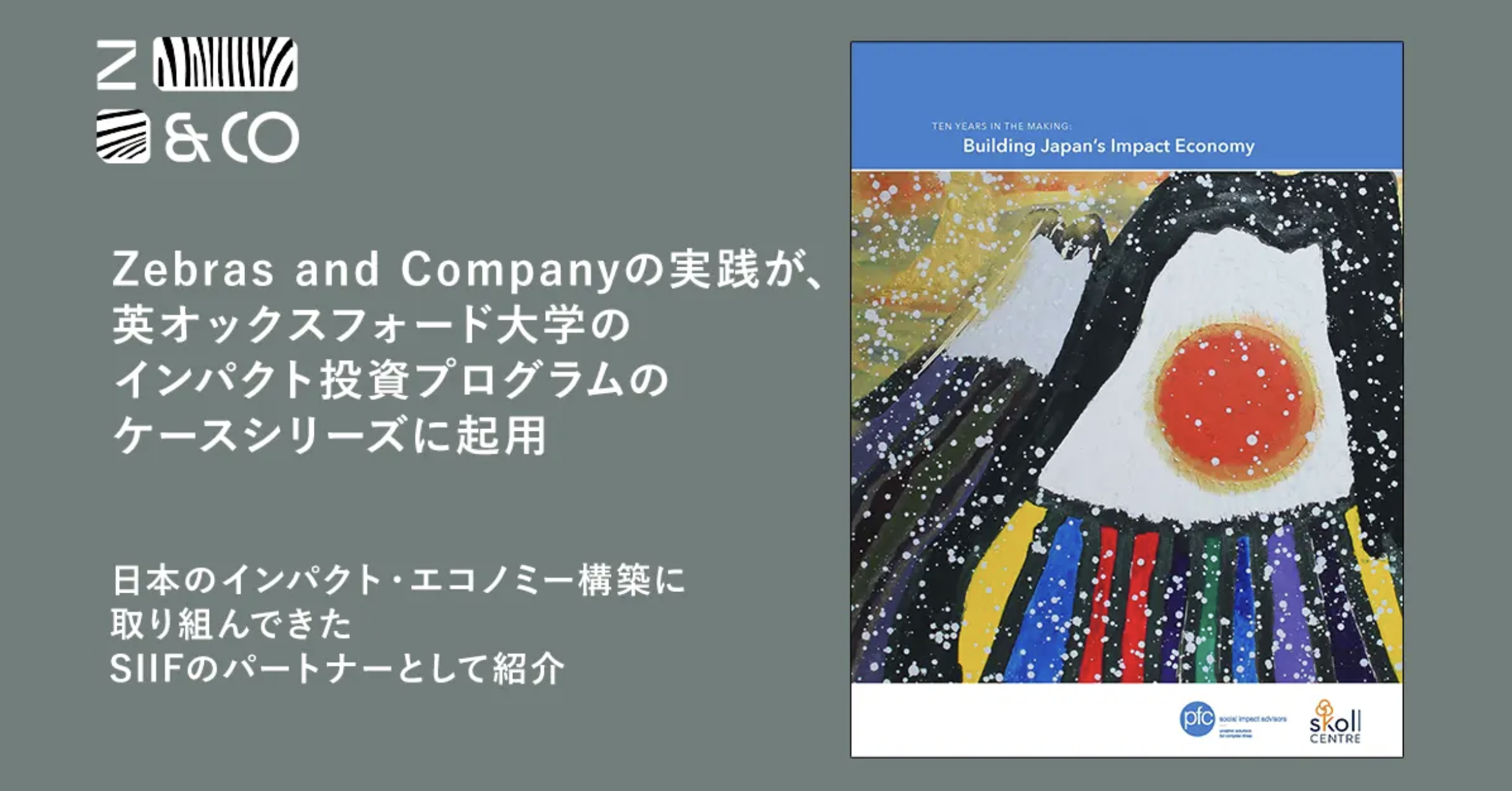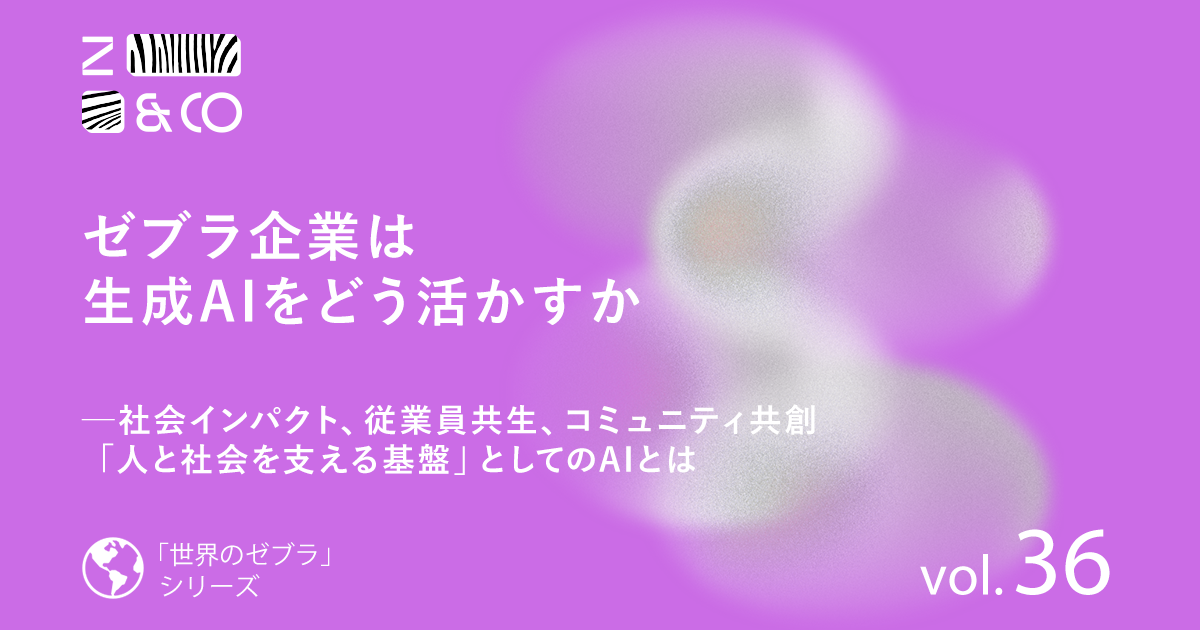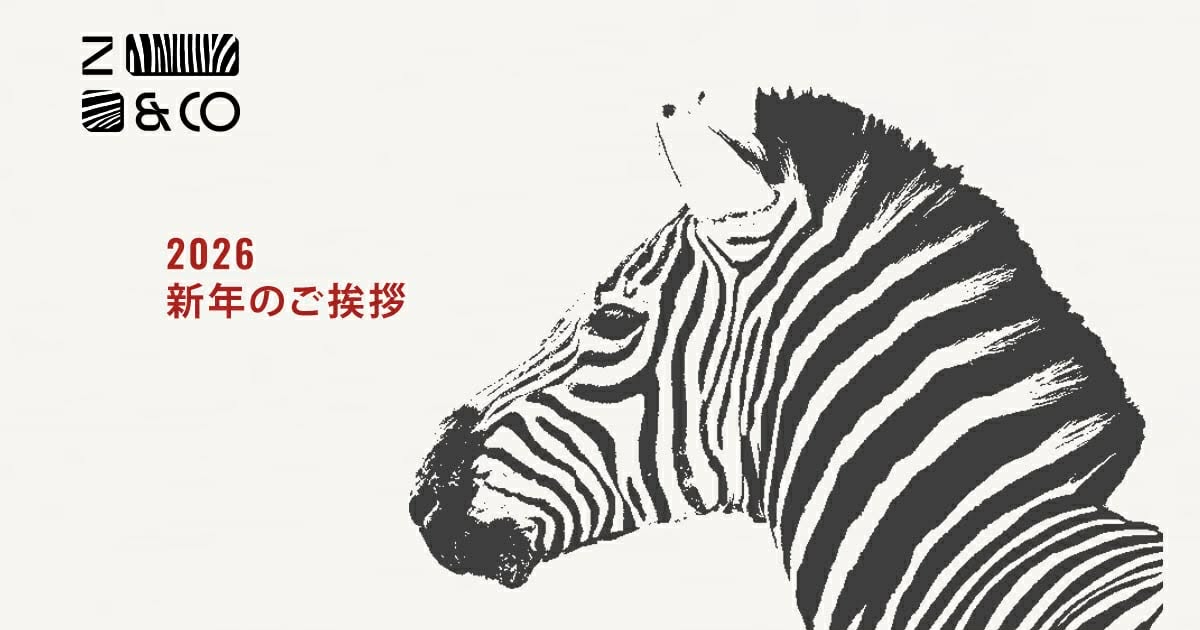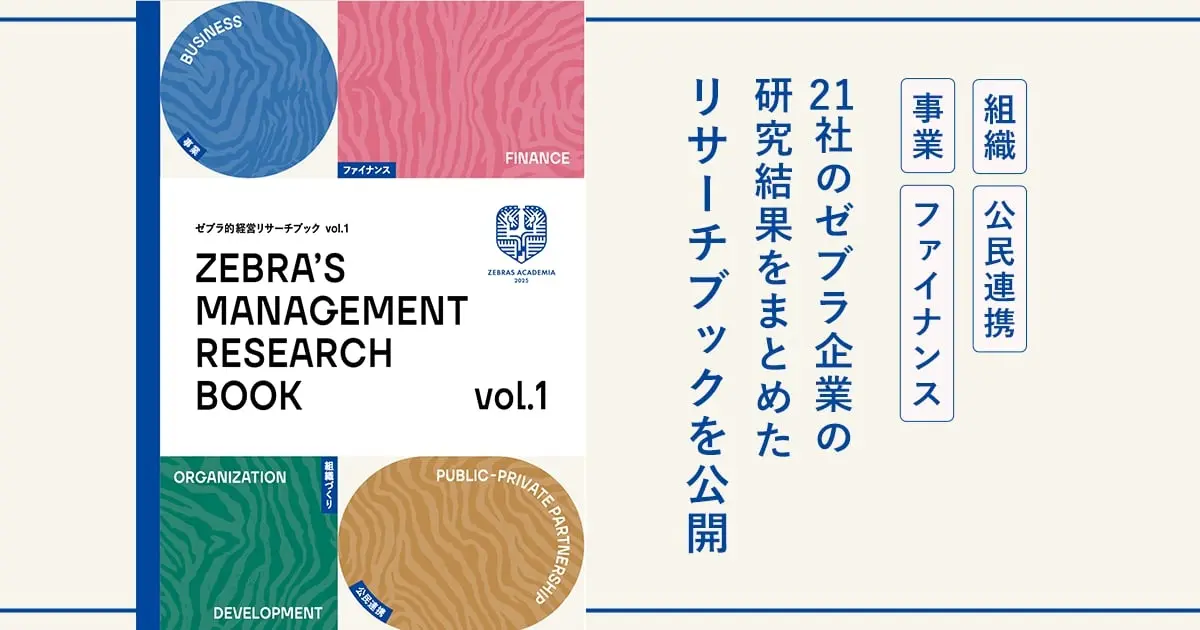2025.05.09 ZEBRAS まずはこのトピックから
注目高まるローカルゼブラ。多省庁連携で支援を加速【政策発表会レポート】
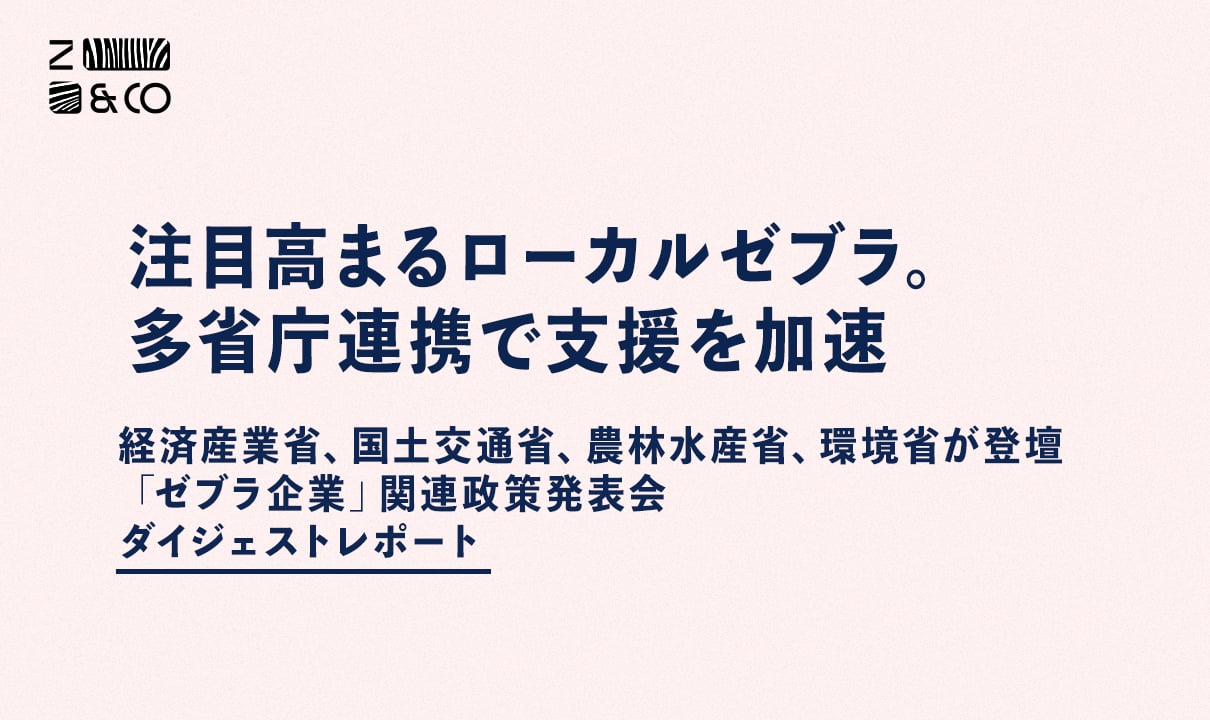
ゼブラ企業に関する政府の取り組みを広く共有することを目的に4月23日、「令和7年度 ゼブラ企業関連政策発表会」を開催しました。昨年度に続く2回目の開催で、経済産業省中小企業庁、農林水産省、国土交通省、環境省の4省庁が参加。ゼブラ企業に関連する最新政策や、官民連携による地域課題解決への期待を語ってもらいました。オンライン参加を含め400人近くが聴講した当日の模様をレポートします。
注目高まる「ローカルゼブラ」の存在意義
唯一2年連続の参加となる経済産業省中小企業庁の伊奈友子商業課長は冒頭、ゼブラ企業、特にローカルゼブラ企業の存在意義に言及。「少子高齢化や人口減少が進む中で、行政(公助)や資本市場(自助)だけでは対応できない領域が拡大しており、地域全体の持続可能性にコミットする共助の担い手として、ビジネスの手法で課題解決に取り組むローカルゼブラ企業の活躍領域が広がっている」との認識を示しました。
政府は2023年の骨太の方針で初めて「ゼブラ企業」という言葉を盛り込み、地域課題解決の担い手として、ソーシャルビジネスを支援するエコシステムの構築を掲げました。これを受け、中小企業庁は「地域の社会課題解決促進に向けたエコシステム研究会」を立ち上げ、「地域課題解決事業促進に向けた基本指針」を策定。2024年の骨太の方針では再び「ゼブラ企業」が盛り込まれ、20地域でローカル・ゼブラ企業が取り組む事業が創出する社会的インパクトを見える化する実証事業が行われました。
伊奈氏は、この実証事業を通じて「ゼブラ企業への認識が向上した」とし、これを一過性のブームに終わらせず定着させるため、今年度は地域内のエコシステム強化に加え、金融機関や域内外の企業など多様なステークホルダーとの連携強化に取り組む方針を示しました。また、ゼブラ企業を育てられるファイナンスや社会的インパクト評価の活用についても検討を進めるとしています。
地域社会とゼブラの関わりしろは
続いて国交省、農水省、環境省から担当者が登壇し、関連政策を発表しました。
国土交通省の倉石誠司総合計画課長さんは、日本の国土を個人個人の幸せのためにどうしていくかという視点から、日常生活のサービスや経済活動のまとまりである「地域生活圏」を地域社会の新しい原単位として捉える考え方を紹介。「持続可能な日常生活サービスを提供するためには、外部からの資本(お金、人、情報)を呼び込むことが重要であり、その主役となるのがゼブラ企業である」と位置づけました。
同省は、この地域生活圏の実装に向けた制度設計を今まさに検討中。発表会前日(4月22日)から地域生活圏の形成に取り組むプレイヤーおよびプレイヤー間をつなぐプラットフォーマーを支援する「地域生活圏形成リーディング事業(調査業務)」の公募を開始しています。
農林水産省の朝日健介農村活性化推進室長は、高齢化による農業者の急減や、集落機能の低下が進む農山漁村の現状を説明。食料安全保障の意味でも農山漁村コミュニティの維持は不可欠であり、そのためには「集落と外側のエリアに住む方との関係性維持が重要」と述べました。その上でゼブラ企業には「直接の支援はもちろん、支援者同士をつなぐ役割を担ってほしい」との期待を示しました。
同省が推進する「『農山漁村』経済・生活環境創生プロジェクト」では、通い、副業などさまざまな形での農林水産業への参画を支援してきています。また「『農山漁村』インパクト可視化ガイダンス」では、地域経済の活性化のみならず、ウェルビーイング向上、ネイチャーポジティブなど多様なインパクトの視点を示すことで、参画しやすい環境を整えています。
環境省からは、石川拓哉地域循環共生圏推進室長が登壇しました。地域循環共生圏は「地域資源を活用して環境・経済・社会を良くしていく事業(ローカルSDGs事業)を生み出し続け、地域課題を解決する自立した地域」と「地域の個性を活かして地域同士が支え合う分散型のネットワーク」からなる、自立・分散型の持続可能な社会を目指す考え方。自然資本の維持・回復・充実が前提となります。
同省では共生圏を作る活動をさまざまな政策で支援してきており、支援実績はすでに100地域以上。環境という軸でも、ローカルゼブラの関わりしろは大いにありそうです。
横の連携と「共創」への期待
続いて行われたパネルディスカッションでは、省庁間の連携についても議論が及びました。
かつては縦割りのイメージもあった行政ですが、近年このように多省庁が連携してゼブラ企業のような共通テーマで登壇する機会が増えています。その理由として、地域づくりのプラットフォームが増えたことや、一つの省庁だけでは複雑化した地域課題に対応できないこと、それぞれの知恵やツールを持ち寄る必要性が高まっていることなどが挙げられました。
また、各省庁の担当者からは、ゼブラ企業への期待が改めて語られました。農林水産省の朝日さんは「人手不足の地域現場において、ソリューションを持つゼブラ企業が課題解決に貢献し、地域のプロフェッショナルと結びつくこと」への期待を表明。
中小企業庁の伊奈さんは、2年目のローカルゼブラ実証事業では、ゼブラ企業同士のコミュニティに加え、域内外からの資本(人、お金、情報)の流れをつくり、つないでいくことに注力したいとし、「関係省庁とも連携して大きな流れにしたい」と語りました。
事例発表から見る官民連携の意義
発表会後半では、実際に中小企業庁や農林水産省の事業に採択された企業の事例発表も行われました。
鹿児島から参加した株式会社musuhiの野崎壮平さんは、地域の多様なステークホルダー(経営者、行政、学校、金融機関など約40名)を巻き込み、全3回のワークショップを通じて、これまでバラバラだった活動を「一体何を起こそうとしているのか」という一つの物語(ビジョン・インパクト戦略)として語れるようになった成果を報告。省庁との関わりの意義として「事業活動に国のお墨付きを得られたことで、これまでアプローチできなかった層に働きかけられるようになった」「何よりも自分たちの事業活動に自信を持てるようになった」ことを挙げました。
島根県大田市の株式会社石見銀山群言堂グループ代表の松場忠さんは、人口400人の町で長年にわたり企業活動と共に地域づくりを行ってきた経験を紹介。農林水産省の「農泊推進事業」(2017-19年度)に始まり、経済産業省の「地域企業共生型ビジネス導入創業促進事業」(2021年度)、中小企業庁の「地域の社会課題解決企業支援のためのエコシステム構築実証事業(地域実証事業)」(2024年度)、国土交通省の「二地域居住先導的プロジェクト実装事業」(2025年度)と、連続して国の政策に取り組んできた経緯を説明しました。
多様な政策に取り組んだ結果として、ハード整備から計画策定、実証、事業化、地域法人の設立、コンソーシアム化へと繋がり、行政、民間、地域住民の垣根を超えた連携体が生まれたことを報告。省庁と関わりながら事業を営む意義として、「行政の抱える地域課題と民間や地域住民の抱える地域課題の接合点を発見」し、それぞれのリソースを持ち寄ることで課題解決へのコミットが明確になること、国の描く方向性を理解することで、人口減少下でも行政連携して事業に取り組めるメリットを挙げました。
また、環境省の地域循環共生圏事業に関わる佐賀県唐津市の小田切裕倫さんからは、環境というテーマが省庁間の横串を刺しやすく、自治体内の連携を促す可能性や、日本独自の自然共生文化を世界に発信する可能性が示唆されました。
発表会全体を通して、地域課題が複雑化・複合化する現代において、一つの主体や省庁だけでは対応が難しくなっており、社会的インパクトと経済性の両立を目指すゼブラ企業が、多様な関係者をつなぎ、官民連携・異分野連携・広域連携の中核を担うことへの期待が強く示されました。国の政策が、こうした企業の活動を後押しし、「共創」を通じて地域社会の持続可能性とウェルビーイング向上を目指していく、新たな時代の幕開けを感じさせる発表会となりました。
本発表会の当日の様子を公開中です。
全編を視聴希望の方はこちらからご覧ください。
――――――――――
■録画URL(YouTube)
第一部:各省庁からの取り組み紹介
第二部:地域プレイヤーによる現場報告・対話セッション
※第二部では、登壇者の群言堂・松場さんの姿のみが映り、音声のみでディスカッションが進む箇所がございます。視聴しづらい部分があり恐縮ですが、ご了承いただけますと幸いです。
■スライド資料(Google Drive)
https://drive.google.com/drive/folders/11WeZdZ9PjCe0sZOTQebuIysfE5IhLO6c?usp=sharing
――――――――――

PROFILE
ゼブラ編集部
「ゼブラ経営の体系化」を目指し、国内外、様々なセクターに関する情報を、一緒に考えやすい形に編集し、発信します。