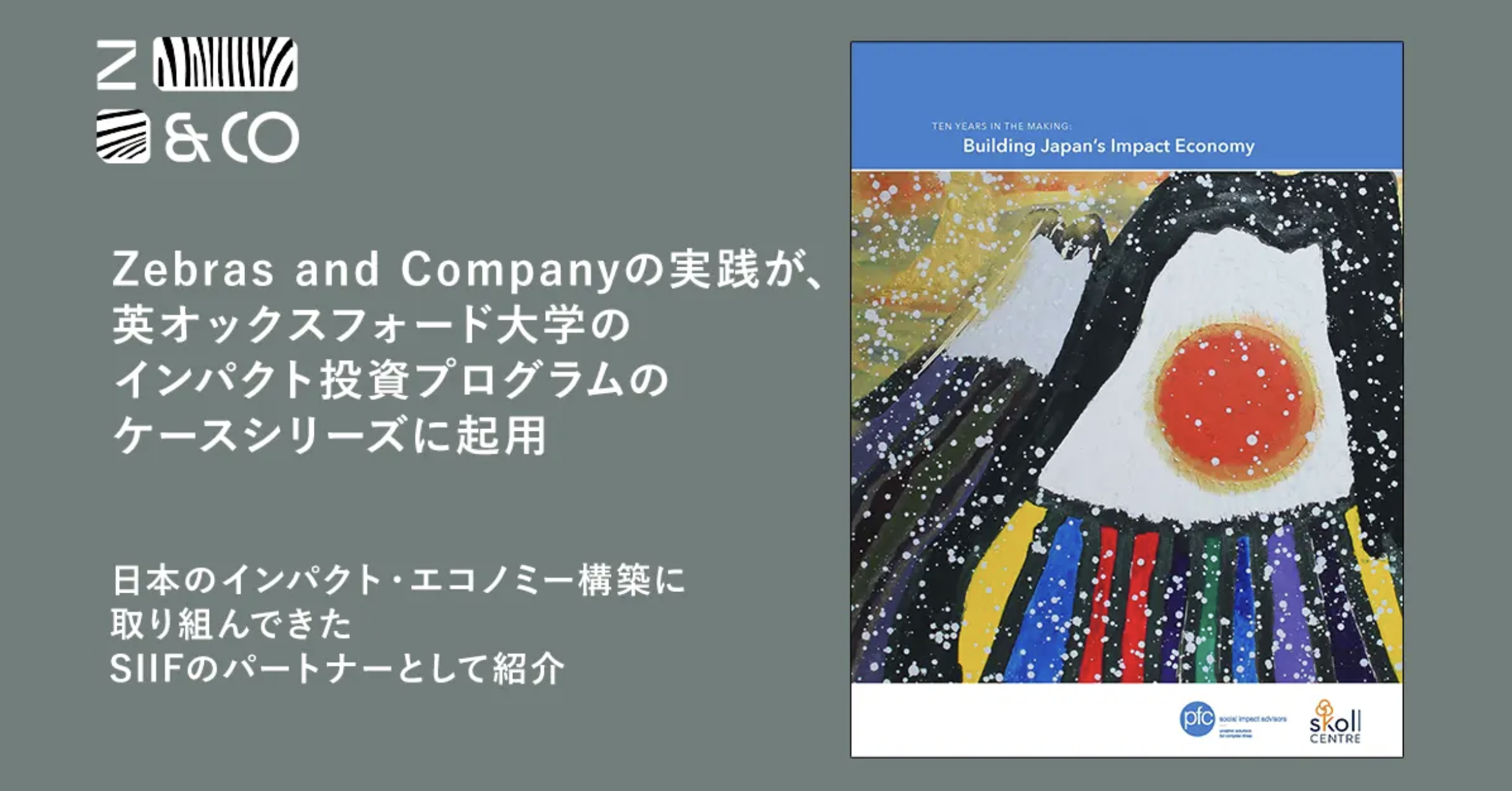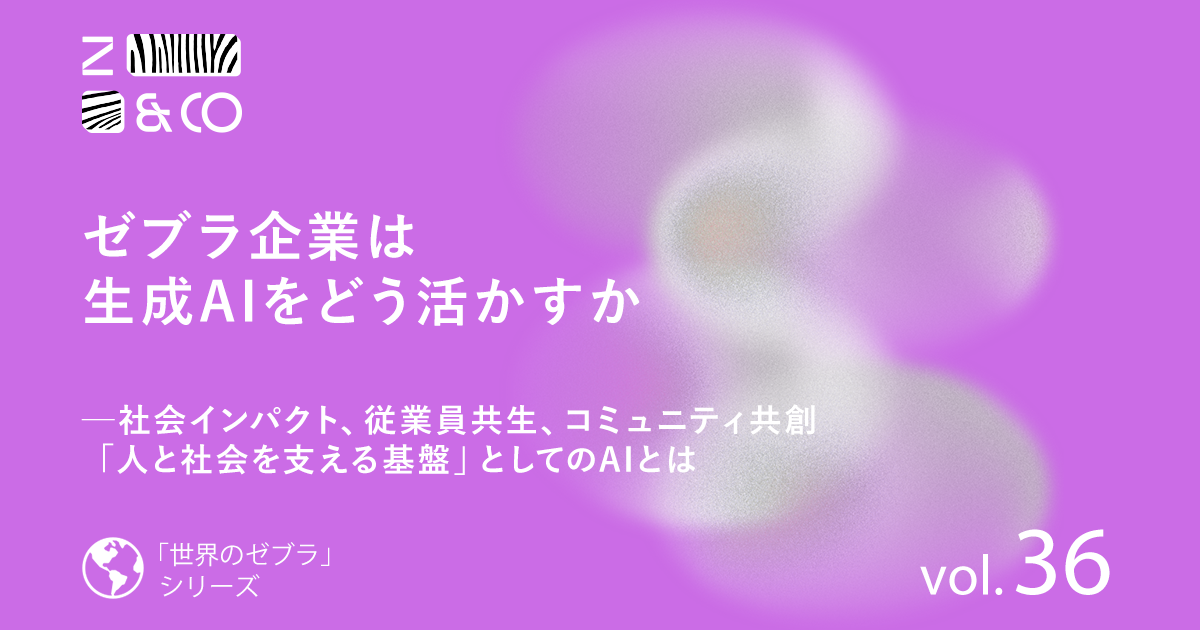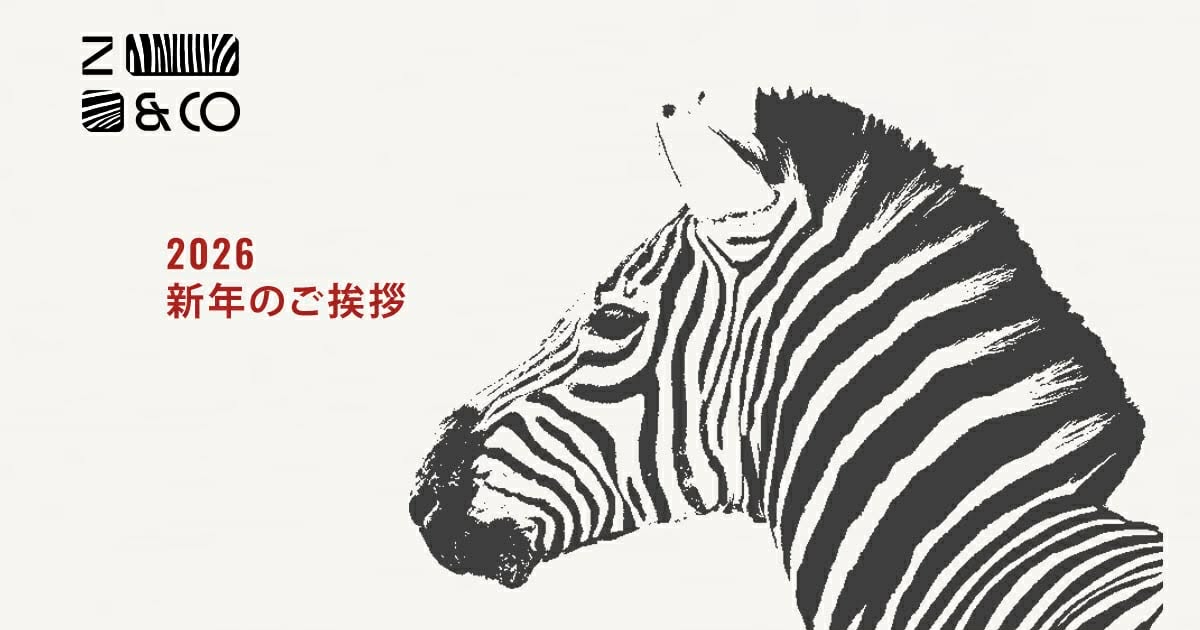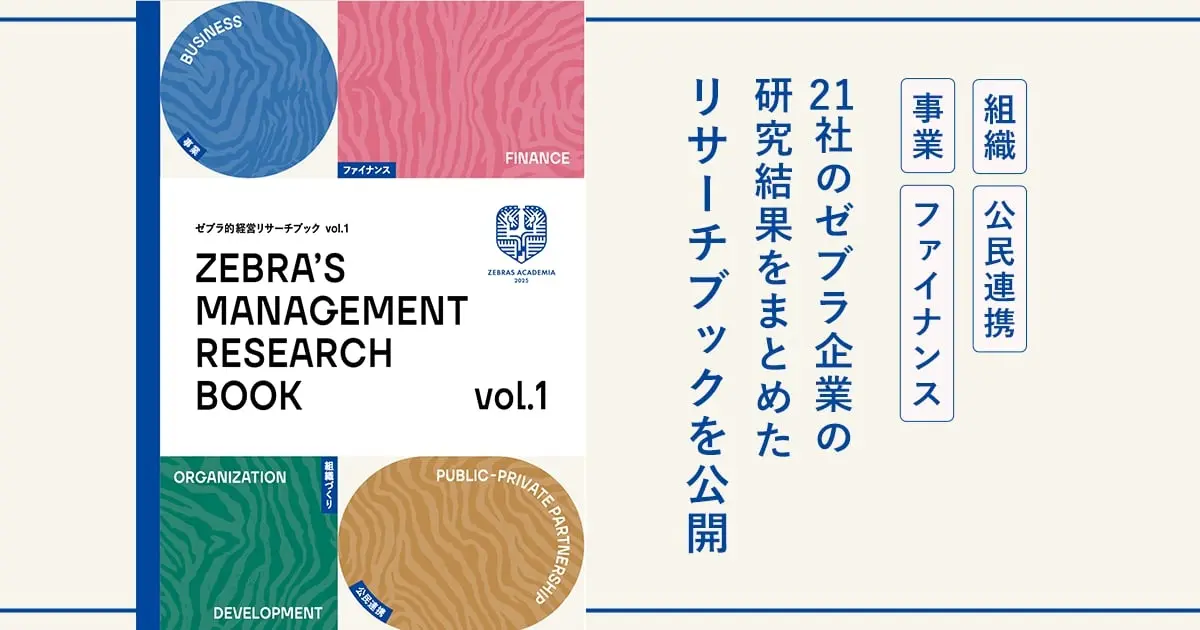2025.04.30 ZEBRAS
インパクトスタートアップ支援プログラムの舞台裏と、今後の支援に求められる考え方。TOKYO Co-cial IMPACT成果報告会から見えたこと

社会課題解決を通じた「持続可能性(社会的インパクト)」と「成長(経済的リターン)」の両立を目指す企業を支援するプログラムは、近年増加しています。しかし、その設計背景や現場でのやりとりに触れる機会は多くありません。そこで今回は、東京都が展開する社会的インパクト共創事業「TOKYO Co-cial IMPACT」をレポートします。
本プログラムは2024年7月から2025年3月にかけて実施されました。構成は二本立てになっており、前半は、起業家と支援者それぞれに対して、社会課題解決に必要な知見やネットワークを提供する「エントリープログラム」。後半は、起業家に対して、各分野の専門家が伴走するスタートアップスタジオ型プログラム「スタジオプログラム」です。
Zebras and Company(以下、Z&C)はエントリープログラムにて、ゼブラ企業をテーマにファイナンスや事業開発の講義を担当。また、支援期間の最後に開催された、スタジオプログラムの成果報告会「デモデイ」では、Z&C共同創業者の阿座上陽平(以下、阿座上さん)がパネリストとして登壇しました。
本レポートでは、デモデイの内容を中心に、参加者や運営者の声を交えながら、プログラムの実態やそこから得られた学びを紹介します。社会起業を目指す方や、支援に関心のある方にとって、何かしらのヒントとなれば幸いです。
起業家と支援者が“ともに”社会的インパクトを追求するTOKYO Co-cial IMPACT
「TOKYO Co-cial IMPACT」の名称に含まれる“Co-cial”は、「コレクティブインパクト」と「ソーシャル」を掛け合わせた造語。社会課題に挑む起業家の支援にとどまらず、自治体や企業、支援機関など、周囲の多様な立場の人々が協働する環境づくりを目指しています。
前半のエントリープログラムでは、社会課題解決型ビジネスの考え方や支援のあり方に関するインプットを実施しました。中でも重視されていたのは「社会課題はみんなで取り組むもの」という共通認識を醸成すること。こうした土壌を整えたうえで、スタジオプログラムでは、専門家による伴走支援やメンタリング、ネットワークの機会を通じて、スタートアップの起業家の事業構築や成長を支援しました。
デモデイの前半では、「社会的インパクトと経済的リターンの両立」をテーマに2本のパネルディスカッションを開催。社会課題解決に興味のあるオーディエンスに、中間支援者と起業家の視点から学びを提供しました。また、メインコンテンツである成果報告プレゼンでは、採択された起業家の事業構想とともに、協力を求めたい点も共有。オーディエンスの関わりしろが提示されました。
支援する側・される側という枠組みを超えたつながりを生み出す設計が、TOKYO Co-cial IMPACTの大きな特徴です。
社会的インパクトの共創には、異分野をつなぐ“翻訳者”が必要——インパクトスタートアップエコシステムに求められるもの
ここからは、パネルディスカッションの内容をお届けします。
2つあるうち、1つ目のテーマは「『社会的インパクト』と『経済的リターン』の両立を目指す企業の生態系」。登壇したのは、Z&Cの阿座上さん、一般社団法人インパクトスタートアップ協会の小池克典さん、株式会社ガイアックスの佐々木喜徳さん、一般社団法人スタートアップエコシステム協会の藤本あゆみさん(モデレーター)の4名です。

ディスカッションの話題は、「インパクトスタートアップ」の定義についてからスタート。佐々木さんは「スタートアップには、大きな市場を狙って立ち上げるケースと、社会課題を起点に始めて結果的に成長していくケースの2つがある」と整理しつつ、TOKYO Co-cial IMPACTでは後者に重きを置いていると語りました。
これに対し、阿座上さんは「社会的な信頼や価値は、短期的には売上に直結しないけれど、中長期的には経済性を生む構造につながっていく」と発言。また、小池さんは「テクノロジーの進化によって、新しい市場が次々と生まれている。少人数でも成り立つビジネスが増えてきている」と話し、今の時代ならではの成長の可能性を紹介しました。
続いて、資金調達や投資判断について、阿座上さんは、Z&Cの投資基準として「社会性・経済性・経営ガバナンス・相性」の4軸を紹介し、小池さんからは「コミュニティラウンドで信頼を積み重ねてから、次のステップへ進むケースも増えてきている」と、資金調達の新しい流れを紹介。
議論は、スタートアップの前提である「急成長」のメリットとデメリットにも及びます。佐々木さんは「巻き込む人が増えることで煩雑さも生まれるけれど、大きなビジョンに人が集まるメリットもある」と発言。阿座上さんは「スピードを持って成長することで注目を集め、モメンタムを生み出せるという利点もある」と話しました。
終盤では、「このエコシステムをどう強化していくか?」の問いに対して、小池さんが「公共調達や法制度の活用が、インパクトスタートアップの社会実装につながる」と展望を語ります。阿座上さんは「この領域にあまり触れていなかったメディアやアカデミアなども巻き込めるといい。そうした各分野をつなぐ“翻訳者”が必要」と発言。また、起業家と支援者それぞれが描くセオリー・オブ・チェンジが重なったときに、協働の価値が最大化されると強調しました。
最後に、藤本さんが「支援して・支援されて当たり前ではなく、お互いの役割や視点を持ち寄って重なる部分を探すことが大切」と場をまとめました。社会的インパクトと経済性を両立させるスタートアップの可能性と、その支援をめぐる実践知が詰まったセッションとなりました。
「2025年問題」は追い風。今こそ介護の制度と市場に変革を——介護領域の事業立ち上げのポイントと、今後の可能性
2つ目のパネルディスカッションのテーマは、「介護領域の社会起業家で見る、社会性と経済性の両立する事業の立ち上げ方」。登壇者は、テクノロジーで介護者支援を目指す株式会社abaの宇井吉美さん、介護ソフトウェアの開発を手がける株式会社Rehab for JAPANの大久保亮さん、訪問介護サービスを展開するイチロウ株式会社の細川寛将さんの3名。モデレーターを務めたのは、株式会社UNERI代表で一般社団法人IMPACT SHIFT代表理事の河合将樹さんです。
インパクトスタートアップの経営者が集ったこのセッション。冒頭では、介護領域におけるビジネス構築の難しさについて話されました。
宇井さんは、ものづくりの視点から「ご本人・介護者・購入者という最低3人のステークホルダーがいて、全員にとっての価値をつくらなければならない」と語り、製品開発と販売の難しさを紹介。大久保さんは、「良いものを作れば売れるわけではなく、導入側にとって売上につながるかどうかも重要」と購入者へのメリット提示の必要性を強調しました。
続いて、それぞれの事業のターニングポイントについても共有されました。細川さんは「普段、保険内のサービスを扱うケアマネージャーが、イチロウのような『保険外の訪問介護』も扱いたいと問い合わせしてくれたのが転機」と語り、予想外の販路が生まれたことを説明。大久保さんは、初期のサービスをある介護施設が導入してくれたことで、PoCやサービスの磨き上げができたといいます。宇井さんも、初期サービスを導入してくれた存在がいたことを語りつつ、自身もいち介護職として現場を経験したことが、サービスのブラッシュアップにつながったと話しました。
中盤では、団塊世代が後期高齢者となることで介護現場の負担が増加するといわれる「2025年問題」の議論に。宇井さんは「介護を必要とする高齢者が増える一方、介護の担い手は減るという構造的課題がより顕在化する」と解説。大久保さんと細川さんも「現行の保険制度だけでは対応しきれないからこそ、保険外の領域で新たな仕組みをつくるチャンス」と語り、今が大きな転換点であるという意味で「追い風」だと表現しました。
現行の制度や市場を変革する取り組みのひとつとして、宇井さんはすでにシンガポールでのPoCを開始していると紹介。「制度が異なるから、介護先進国である日本からの提案もしやすい。そしてそこから日本に逆輸入できるアイデアもでてくるかもしれない」と展望を語ります。モデレーターの河合さんも「海外の投資家は、日本のエイジテックに関心を寄せている」と補足し、グローバルな視点を持って介護領域に取り組む可能性を示しました。
制度と現場の狭間を縫いながら、介護の現実に向き合う3人の起業家。それぞれの立場から培った視点と実践をもとに、介護業界の未来を切り開こうとする意思が見られたパネルディスカッションでした。
採択者プレゼンと審査から見えた、TOKYO Co-cial IMPACTが起業家に求める資質
続く成果発表会では、スタジオプログラムに参加した6名の起業家が、それぞれの取り組みと今後の展望についてプレゼンテーションを実施。本レポートでは、審査員の質問内容と、最優秀賞・オーディエンス賞の選考理由から、インパクトスタートアップに求められる要素をまとめました。
各プレゼンの後には、審査員から多角的な質問が投げかけられました。たとえば「法制度や市場の中で、どこに事業のハードルがあるのか」「マス展開をどのように実現しようとしているのか」「なぜ自分がこの課題に取り組むべきなのか」といった問いです。
こうした質疑を通じて見えてきたのは、インパクトスタートアップに求められる視点と資質。社会課題に対する深い理解と独自の切り口、法的・制度的な制約への対応力。また、ユーザー体験だけでなく、連携先の企業や自治体にとって導入する意義が明確であること。さらには、「今、何がボトルネックで、何があればスピードアップできるか」といった、成長のための次の一手をクリアにし、挑戦し続ける粘り強さも重視されていました。
最優秀賞に選ばれたのは「Quick」の武田淳宏さんです。評価されたのは、現場視点に基づいた提案と、PoCを含む実装準備の確かさ、そして救急医療の構造的課題を現場視点で多面的に捉える姿勢でした。また、オーディエンス賞に選ばれた「ポチキフ」の小室拓巳さんは、「複雑な課題をシンプルに届けて共感を呼んだ」ことが評価されました。
こうした審査のやりとりから、インパクトスタートアップには「社会課題やステークホルダーの理解」「確かな構想をもとにした実行力」「共感を生むコミュニケーション」が必要なことが伝わってきます。総評では「本当の審査員はサービスを待ち望む受益者である」という視点も示され、初期仮説を着実に検証・改善するプロセスこそ重要だと強調されました。今後、各事業が形を変えながらも社会にどのようなインパクトをもたらすのか、その展開が注目されます。
ビジョンが磨かれ、事業の進め方を再考できた——採択者の声
デモデイ終了後、Trip Doctorの佐々木蓮さんにスタジオプログラムの感想を伺いました。佐々木さんによると、プログラムで得られたものは大きく3つ。ひとつは、メンターや支援者との壁打ち、受益者へのヒアリングを通じてビジョンがブラッシュアップされたこと。次に、構想していたビジネスの制度的なハードルが見え、スモールスタートで別の事業モデルに踏み出す決断ができたこと。そして、サービスに必要なLPの作成時に、Co-cialのデザイナーから実務的な手厚い支援を受けられたことも印象的だったと振り返りました。
一方で、起業家同士のつながりや自治体・地域との接点をさらに増やすことで、相互学習やマッチングの可能性が広がるのではないかと、改善案も共有してくれた佐々木さん。こうしたプログラムへの参加を検討する人に向けては、「ビジョンや構想がふわっとしていても、興味があるなら飛び込んでみてほしい」といい、一歩を踏み出すことの重要性を語りました。
柔軟な支援形態と、ステークホルダーの巻き込み設計が鍵——企画者の振り返り
最後に、TOKYO Co-cial IMPACTの業務責任者のデロイトトーマツリスクアドバイザリー合同会社マネジャー石塚理博さんに、プログラムの手応えと今後の展望を聞きました。
まず石塚さんは、「スタジオプログラムへの応募が100件を超え予想以上の関心を得られた」と手応えを語ります。一方で、起業家と参加企業・支援者との協業やオープンイノベーションへとつなげる点には、さらなる工夫が必要だと感じたそうです。また、支援プログラムについては、「スタートアップ支援」にとらわれない柔軟なアプローチの重要性を実感。令和7年度からは、起業家を生むスタジオプログラムに加え、起業済みのスタートアップ・ゼブラ企業に対する「アクセラレーションプログラム」の新設を予定しているそうです。成長フェーズの事業者に対して、社会的インパクトの可視化や資本政策の支援を提供していきたいと意気込みを語ってくれました。
近年こうした支援プログラムが増えていることを踏まえ、今後の設計におけるヒントを尋ねると、石塚さんは2つのポイントを挙げました。ひとつは、起業家自身が社会課題をスケールの視点で捉え、ビジョンを大きく描けること。もうひとつは、どのようなステークホルダーを、どう巻き込むかという構造の設計です。TOKYO Co-cial IMPACTでは、その仕掛けとして、協働の重要性を理解してもらうためのステークホルダーも参加できる基礎的な知見を提供するエントリープログラムや、スタートアップ支援とインパクト支援の両視点を持つ多様な支援者と座組を構成することを意識的に設計したといいます。さらに、地域の課題解決には、都市部の支援者が直接介入するのではなく、現場に精通した中間支援者を地域ごとに育てていく体制づくりが重要なのではないかと語ってくれました。

PROFILE
Fumiaki Sato
編集者・ライター・ファシリテーター。「人と組織の変容」を専門領域として、インタビューの企画・執筆・編集、オウンドメディアの立ち上げ、社内報の作成、ワークショップの開催を行う。趣味はキャンプとサウナとお笑い。