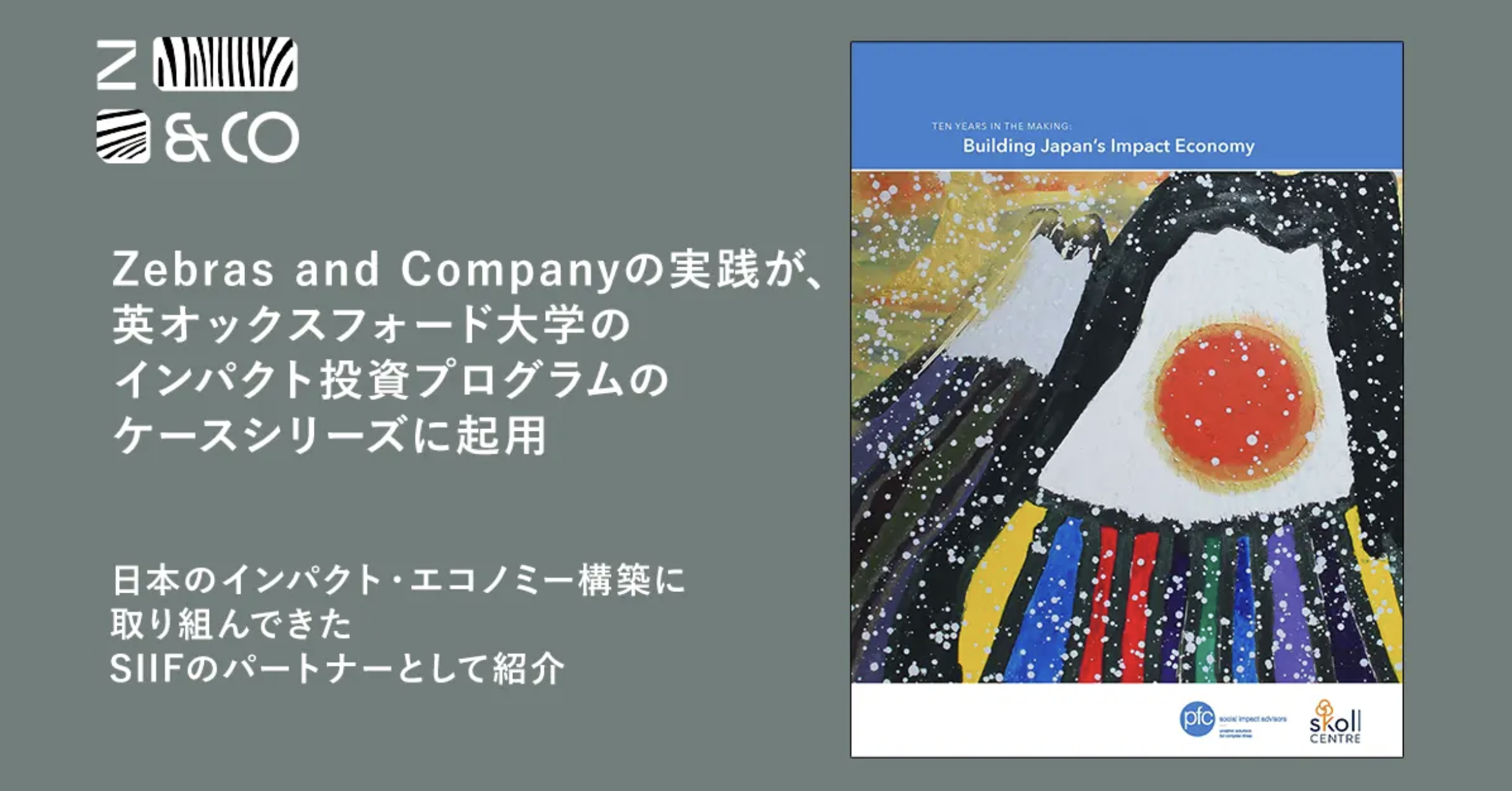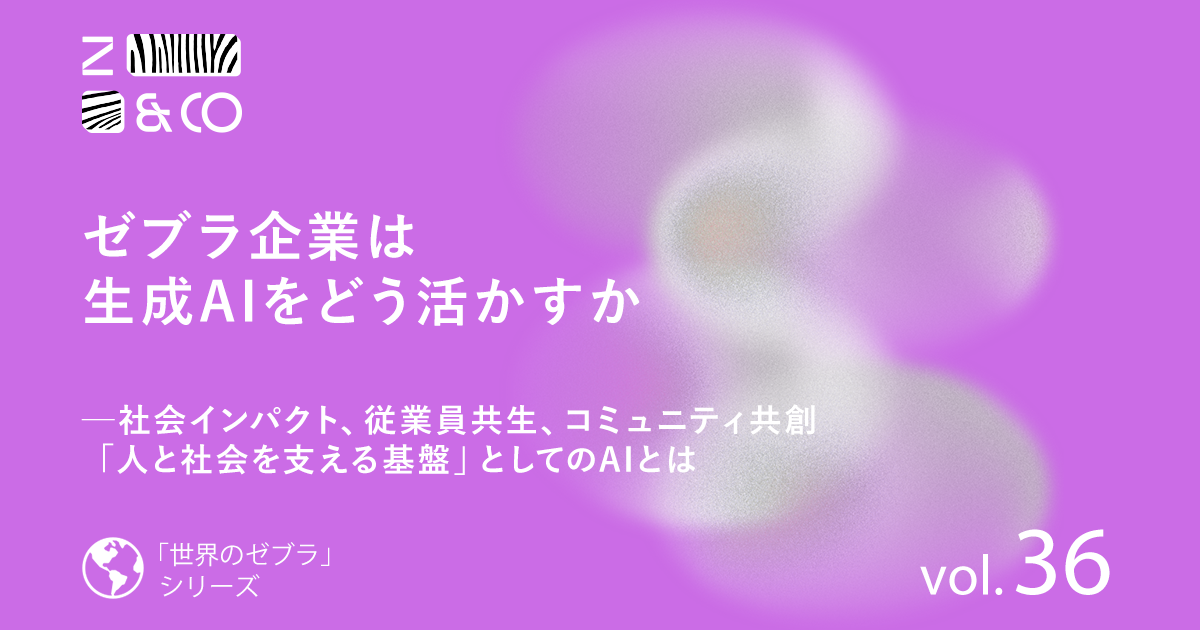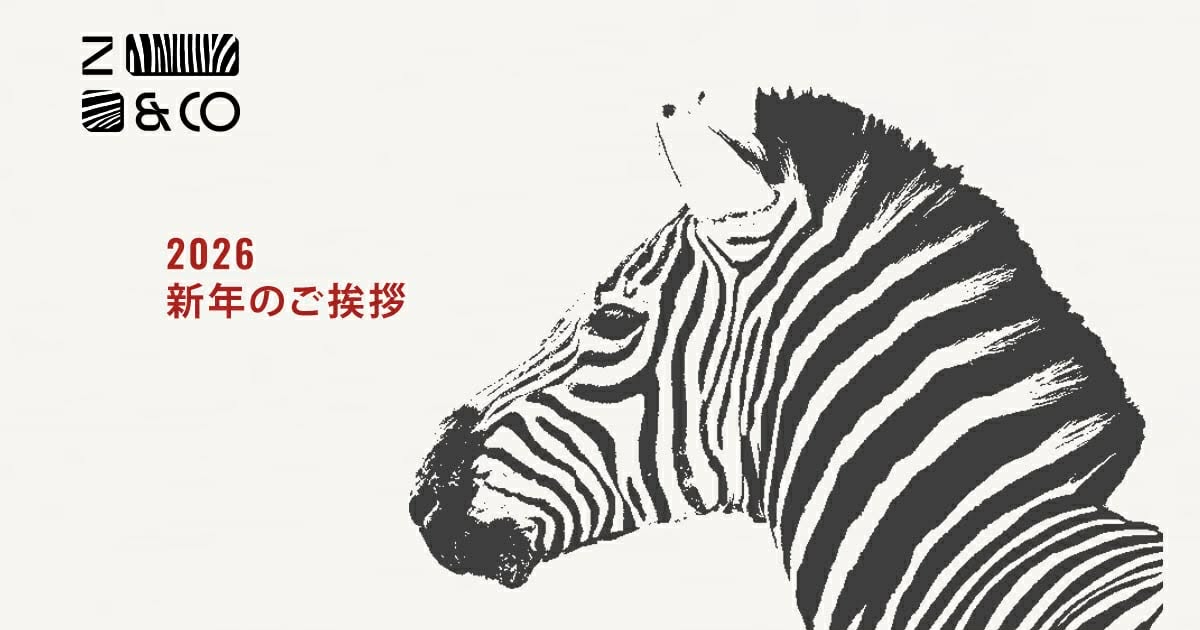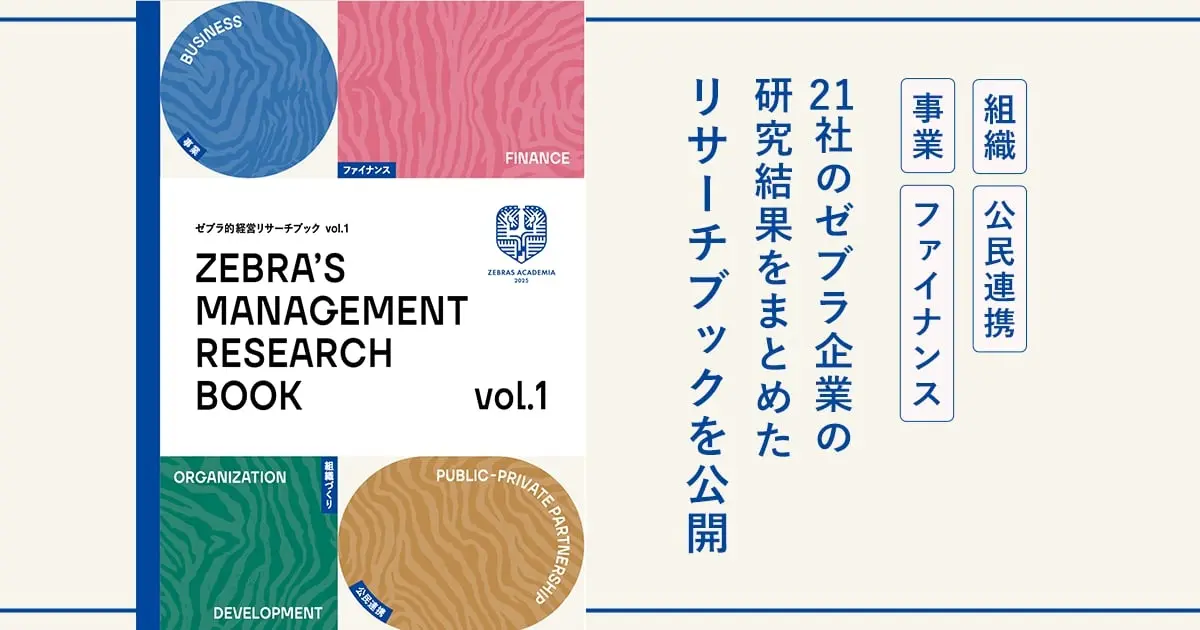2025.10.09 ZEBRAS
公正な働き方と人々の幸福へ:未来を拓くシステムチェンジ

大阪・関西万博の「ウーマンズ パビリオン」「WA」スペースで7月28・29の両日、「ジェンダーの視点から未来の経営と社会システムを考える」と題した一連のセッションが開催されました。この企画は、従来の経済成長に偏らない、公正で持続可能な社会をジェンダーの視点から考えることを目的に、ゼブラアンドカンパニーが一般財団法人社会変革推進財団(SIIF)と共同で手掛けたものです。
本稿では、28日に行われたセッション「公正な働き方と人々の幸福へ:未来を拓くシステムチェンジ」をレポートします。
このセッションでは「子供や孫の世代まで残したいと思える未来を築くため、社会の仕組みやシステムをいかに変革すべきか」という問いを参加者と共に深めることを目指しました。モデレーターはSIIFインパクト・エコノミー・ラボのインパクト・カタリストである川端元維さんが務め、ラヴィベル株式会社代表取締役の佳山奈央さん、組織開発コンサルタントの勅使川原真衣さん、三菱UFJ信託銀行サステナブルインベストメント部フェローの加藤正裕さんが登壇しました。

経済と暮らしの共存は可能か
セッションの核心的な問いは「資本主義社会において、経済の発展と日常のウェルビーイングは本当に共存するのか」というものでした。
モデレーターの川端さんは冒頭、資本主義を現在の経済と暮らしの前提にある「ルール」と定義し、物やサービス、人の労働力、会社の意思決定権にまで値段がつき、お金を払えば個人や法人が影響力を拡大できる世界の現状を説明。その上で、個人の幸せな暮らしと、社会を破綻させない、真に社会を豊かにする経済活動が共存できるのかという問いを提示しました。

川端さんは、日本のジェンダー格差の現状にも触れ、問題解決には単に目に見える数字(女性役員比率、賃金格差など)を改善するだけでなく、「システムチェンジ」という概念が重要であると強調しました。
システムチェンジとは、社会・環境システムの機能や構造に働きかけ、複雑な問題を根本的に解決することであり、目に見える「氷山の一角」だけでなく、その根底にある原因や構造、価値観、文化に目を向け、新しい仕組みや世界のあり方を提示することを目指します。SIIFは、このシステムチェンジの考え方に基づき、長野県上田市でジェンダーペイギャップ解消に向けた投資活動を行っているといいます。
川端さんはさらに、個人、組織、社会・経済の三つの次元で起きている「綱引き」という概念を提示しました。これは、市場の発展や成果創出といった経済活動と、人権、公正、個人の脆弱性、自己や他者へのケア、環境維持といった側面との間の葛藤を指します。この「綱引き」をどうやりくりするかが、究極的には人類の幸福やジェンダー公正の実現に不可欠であると述べました。
子育ての「当たり前」を覆すPORTOの挑戦
最初の登壇者である佳山さんは、セッションの問いかけを「個人のキャリア・機会と、自己や家族へのケアとの綱引き」という側面から捉え、特に子育て世代の大人たちのウェルビーイングの重要性を強調しました。
佳山さんが神戸三宮で運営する複合サービス施設「PORTO」は、この課題に取り組むための具体的な場所。子育て世代のウェルビーイングをビジョンに掲げ、親子が一緒に過ごせる保育士常駐のプレイスペース、一時保育、子連れで楽しめるバー、イベントなど、様々なサービスを一つの空間で提供しています。
佳山さんによれば、PORTOの特徴の一つは、利用者の約4割が父親である点。これは、空間の色使いやインテリアを男女問わず落ち着くデザインにしたり、イベント告知に「お母さん、お父さんのための」と明確に記載したりするなど、意識的な工夫によって実現されているといいます。父親が子連れで利用する際の心理的ハードルを下げ、「ここはパパが来てもいいんだ」と思わせる細やかな配慮がなされています。

また、一時保育では、利用理由を問わず(美容室や買い物、リフレッシュのためなどでもOK)気軽に子
供を預けられるようにしており、保育士が例えば「髪型綺麗になられましたね」「楽しかったですか」と親の自己リフレッシュを肯定する声かけをすることで、親が罪悪感を感じず、自分を大切にできるような環境を提供していると言います。佳山さんは「親が自分を大切にしながら子育てできることが、子供がのびのび育つためにも重要である」という考えを、スタッフ全員が共有していると述べました。
佳山さんの活動の背景には、彼女自身の幼少期の経験と子育て経験があります。シングルマザーとして4人の娘を育てた母が、子供たちのために自己犠牲を払う姿を見て「自分がいることで母がボロボロになる」という子供の側の苦しさを感じたこと。また、19歳で出産しシングルマザーとして子育てをする中で「早くからたくさん預けてかわいそう」といった周囲の言葉に疑問を感じ、「親が自分の人生を大事にできないと、子供に背中を見せられない」という思いを抱いたことが、現在の活動の原点となっていると話しました。

能力主義という巧みな社会システム
続いて登壇した勅使川原さんは、教育社会学を専門とし、企業が求める人材像や「能力」という概念を批判的に見てきたと自己紹介しました。彼女は、能力開発の業界に身を置きながらも、「人を開発する」という考え方に疑問を感じ、人が活かされていない組織を減らす「組織開発」の道に進んだと言います。自身の乳がんステージ3Cの診断と闘病の経験を経て、執筆を通じた啓蒙活動も行うようになりました。
勅使川原さんの主なテーマは「能力主義」への批判です。彼女は能力主義を、かつての身分制度に代わって近代化の過程で生まれた「巧みな社会システム」「配分原理」であると説明しました。能力主義は「できる人が多くをもらい、できない人は仕方がない」という論理で社会の納得性を得てきましたが、令和の現代においてもこれに代わる原理は見出されておらず、個人に絶えず「能力獲得」や「成長」を促し、そうでなければ将来がないと煽る「自己責任社会」につながっていると指摘しました。
しかし、勅使川原さんは、能力は個人の臓器のように固定的に内在するものではなく、可変的で状況依存的であると主張します。参加者の態度次第で会議での発言のしやすさが変わる例を挙げ、能力はその人らしさと環境との組み合わせ、相性によって大きく影響されると述べました。したがって、社会を変える、社会変革とは、個人の問題を指摘するのではなく、私たちが選択してきた能力主義という「社会システム」そのものを変えていくことだと訴えました。
「声なき声」をどう拾うべきかという問いに対しては、組織の中で「全員すべからく弱い前提」で、弱さを開示し合う場を作ることが重要だと述べました。能力主義に染まっていると、弱音を吐くことや疑問を呈すること自体が「能力が低い」と見なされることを恐れ、自己抑制してしまうため、お互いの弱さをジャッジせず、とにかく聞き合うこと。そこから助け合いが生まれるのだと説明しました。

システムチェンジ投資という新たなアプローチ
3人目の登壇者である加藤さんは、投資家の立場からセッションに参加しました。従来の投資家は、企業の利益や成長可能性を重視し、株の売買を判断することで運用リターンを高めることを基本としてきたと述べました。しかし、2005年頃から環境や社会の取り組みも考慮する「責任投資」が広がり始め、その後、「インパクト投資」への関心も高まりつつある中、最近はSIIFと共に取り組んでいる「システムチェンジ投資」という考え方が注目され始めているといいます。
加藤さんが強調したのは、環境・社会への配慮は「特別」なことではないということです。これらを考慮することは、投資家が見る領域を広げることであり、これまで見えていなかった投資機会やリスクを発見し、結果として投資収益を向上させ、リスクを下げる可能性を秘めていると語りました。例えば、工場建設は単なる金銭的投資だけでなく、地域の雇用創出や貧困率改善といった社会貢献にも繋がるとし、企業の活動を財務面だけでなく環境・社会面からも包括的に評価することが重要であると説明しました。
さらに、「システムチェンジ投資」について、加藤さんは既存のインパクト投資との違いから説明しました。インパクト投資が製品やサービスが生み出す直接的なポジティブな影響(例:EVによるGHG排出削減)に焦点を当てるのに対し、システムチェンジ投資は、例えばサプライチェーンのあり方全体を見直すことなどを通じて、社会の構造的な課題を根本的に解決することを目指します。
このアプローチをとるには、投資家は従来のように企業とだけ対話しているのでは不十分で、有識者や市民社会など、より多くの多様なステークホルダーとの対話と協働が不可欠であると強調しました。投資家が「運用の考え方や情報の活用方法など」を自ら開示し、企業の属する業界や課題、新たな価値観や考え方について謙虚に学ぼうと努力することは、必要な知識を得るというだけでなく、信頼感を醸成し、より深い議論に繋がると説明しました。

越境対話と時間をかける勇気
セッションを通じて、3人が共通して強調していたのが、多様な立場の人同士で対話をすること、そして「時間をかける勇気」を持つことの重要性でした。
勅使川原さんは、成長とは「螺旋的」に進むものであるとし、一見堂々巡りや行きつ戻りつに見えても、立体的に見れば着実に上に上がっていくのが現実的な成長のあり方であると述べました。能力主義が人を早く否定する傾向にあるのに対し、一度立ち止まり、判断を急がない勇気の重要性を示唆しました。
加藤さんもまた、投資においては「できなかったからバツ」と安易に判断するのではなく、なぜできなかったのか、どう改善しようとしているのかを深く聞き、相手の立場に立って考えることが、信頼関係を築き、より良い協力関係に繋がるのだと述べました。
佳山さんは今回のセッションを通じて、個人、組織、社会・経済という三つの異なるレイヤーが混ざり合い、領域を超えて対話することの重要性を改めて感じたと述べました。子育て世代に限らず、誰もが心身の波や制約を抱える中で、特定の個人への「配慮」に留まらず、組織の給与体系や人材開発、さらには資金の流れといった各フィールドで同じ視点を持って取り組むことが、システムをじわじわ変えていく力になるだろうと語りました。


PROFILE
ゼブラ編集部
「ゼブラ経営の体系化」を目指し、国内外、様々なセクターに関する情報を、一緒に考えやすい形に編集し、発信します。