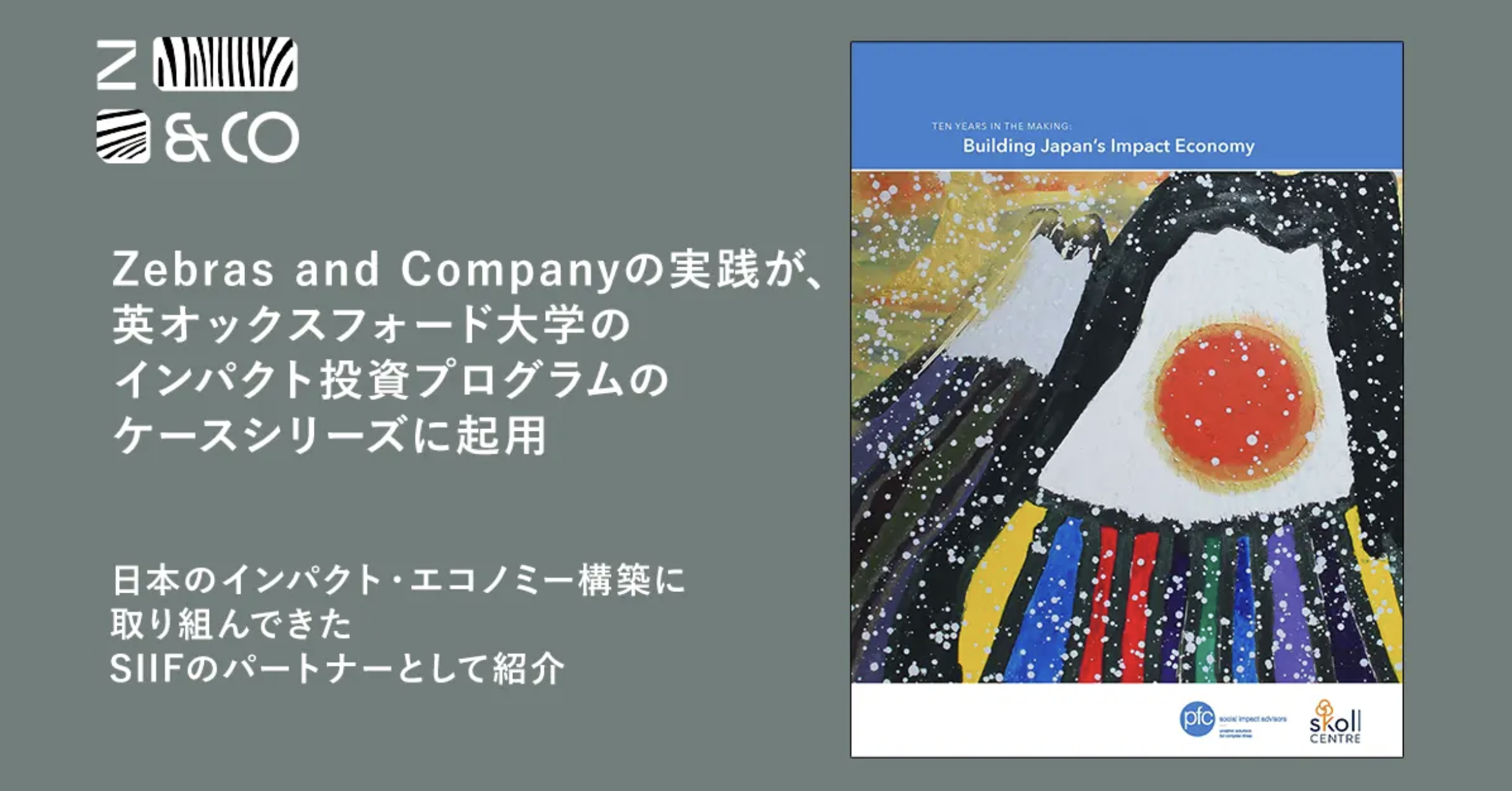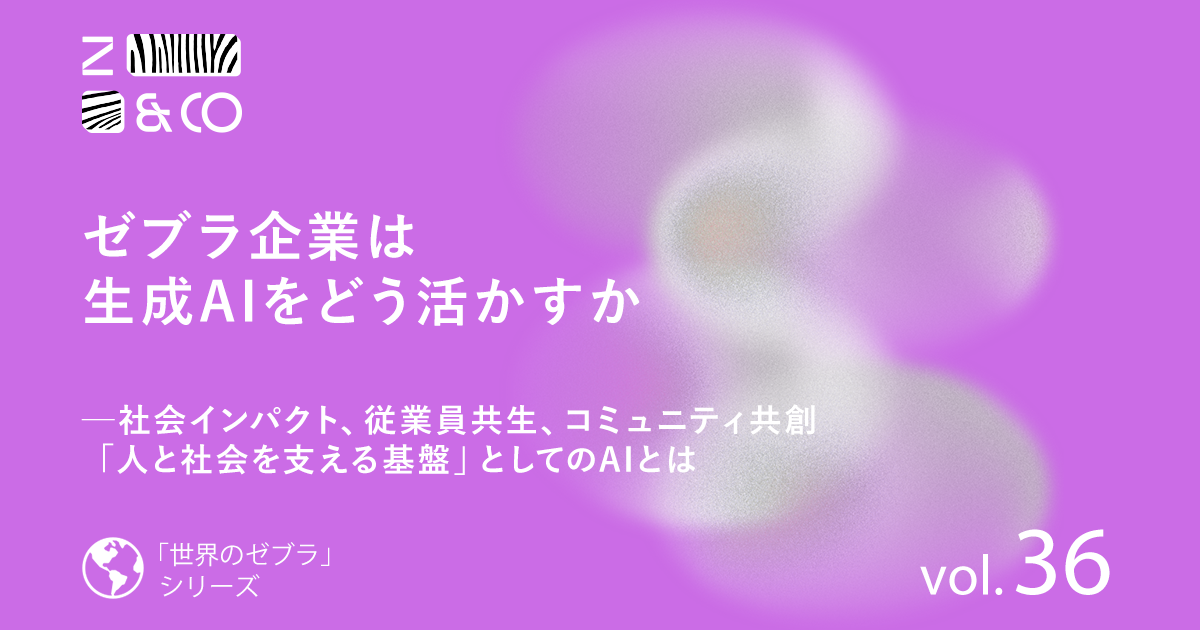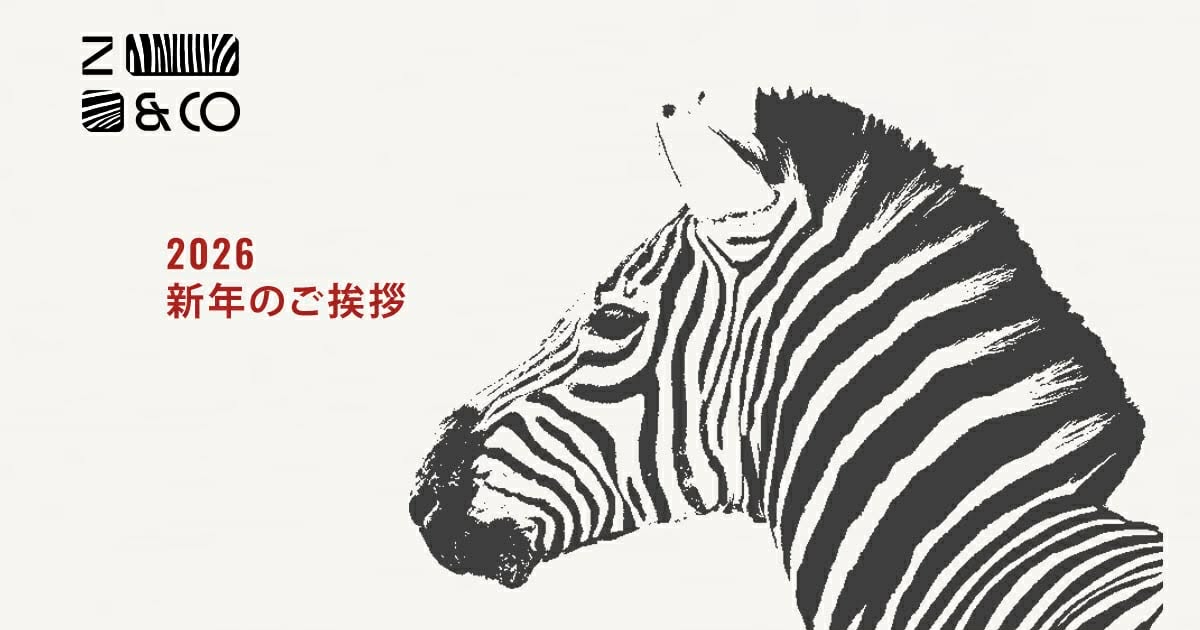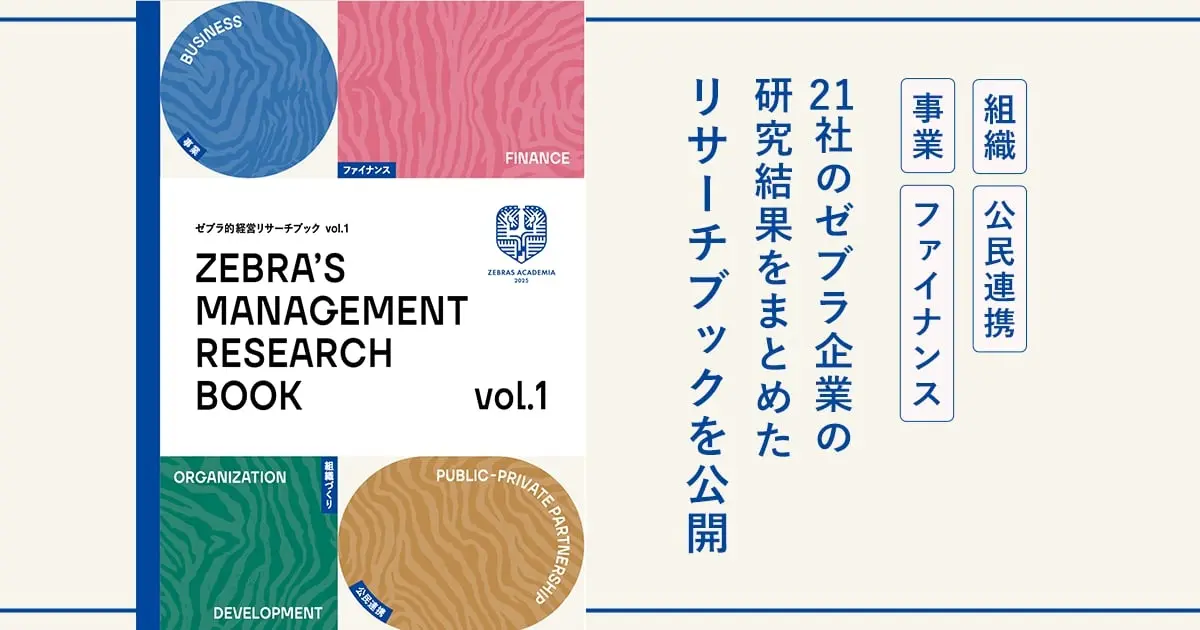2025.10.07 ZEBRAS
「地域の未来は、となりの人の笑顔を作ることから」 —福島ローカルゼブラ会議から見えた“地域経営”の現在地—


「ここにいる人たちは、ただの経営者じゃない。地域という会社の株主だと思うんです。」
福島県で開催された「ローカルゼブラ会議」には、震災から十数年を経た今、あらためて地域と向き合い、未来を築こうとする起業家や事業者が集まった。登壇者は、76年の歴史を持つ老舗企業の3代目社長、震災後に建設業で地域復興に取り組む経営者、東京から移住して廃墟を活用した新しい事業を展開する若手起業家、そして伝統的な酒造業に革新をもたらすクラフトサケの醸造家という、多様な背景を持ち、それぞれの立場で“稼ぐ”と“支える”を両立しようとする実践者たち。
この会議の背景には、「ゼブラ企業」という新しい経営哲学がある。白と黒の縞模様のように、社会性と経済性を両立しながら、群れとして連携し、現実に根ざした存在として地域と共に生きる──そんな企業を指すこの言葉は、急成長とスケーラビリティを追い求めるユニコーン企業とは対照的な価値観を持っている。
なぜ、今「地域経営」なのか?
「地域経営」という言葉には、行政任せではなく、自分たちの手で地域の未来を形づくっていこうという意思が込められている。震災という極限の体験を経た浜通り地域では、自治体・企業・個人がそれぞれの限界を知った。その中で求められたのが「連携」と「自律」だ。
タイズスタイル代表の吉田さんは語る。
「震災後、町には誰もいなかった。猿と鹿だけがいるような状態。でも、だからこそ、人が戻ってくるために最初に必要なのは、泊まる場所、食べる場所、仕事だった。」

建物を再生し、ホテルをつくり、商店街を再構築する。経済性が見込めない段階でも、“先に場を用意する”という行動には、地域の未来を信じる覚悟があった。
「稼ぎ三割、務め七割」という地域経営の美学
鳥藤本店代表の藤田さんが紹介したのが、江戸しぐさに通じる「稼ぎ三割、務め七割」という考え方だ。商いの利益よりも、となりの人を助けること、役に立つことに人生の大半を使うという価値観は、現代の持続可能な地域づくりに強く通じる。
これは、単なる精神論ではない。
「社会に良いことをしたい会社が、お金儲けだけをしたい投資家から資金を受けると、やりたいことができなくなる。」

この言葉が示すのは、資本と志の一致の重要性だ。補助金や行政支援を“手段”として活用しながらも、依存しすぎず、自分たちの色に合った資金を選び取る姿勢が求められる。
「自立型地域経営」の兆し:ゼブラ的視点
地域を支える企業には、さまざまな“ゼブラのかたち”がある。
- 地域の老舗企業が、若い起業家のチャレンジを後押しする「兄ゼブラ」
- 補助金に頼らず、ツアーやクラフトサケで外貨を稼ぐ「子ゼブラ」
- 自治体や大学と連携してインフラや文化を再生する「親ゼブラ」
それぞれが異なるフェーズやリソースを持ちながらも、「地域の未来にとって本当に必要な事業か?」という問いを共有している。
“地域のKPI”は、米の売れ行き?
一見ユニークな提案として会議で語られたのが、地域全体で「お米の売れ行き目標」を共有し、達成を目指すという仕組みだ。
「米農家がどれだけ売れたか、その情報をみんなで共有できたら、それだけで地域の応援になる。」
これは象徴的なアイデアであり、事業の収益や投資回収率とは別に、「地域が応援し合う力」がKPIになり得ることを示している。
世界一チャレンジできる場所としての“福島”
MARBLiNG代表の矢野さんは、「福島は世界で一番チャレンジができる場所だ」と断言した。その言葉の裏には、極限を生き抜いた地域ならではの“失うものがない”自由さと、未来に対する渇望がある。彼女は東京芸大を卒業後に浜通りへ移住し、廃業したホームセンターを「実験的な地域ラボ」として再生した若手起業家だ。
「東京で10の努力をしても10の評価をもらえるとは限らない。でも福島では、10の努力に15の評価を返してもらえる空気がある。」
震災の記憶が、地域を変えた。過去を乗り越えて生きる人々は、痛みと希望を引き受けながら、誰よりも自由に、新しい選択をしている。

アーティストや研究者、地元の高齢者、学生たちが集まり、ワークショップや実験、商品開発が行われるこの場所について、「社会性・創造性・経済性が交差する場として注目されている」と語った。
経済性を忘れない「社会企業家」の意識
社会課題への情熱はもちろん重要だが、「稼げる構造」への現実的なまなざしも、この地域のゼブラたちは持ち合わせている。
「この地域で稼げる会社をつくれば、大きなものに依存しない自律的な構造を築ける。」
これは単なる理想論ではない。クラフトサケという新ジャンルをつくり、農家のレシピを復活させながら、全国に販路を持つ酒蔵をゼロから築いた佐藤さんの言葉だ。小規模ながらも自らを「未来の地域インフラ」と位置づけ、物流・観光・文化までを含めたエコシステムを描いている。

「自分で選んだ地域」だからできること
この地域に集まった多くの人々が、口を揃えて語るのが「ここに来たのは自分の意志だ」ということだ。誰かに頼まれたからでも、逃げてきたわけでもない。そこには、自分の手で未来を創りたいという強い自発性がある。
それゆえ、彼らは“登場人物”になる覚悟を持っている。地域の主人公として、対等な関係で関わる。その姿勢が、行政や企業を巻き込む力となり、地域全体を推進させているのだ。
地域経営の鍵は「隣の人を喜ばせる」こと
会議の終盤、参加者の間で共有されたキーワードがある。それが、「隣の人を喜ばせる経営」だった。
これは、経済理論でもマーケティング戦略でもない、日々の所作に宿る哲学だ。
「隣の人が笑ってくれる仕事をしよう。
自分の小さな灯りが誰かを照らせば、それが地域全体を明るくする。」

この言葉は、登壇者のひとりが引用した「一灯を照らす者、これ国宝なり」という言葉にも重なる。経営のスケールではなく、半径数メートルに灯る小さな光。それを重ね合わせていくことが、真の“地域経営”なのだ。
まとめ:ゼブラ経営という生き方
福島ローカルゼブラ会議は、単なる経営者の集まりではなく、「どう生き、どう地域と関わるか」を問い直す場でもあった。
ここから私たちが学べることは多い。
- 社会性と経済性の両立は可能である
- いずれ「自分たちの地域を自分たちで経営できる」日を迎えるために、挑戦は始まっている
- 困難な場所こそ、可能性に満ちている
- 地域の未来は、隣の人を喜ばせるところから始まる
そして何より、「自ら選んだ場所で、自分の光を灯す」という意思が、新しい地域社会の姿を形づくっていくのだ。


PROFILE
ゼブラ編集部
「ゼブラ経営の体系化」を目指し、国内外、様々なセクターに関する情報を、一緒に考えやすい形に編集し、発信します。