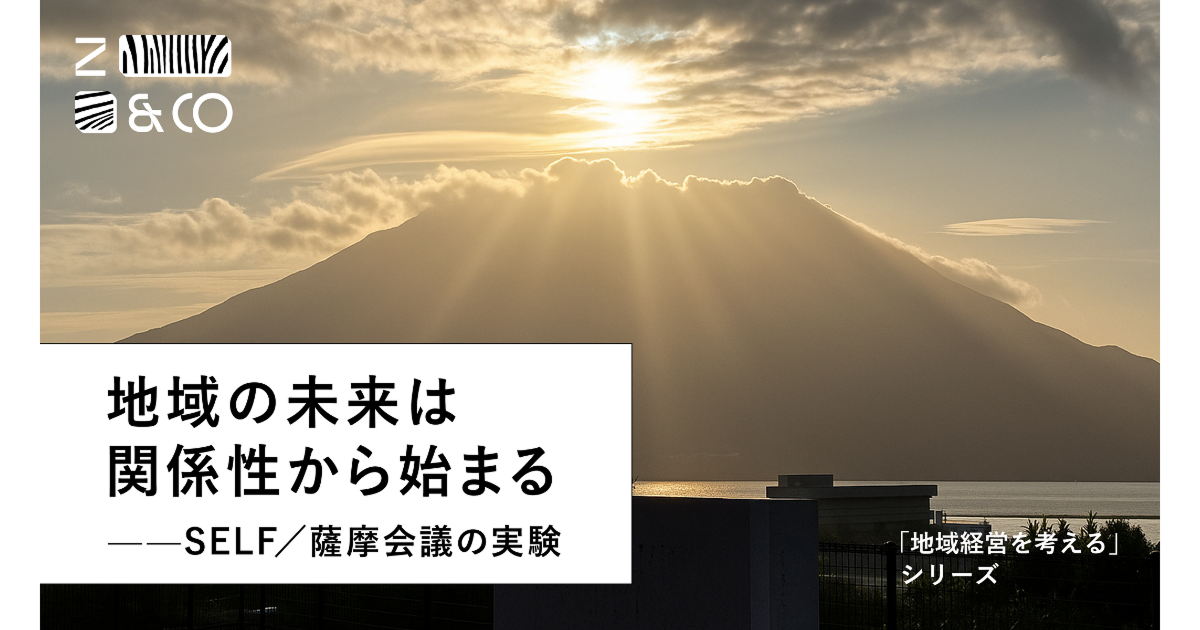2025.08.25 ZEBRAS
自然を“測り、育てる”ゼブラたち──テックが耕す0次産業の未来

自然の“スコア”が企業を動かす時代に
「自然は大切にしなければならない」——その言葉に異を唱える人は、もうほとんどいないでしょう。しかし実際の社会では、自然環境を守ることに対して、どれほどの資金や技術が投じられているでしょうか。守ることの大切さが語られても、具体的な評価や対価が伴わなければ、自然は依然として「経済の外側」に置かれたままです。
そんな状況を変えようとする動きが、いま世界のあちこちで静かに始まっています。森や湿地の保全、生物多様性を支える農業や養蜂といった営みに対して、「どれだけ自然にポジティブな変化を与えたか?」を定量的に測定し、その成果に経済的な価値を与えるという発想です。
この流れのなかで登場してきたのが、自然を“見える化”し、“測定”し、“報いる”仕組みを開発するスタートアップや非営利のサービスたちです。彼らは、自然を搾取や保護の対象としてだけではなく、「共に育てていく経済の一部」として再定義しようとしています。
本稿では、イタリア発の企業「3Bee」を中心に、ブラジルや北米での事例も交えながら、自然とテクノロジー、そしてゼブラ的な価値観の融合についてご紹介します。
ミツバチが教えてくれる、自然の現在地──3Beeという企業
出典:3Bee
3Bee(スリービー)は、イタリアのミラノ近郊で2017年に創業されたネイチャーテック企業です。もともとは、地元の養蜂家を支援するために、巣箱の状態を遠隔からモニタリングできるIoTセンサーを開発したのが始まりでした。養蜂は、環境の変化に極めて敏感な産業です。気温の急変、農薬の影響、花の開花タイミングのズレなど、微細な変化がミツバチに大きな影響を与えます。
3Beeは、この“ミツバチが持つセンサー的な感受性”に着目し、やがてそのデータを生態系の健全性を測る指標へと発展させていきました。現在は、養蜂のみならず、森林、草原、農地など多様な生態系にセンサーやAIを導入し、自然環境の変化を可視化する「Biodiversity Index(生物多様性指数)」を開発・提供しています。
この指数は、植物の種類や密度、昆虫や鳥類の活動量、土壌の状態など、複数の環境要素をもとに構成されており、3Beeが提案する「Biodiversity Credit(生物多様性クレジット)」の基礎にもなっています。自然を守ったという実績を、データにもとづいて“価値”として認証する仕組みです。
特徴的なのは、3Beeが単なる気候テック企業ではなく、ゼブラ的な理念を持つ点です。たとえば、収益性のある事業モデルを維持しつつも、ローカルな養蜂家や農家との協働を重視し、テクノロジーの恩恵が地域の生業や生態系に循環することを意識した仕組みづくりを行っています。
こうした取り組みは、環境保全と経済性の二項対立を乗り越えようとするゼブラ的アプローチそのものであり、新しい“0次産業のインフラ”をつくろうとする動きでもあるのです。
出典:3Bee
なぜ今、注目されているのか?──制度と企業の変化
3Beeのような取り組みが欧州で急速に注目され始めた背景には、制度面と企業側の意識変化という2つの大きな流れがあります。
ひとつは、EU(欧州連合)が進めている「ネイチャークレジット市場」の制度設計です。2025年7月、欧州委員会は正式に制度構築に乗り出すと発表しました。この制度は、森林再生や湿地の保全、生物多様性の回復といった自然環境への貢献を“クレジット”として認証し、企業がそれを購入することで支援できるようにするものです。
背景には、生物多様性の保全に必要とされる年間投資額がEU全体で約370億ユーロ(約6兆円)に上る一方で、既存の公的資金では大きく不足しているという構造的課題があります(出典:Reuters)。
このギャップを埋める手段として、ネイチャークレジットは「自然を守る行為に報酬を与える」制度として位置づけられています。制度の設計には、科学者やNGO、地域住民、農林業関係者などが参加することになっており、多様なステークホルダーの視点を取り入れながら進められています。
もうひとつの流れは、企業サイドの変化です。特にESG(環境・社会・ガバナンス)投資の拡大とともに、「自然をどう測るか?」「環境への貢献をどう可視化するか?」といった問いが、経営戦略の一部として浮上しています。たとえば、LVMHやNestléといったグローバル企業は、生物多様性に対する投資や可視化の手法を模索し始めており、3Beeのような企業とのパートナーシップを検討する動きも出ています(出典:Carbon Pulse)。
こうした制度と企業の“間”にあるのが、3Beeのようなネイチャーテック企業です。制度の未整備な段階から、実際に自然と向き合いながら、測定・可視化・価値化のインフラをつくっている彼らの存在は、今後のルールづくりや実装において欠かせないプレイヤーとなりつつあります。
iNaturalist:誰でもできる生物多様性モニタリング
出典:iNaturalist
自然を“測る”という行為は、企業や政府だけのものではありません。スマートフォン1台あれば、誰もが自然観察に参加し、そのデータを生態系保全に役立てることができる時代が訪れています。そんな市民科学の代表格が、「iNaturalist(アイナチュラリスト)」です。
iNaturalistは、アメリカのカリフォルニア科学アカデミーとナショナルジオグラフィック協会によって運営されている非営利のプラットフォームです。使い方はシンプルで、植物や動物の写真をスマホで撮影するだけ。AIがその種を自動推定し、位置情報や日付とともに投稿することで、世界中の研究者やユーザーと情報を共有できます。
この仕組みの面白さは、観察データがそのまま科学研究や政策判断の基礎情報として活用される点にあります。たとえば、ある地域で特定の蝶の観察が急増していれば、その地域の植生の変化や気候条件の変動が示唆されるかもしれません。実際、iNaturalistのデータは多くの国の生物多様性戦略や保全施策に活用されはじめています。
また、教育分野でもこのツールは注目されています。学校の自然観察授業で活用されるだけでなく、地域のワークショップや里山保全団体が活動記録として使う事例もあります。最近では日本語対応も進んでおり、国内でもじわじわと利用者が増えてきています。
このように、自然を「見る」「記録する」「共有する」という行為が、専門家だけでなく市民レベルで広がることで、自然との関わり方が根本的に変わりつつあるのです。観察すること自体が自然保全につながるという感覚は、企業主導のネイチャークレジットとは異なるアプローチですが、「見えない価値を見える化する」という点で通底しています。
Nucleário:森を“植え直す”ためのテクノロジー
「自然を守る」だけでなく、「自然を再び育てる」こと。そんな視点から登場したのが、ブラジル発のスタートアップ「Nucleário(ヌクレアーリオ)」です。彼らは、森林の再生を支援するために、自然環境と共生するよう設計された独自の“再植林デバイス”を開発しています。
ブラジルでは、熱帯林の急速な減少と、その再生の難しさが長年にわたる課題です。特に、苗木を植えても乾燥や雑草、動物によって成長できないケースが多く、再植林には大きなコストと人手がかかるという現実がありました。Nucleárioは、そうした課題に対して、「自然が自然を育てる」ことを目指したプロダクトを開発しました。
彼らの製品は、種子や苗木の周囲をドーム状に保護し、雨水をため、地中にゆっくりと浸透させる構造をもっています。さらに雑草の侵入を防ぎ、苗の根の生育を助ける機能も備えています。これは単なる“ガジェット”ではなく、土壌の状態や気象データをもとに設計された、いわば「生態系支援装置」と言えるものです。
この技術により、森林の再生が持続可能かつ低コストで実現できる可能性が広がり、植林活動のスケール化にも貢献しています。さらに注目すべきは、Nucleárioが製品の普及だけでなく、現地の雇用や教育にも力を入れている点です。デバイスの設置や苗木の育成を地元の住民と協働で行い、地域に根ざした再生モデルを築こうとしているのです。
収益性と社会性、テクノロジーと生態系のバランスをとるその姿勢は、まさにゼブラ的です。利益至上ではなく、長期的な環境回復と人々の関係性を重視するスタートアップとして、国際的な賞も多数受賞しています。
3Beeが「自然を測る」存在だとすれば、Nucleárioは「自然を支える」存在です。どちらも異なるアプローチで、自然と経済の新しい接点を切り拓いていると言えるでしょう。
日本へのヒント──地域、企業、自然の新しい関係を探る
ここまで紹介してきた3Bee、iNaturalist、Nucleárioはいずれも、自然と向き合いながらも、その価値をテクノロジーによって見える化・再設計しようとする存在です。そして彼らのアプローチには、私たち日本の地域や企業にも応用できる示唆が多くあります。
たとえば、3Beeのように「生態系スコア」を通じて環境への貢献を可視化する仕組みは、地方自治体や企業のCSR活動と非常に親和性があります。里山の手入れや棚田の保全活動など、日本各地ですでに行われている取り組みに対して、「数値化して伝える」ことができれば、支援や連携の輪が広がるかもしれません。
また、iNaturalistのような市民参加型の自然観察は、地域コミュニティや学校教育の場でも活用が期待できます。生物多様性という言葉が難しくても、「近所にどんな生きものがいるかを記録してみよう」という活動から、自然へのまなざしが育まれていくはずです。地域に暮らす人々が「見つける人」「測る人」になることで、行政や企業の取り組みとも接続しやすくなります。
さらに、Nucleárioのように「自然再生」を目的とする製品・仕組みを通じて、環境課題と雇用や地域経済をつなげるモデルも、日本の中山間地域や過疎地において重要なヒントになるでしょう。再生型農業や自然エネルギーといったテーマと組み合わせれば、独自の“地域循環経済”の可能性も広がります。
重要なのは、「制度を待つ」のではなく、既にある自然や活動、関係性の中に、少しずつ“測る・伝える・支える”要素を取り入れていくことです。ネイチャーテックやゼブラ企業の事例は、技術だけでなく「誰と、どんな価値をつくるか?」という問いかけの集合でもあります。
測ることで、育てる未来へ
自然を「守る」ことが叫ばれて久しい今、あえて「測る」「伝える」「価値化する」という視点が、もう一歩先の実践につながる時代が来ています。
3Beeは、ミツバチを通して自然の健全性をスコア化しました。iNaturalistは、市民一人ひとりの観察を科学につなげました。Nucleárioは、自然再生のプロセスにテクノロジーを持ち込みながら、地域とともに森を“植え直す”モデルを提示しています。
どれも単にデジタル技術の力を活用しているだけではなく、「誰が自然を守るのか」「その貢献にどう報いるのか」といった、社会的な問いに向き合う姿勢を持っていました。こうした企業は、利益と共感、成長と倫理のあいだを往復しながら進む、いわゆる“ゼブラ企業”的な存在として注目されています。
ネイチャーテックという言葉には、自然とテクノロジーを対立させない意志が込められています。自然を“測る”ことは、単に数値を並べることではなく、その価値を社会の中で再確認し、未来へと“育てていく”行為でもあるのです。
日本にも、豊かな自然と、それを守ってきた知恵と関係性があります。それらが見える形になれば、支援する人・共に育てる人がもっと増えていくかもしれません。これからの環境保全は、専門家だけのものではなく、誰もが関われる“経済活動”として、育ち始めています。
自然は、静かに変化を教えてくれています。私たちは、それを測ることで何を学び、どう育てていけるのでしょうか。
文:岡徳之(Livit)

PROFILE
Noriyuki Oka
編集プロダクションLivit代表。サステイナビリティー先進国・オランダを拠点に、ゼブラ企業や地域循環型モデルを調査・執筆。有力メディア(NewsPicks、東洋経済オンラインなど)や企業オウンドメディア向けにコンテンツ制作を手がける。 https://livit.media/