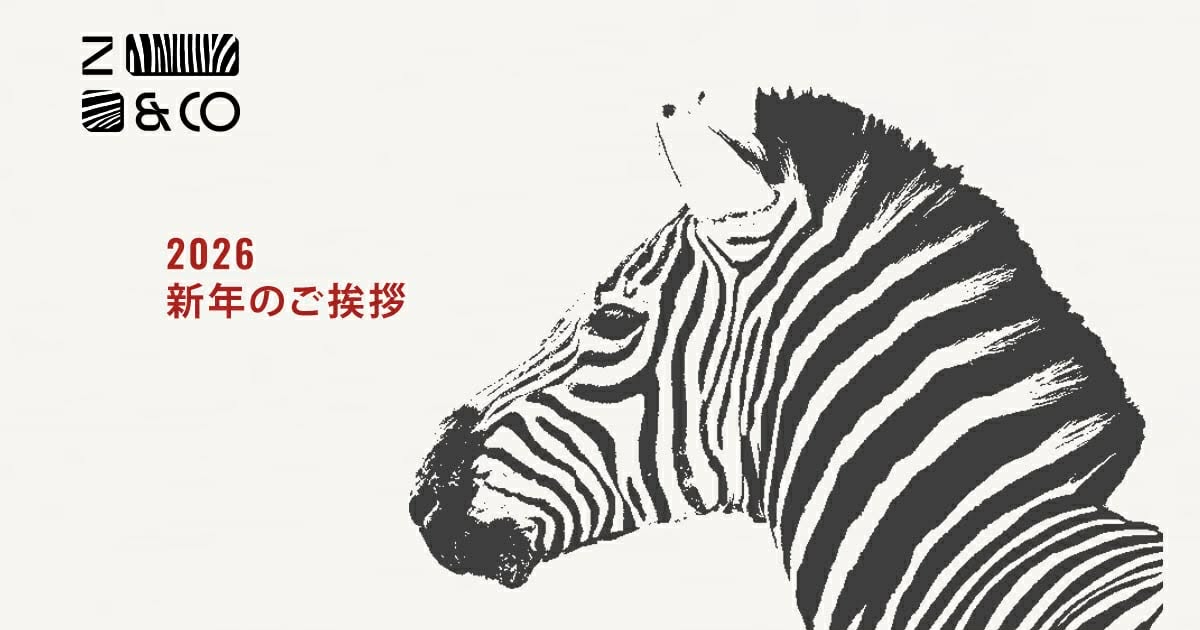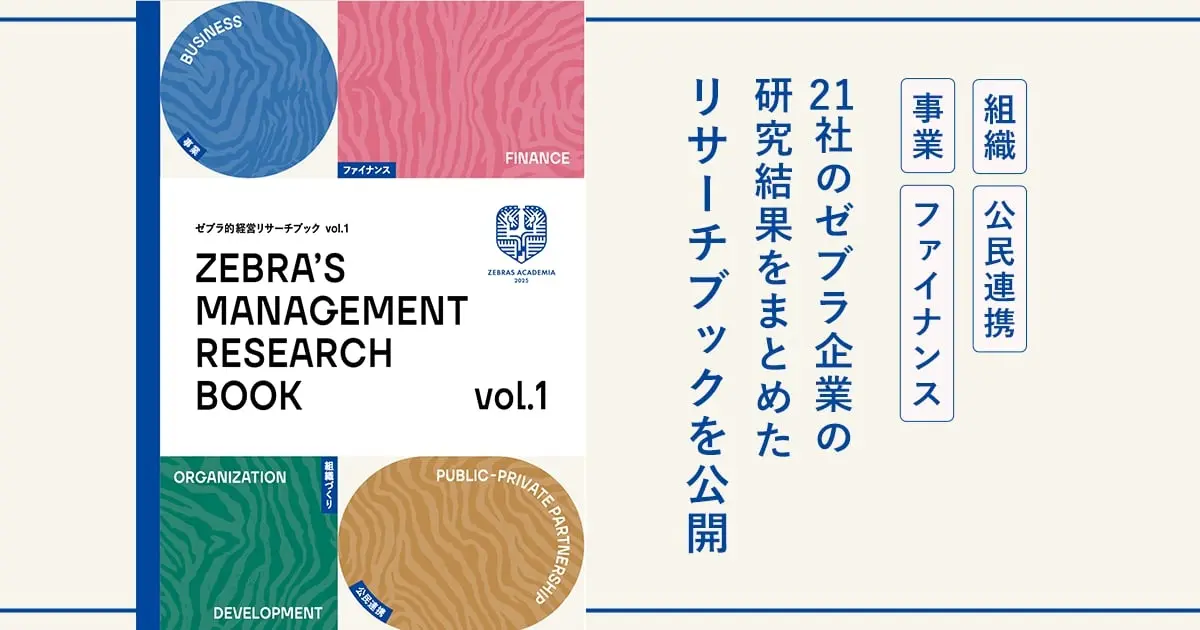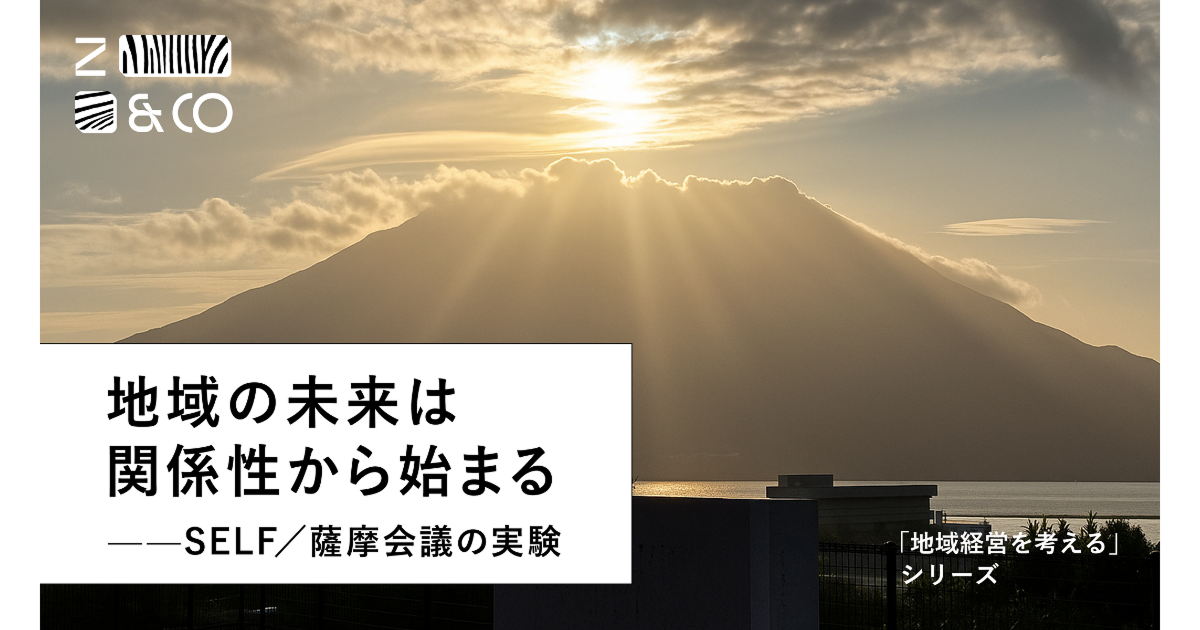2025.09.26 ZEBRAS
批判者ではなくゲームチェンジャーになる。Z&C初の“起業した元インターン生”が、地元青森での「お祭り事業」の立ち上げから学んだこと

「お祭りという文化資源を未来につなぎたい」
そんな思いから、学生が地元・青森の仕事と暮らしに接する機会を作っているのは、青森県八戸市出身の古井茉香(以下、まのさん)さん。2025年4月、Senbay株式会社を立ち上げ、地元での創業に踏み切りました。
その背景には、2022年から約2年間インターンとして関わった株式会社Zebras and Company(以下、Z&C)での経験があります。インターン時代にメンターを担当したZ&Cの共同創業者・陶山祐司さん(2023年9月に退任)は、現在も起業家の先輩として彼女の挑戦を見守り続けています。
Z&C初の“起業した元インターン生”であるまのさんは、なぜ地方での挑戦を選んだのか。彼女の変化を間近で見てきた陶山さんとの対話を通して、創業の原点や、Z&Cインターンと事業作りの経験により得たもの、そして先に見据える未来を聞きました。
「支援」ではなく、地域にすでにある価値に光をあてる
——今日は、事業の話からZ&Cでのインターン経験にまつわることまで聞いていきたいと思います。まずは、Senbay株式会社の事業や設立の背景を教えてもらえますか?
まのさん:
Senbay株式会社は、2025年4月に創業しました。現在は、地元・青森で「誇りを持てる故郷をつくる」ことを目指し、いくつかの事業を展開しています。なかでも力を入れているのが「おまつりインターン」です。これは就活生に向けた採用を見据えたインターンプログラムで、日中は地域の企業で働き、夜はその企業の人と一緒にお祭りに関わる体験社員とお祭りに参加する体験を提供しています。仕事と文化の両面に触れることで、地域の暮らしに自然と溶け込めるようなきっかけになることを目指しているんです。

——地域と学生をつなぐ取り組みは様々あるなか、「お祭り」を切り口にしたのはなぜですか?
まのさん:
きっかけは、2年ほど前に留学時代に知り合ったカナダの友人を地元のお祭りに招いたときのことです。私自身も初参加でしたが、その場所で広がる光景に心が動かされました。そのお祭りでは、赤ちゃんから高齢の方まで、障がいのある方や外国人も含め、年齢や背景を問わず人々がつながり、思い思いに楽しんでいた。東京のような都市にも、過去に留学をしていたアメリカにもなかった、貴重な文化資源がここにあると確信しました。
そして、「地域と共に誇りを育み、自分が成長していける価値」を、必要としている人たちに届けたいという思いが芽生えたんです。ですから私にとってこの事業は、地域を「支援する」といった上から目線のものではありません。地域にすでにある価値に光をあて、形を整えて、未来へつなぐ営みだと考えています。
学生、企業、地域の暮らしをつないだ“おまつりインターン”
——自身の体験からお祭りに価値を感じたと。現在の事業の進捗について教えてもらえますか?
まのさん:
2025年8月に初めての「おまつりインターン」を実施しました。学生を受け入れてくださったのは、青森県内でシェアNo.1の地方銀行「青森みちのく銀行」と、青森県で唯一のラジオ放送とテレビ放送の両方を担う民間放送局である「青森放送」の2社です。
この取り組みは、次年度の新卒採用エントリー数を増やすことを目的に、学生の帰省時期に5日間で行いました。参加した学生は、日中に各企業で働き、夜は「青森ねぶた祭」に参加。弊社側では、学生が地域企業で働く様子、企業の社員さんが企業で働き、お祭りにも励んでいる様子を動画にまとめました。
10月以降は、次年度の「青森で働き暮らしたい新卒人材」を増やしていくための、SNSを活用した採用ブランディング支援を実施予定です。それを通じて、おまつりインターンに来た学生に広告塔となってもらい、地域で働き暮らすネガティブなイメージを変えていきたいと考えています。
※おまつりの写真

——「おまつりインターン」に対する企業側の反応はいかがでしたか?
まのさん:
受け入れ企業の人事の方からは、「学生が何を考えているのかが見えるようになった」と言っていただきました。これまでは企業説明会くらいしか接点がなく、年々エントリー数が減っていく中で、「なぜ学生たちは青森の企業ではなく、都市部のベンチャーを選ぶのか分からない」と言っていたんです。
しかし、実際に学生と関わったことで、現代の若者の就職観そのものが変わっていること、そして「青森の暮らし」にポジティブなイメージを持ってもらう必要があることを実感されたそうです。
これまでも私からお伝えしてきたことではありましたが、今回の取り組みを通じて、それが関係者全体の共通認識へと広がっていきました。そして企業側においては、「青森で働く若者を増やしたい」という思いが、これまで以上に一層強くなったと感じています。
——学生のみなさんの感想も気になります。
まのさん:
参加した学生からは、「青森で暮らすことへの印象が変わった」という声がありました。お祭りという文化を通じて、暮らしや人との関わりといった“ソフトな側面”にも触れた。そして、青森で楽しく働く大人たちとも出会ったことで「自分もこんなふうに成長できるかもしれない」と、前向きなイメージを持てた学生もいました。

「意図を持てば、国も地域も動かせる」Z&Cインターンでの学び
——ここからはZ&Cのインターン時代のお話を聞きたいと思います。まずは、Z&Cでインターンをしようと思ったきっかけを教えてください。
まのさん:
実は最初、Z&Cの“しまうま”のロゴを見て「NewsPicks」だと勘違いしていたんです。高校3年生のときに、NewsPicksのイベントボランティアの募集かと思って行ったのがZ&C主催の「ZEBRAHOOD」でした(笑)。
でもその場で、陶山さんをはじめ共同創業者の皆さんと出会い、働き方や考え方に憧れて、起業へのステップとして「ここで成長したい」と思ったんです。高校卒業後に上京してすぐインターンを始め、陶山さんにメンターとして関わっていただくようになりました。
陶山さん:
当時は、インターン生に共同創業者が伴走する体制でした。週1回ほど話をする機会を設けて、最近の様子や仕事の進捗を話していました。私が代表を退任した2023年9月以降は少し体制が変わりましたが、今も月1程度で相談に乗っています。

——卒業後もそうした関係が続いているのは素敵ですね。インターン時代に学んだことで、特に印象に残っていることはありますか?
まのさん:
社会人としての基本的な仕事の進め方を幅広く学びました。なかでも印象に残っているのは、「期待値調整」「根回し力」「ステークホルダーマネジメント」の3つです。
期待値調整は、信頼を積み重ねるための技術。最初は何でも「すぐやります!」と答えていたのですが、実際には時間が足りず、信頼を損ねる場面もありました。そこで陶山さんから、「想定する作業時間よりも、少し長めに期限を設定して伝える」ことを教わりました。そうすれば、期限より早く終えたときに相手の期待を超えられ、信頼につながる。当たり前のことかもしれませんが、大きな気付きでした。
2つ目の根回し力は、意思決定をスムーズに進めるための工夫。誰かから承認を得たいときに、誰からどのタイミングで相談をするとスムーズにいくのかを考えるということです。「いきなり承認を得ようとするのではなく、相談という形で話を通しておく」といった工夫も、ローカルで働く今にすごく活きています。
——ある種の泥臭さですが、仕事においてはすごく効果を発揮しますよね。
まのさん:
3つ目のステークホルダーマネジメントは、プロジェクトに関わる全員を“勝たせる”ための考え方です。誰がどんな期待をこのプロジェクトに持っているのかを整理し、それに応えるプロセスや成果を設計するというもの。ステークホルダーが複雑になればなるほど、全体感を捉えながら動くことが大事だと学びました。
陶山さん:
よく覚えていますね。今出た3つのことはかなり具体的ですが、より大きな枠組みでいうと「システムズエンジニアリング」の考え方なんです。どうすれば、求める成果を生み出す仕組み(システム)がつくれるかということです。
たとえば、会議の背景・目的・ゴールを事前に言語化して設計するだけでも、会議やプロジェクトは格段に進みやすくなります。まのさんはその力をどんどん磨いていった。インターンを通じて、話す内容の精度や目的意識が高まっていくのを明確に感じました。
まのさん:
ありがとうございます。あとは、Z&Cにいたことで得たご縁も大きかったです。学生起業の身では信用も実績もありません。しかし、Z&Cの一員として、青森でのイベントを企画から実施まで任せていただいたり、「陶山さんたちと働いていました」と一言添えるだけで、相手の反応が大きく変わるんです。所属していたこと自体が、信頼の土台になっています。

——スキルやご縁以外で、価値観や考え方の面で変化はありましたか?
まのさん:
一番大きな変化は、「批判する」視点から、「どう動かすか」を考える視点に変わったことです。以前は、「なんで国や地域はこうなんだろう」「どうして変わらないんだろう」と疑問や不満を持つこともありました。でも今は、「どうすれば国や地域を動かせるか」「あの人にどう話せば伝わるか」と、現実を前に動かす思考ができています。
Z&Cで印象的だったのは、ゼブラ企業のことを紹介し、その普及を促すための自民党本部でのプレゼンに同行させてもらったときのことです。ゼブラの考え方を、国の政策に反映させていくためのやりとりを見させてもらいました。政策が議論される場に関わり、実際に国の予算が付き、ゼロから事業が立ち上がっていく流れを目の当たりにしたことで、「意図を持って働きかければ、国すらも動かせる」と実感したんです。
陶山さん:
僕自身も経産省で働いていた頃、「世の中は意図を持った人が動かしている」と気づいた経験がありました。新聞の一面記事の選び方にさえ、当然のことながら誰かの意思が介在している。自民党でのプレゼンにまのさんを連れて行ったのも、“見といた方がいいよ”という軽い気持ちでしたが、あの体験がそこまで響いていたとは……。今回聞けてよかったです。
お祭りで子育てをしたい。ローカルゼブラらしい広がりを目指して
——インターン卒業後は、本格的に創業準備や事業作りに邁進してきたと思います。東京と青森を行き来しながら現地で活動するなかで、新たな学びや気づきはありましたか?
まのさん:
先ほどの話とつながりますが、現場を経験して「批判者ではなく、ゲームチェンジャーになる」ことをより意識するようになりました。創業前は、地方銀行や放送局をはじめとする地域企業の皆さんとお話をするなかで、「どうしてこんな取り組みをしていないんだろう」「なぜこんなにも動きが遅いんだろう」と思うことも正直あったんです。でも今は事業者として、地銀や地域企業は大切なお客様になります。お客様の課題にどう向き合うか、どうすれば彼らが動きやすくなるのかを考えられるようになったことが、一番大きな変化です。
陶山さん:
僕から見ると、まのさんの「事業へのコミットメント」はインターン時代と比べて格段に強くなったと感じています。地域でトップクラスの企業と、学生の立場でありながらも小さくない額の契約を交わし、責任を背負っている。その状況では、合意形成の仕方や、誰とどの順番で話すべきかまでを真剣に考えざるを得ません。定期的に相談を受けていますが、やりとりを通じて「やらなければならないことへの解像度」や「相談の精度」が一段と高まったのを感じています。

——起業経験を通じて一段とレベルアップしたまのさん。今後、どんな未来を目指していきますか?
まのさん:
地方で挑戦する人たちを増やすことで、「地方で働くことや、地域を担うようなライフスタイルもかっこいい」と思ってもらえるムーブメントをつくりたいです。都市とローカルを二項対立にしたいわけではないけれど、どうしても首都圏の方が予算も人材も集まりやすい。そのなかで「お祭り」を軸にしながら、地方で働く・暮らすという新たな選択肢を提示し、「誇りを持てる地域づくり」につなげていけたらと考えています。
陶山さん:
事業を成長させることも素晴らしいことですが、「自分のやりたいことに挑戦することで、視野が広がり、新しい未来が見えてきている」ということそのものが、すごく価値があると思いますよ。
だから極論をいえば、まのさんが今後事業をピボットしてもいいし、経営者ではなく政治家になる未来があってもいいと、僕は思っています。大企業と取引していた起業家が政治の世界に進むということも、地域や社会にとって価値がありますから。
Senbayのようなローカルゼブラ企業は、必ずしも「起業で社会課題を解決する」ことだけがゴールではありません。出会いやご縁を起点に想像もできない未来が生まれていく——そんな“エフェクチュエーション”的な成長のあり方も、ローカルゼブラらしい姿なのかもしれない。まのさんが、これからどんな未来を描いていくのかが楽しみです。

——最後に、まのさんから今後の意気込みを聞かせてください。
まのさん:
最近、私自身が描いている夢は、地域のお祭りで子育てをすることです。お祭りには人の成長に必要なものが詰まっています。マナーや責任感、創造性や多様な人との関わり方。そして何より、数百年の歴史の一部としてこの場所に属しているという安心感。日本のローカルには、そうした人としての大切な営みや、世界に誇れる文化が文化資源として残っています。私の活動や発信を通じて、そこに目を向けてくれる方を少しずつでも増やせていけたらと思っています。

PROFILE
Fumiaki Sato
編集者・ライター・ファシリテーター。「人と組織の変容」を専門領域として、インタビューの企画・執筆・編集、オウンドメディアの立ち上げ、社内報の作成、ワークショップの開催を行う。趣味はキャンプとサウナとお笑い。