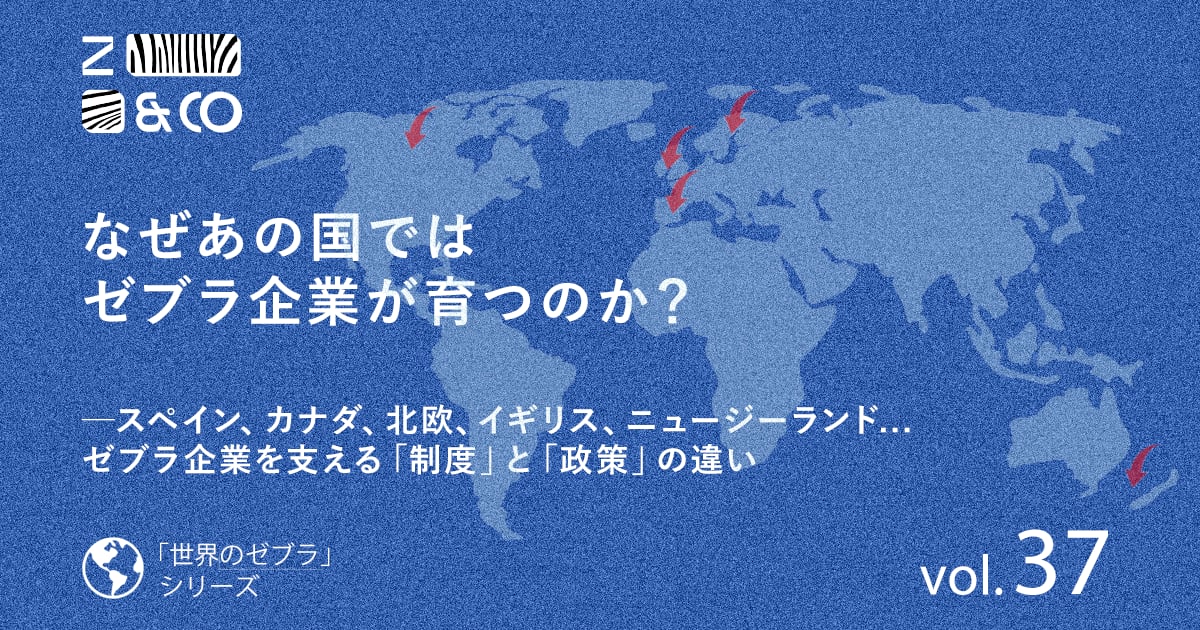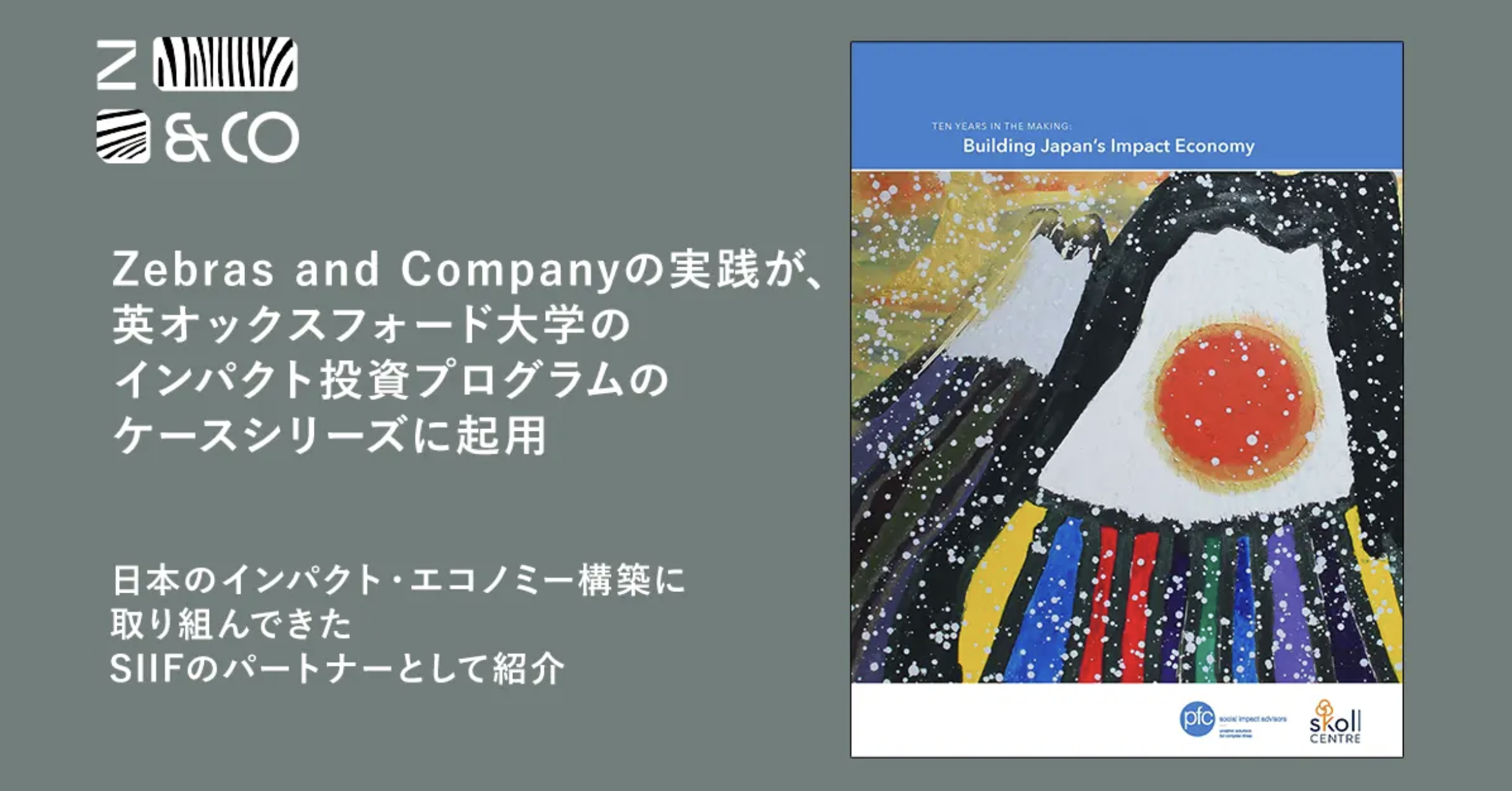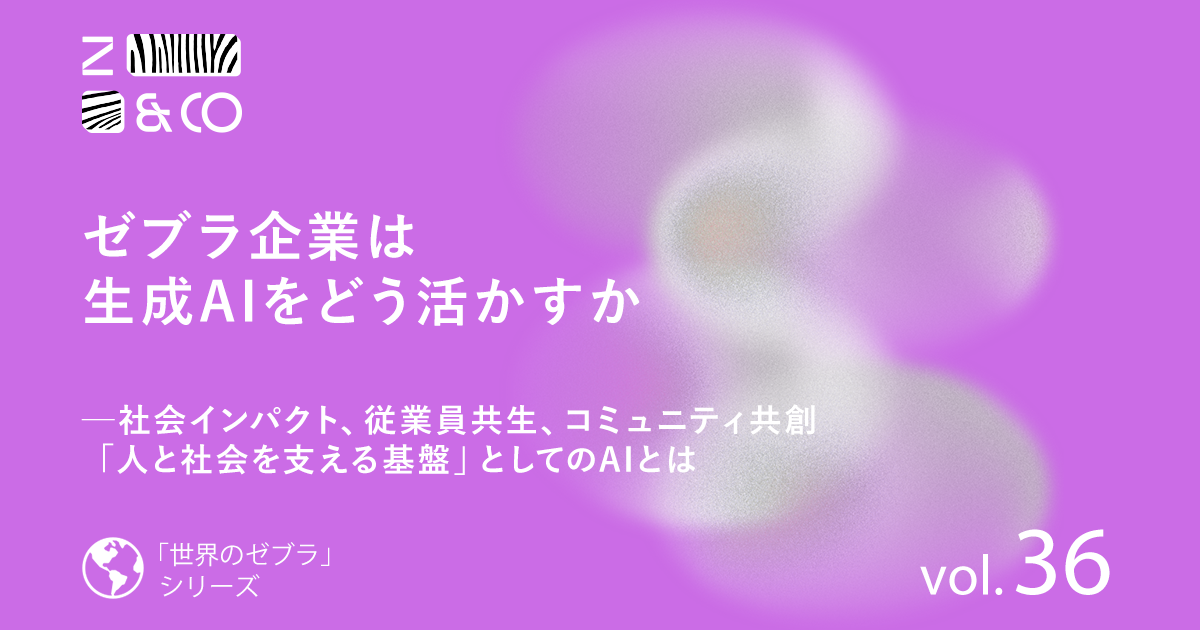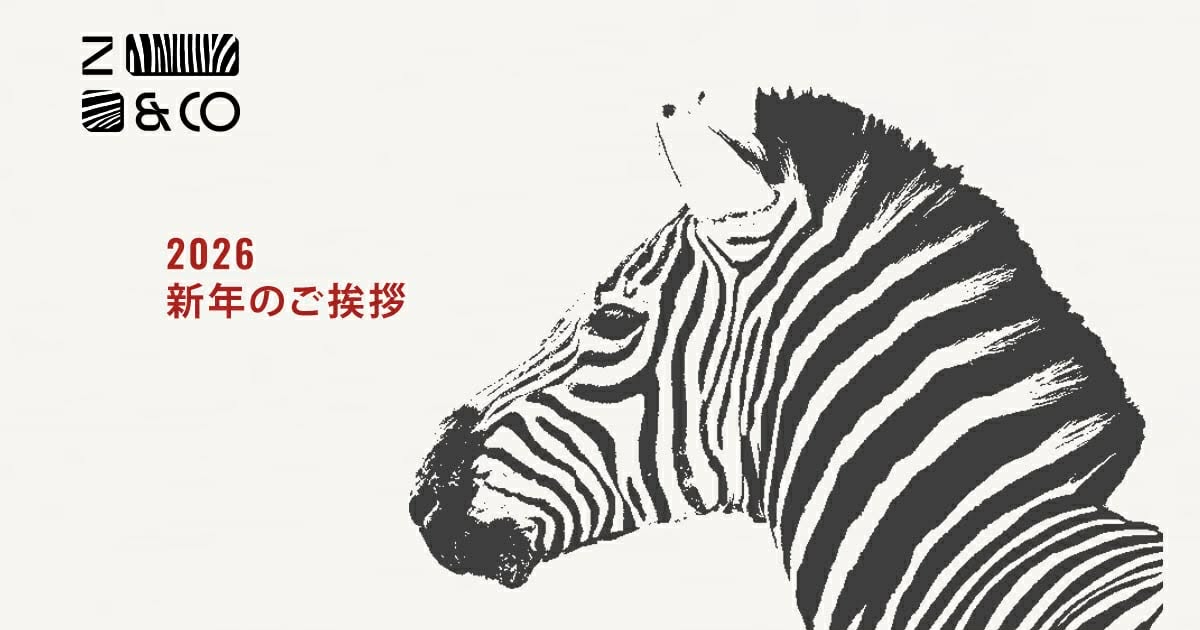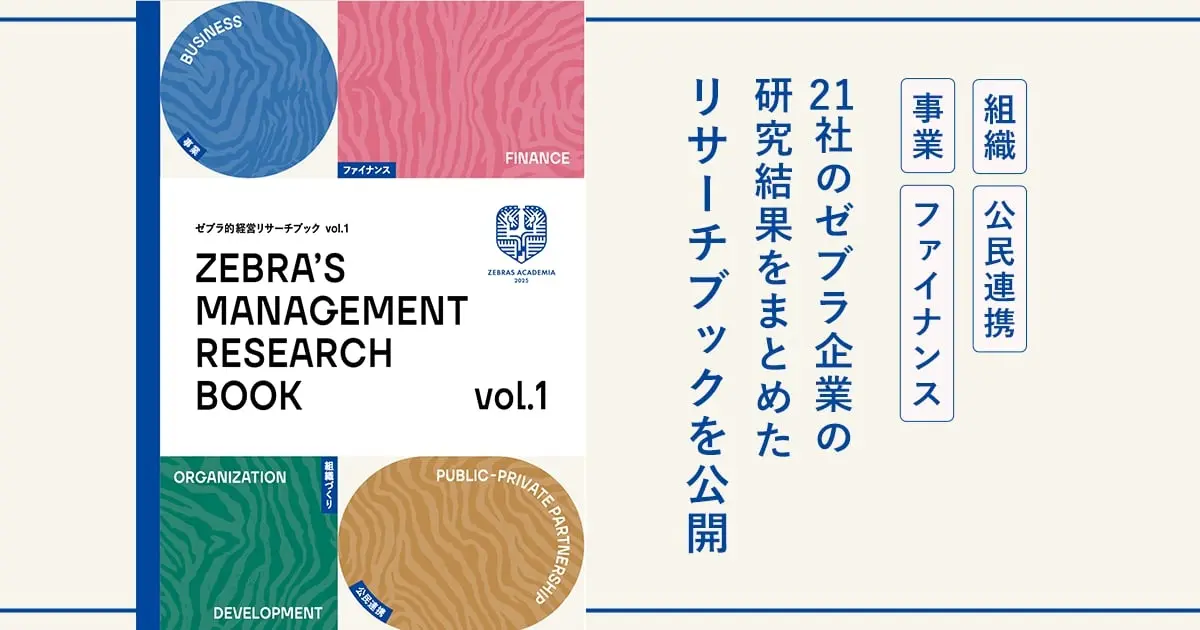2025.10.14 ZEBRAS
社会を紡ぐファイナンス:資本のあり方からジェンダーとのつながりを再設計する

大阪・関西万博の「ウーマンズ パビリオン」「WA」スペースで7月28・29の両日、「ジェンダーの視点から未来の経営と社会システムを考える」と題した一連のセッションが開催されました。この企画は、従来の経済成長に偏らない、公正で持続可能な社会をジェンダーの視点から考えることを目的に、ゼブラアンドカンパニーが一般財団法人社会変革推進財団(SIIF)と共同で手掛けたものです。
本稿では、29日に行われたセッション「社会を紡ぐファイナンス:資本のあり方からジェンダーとのつながりを再設計する」をレポートします。
このセッションでは、「なぜファイナンスは社会を変える力を持ち得るのか?」という問いを深掘りし、ファイナンスが持つ「紡ぐ力」に焦点を当て、資本とジェンダーの関係性を多角的に捉え直すことで、より持続可能で包摂的な社会を実現する資本の可能性を探りました。
昭和女子大学客員教授でジャーナリスト・作家の白河桃子さん、ビー・インフォマティカ株式会社代表取締役社長の稲田史子さん、JPインベストメント株式会社地域・インパクト投資部ディレクターの瀬尾萌さんが登壇。モデレーターはゼブラアンドカンパニーの田淵良敬さんが務めました。

日本は貧乏なおばあさんの国?
モデレーターの田淵さんは、まず日本におけるジェンダー課題の現状を指摘しました。ジェンダー課題は、雇用の問題、教育の問題、女性起業家の数といった特定の課題に限定されず、男女間の経済格差、就労環境の変化、女性の健康課題、家庭の課題、価値観を育む教育、そして国の制度や資源分配など、あらゆる要素が複雑に絡み合って生じている構造的な問題であると提起し、ファイナンスがこれらの社会構造的な問題にどうアプローチできるかという問いを投げかけました。
これに対して、最初の登壇者である白河さんは、自身の専門分野である「女性×働く」を軸に、この問題の構造を詳しく解説しました。
有識者として「地方創生2.0」の議論に深く関わる立場から、地方が若者・女性に選ばれる重要性を強調。女性が地方を去る主な理由として、「仕事がない」ことや「女性役割を押し付けられたくない」こと、そして「結婚・出産への圧力が厳しい」ことを挙げました。これにより、地方では男性の未婚率が高まり、若年層の労働人口が減少するという構造が生まれていると警鐘を鳴らしました。

さらに白河さんは、日本が高等教育を受けた女性のリターン(賃金)が少ない国であると指摘しました。社会学者の上野千鶴子さんの言葉を引用し、「日本は貧乏なおばあさんの国になる」と表現。シングルマザーや高齢の単身女性の貧困率が高い現状や、男女間の賃金格差が大きい(女性の賃金が男性の75%程度)ことをデータで示し、女性にお金が回らない構造が日本に根付いていると強調しました。
政治や経済の意思決定層に女性が少ないことが、女性や子供の政策が後回しになる原因であると指摘し、フィンランドの内閣と比較して、日本の内閣が「高齢の男性」中心である現状にも触れました。また、女性が第一子出産後に10年間で賃金が46%も減少する「出産ペナルティ」の存在も明らかにし、ワンオペ育児が女性の経済的自立を阻害していると述べました。
単なる貸付に留まらない「伴走」

続いて登壇した稲田さんは、自身がマレーシアで展開するマイクロファイナンス事業「ビー・インフォマティカ」と、女性起業家としての経験を語りました。
マレーシアは女性が比較的働きやすく、起業家も増えている一方、日本と比べても立ち上げ期の資金繰りが難しい国だと紹介し、現地でスモールビジネス、特に女性起業家に対して少額融資を行うことの意義を説明しました。こうした事業を行う稲田さん自身も、起業家として資金調達に非常に苦労しており、特に「投資家からのネットワークや情報へのアクセスが難しい」という女性起業家特有の困難に直面したと述べました。
その原因は、男性中心の投資家コミュニティの「輪の中に入れない」ことで、投資家のロジックを理解するためのコミュニケーション機会が不足していたことだったと振り返りました。しかし、多くのエンジェル投資家との対話を通じてピッチの質を高め、最終的にVCからの調達に成功したと語りました。
稲田さんの会社では、小売業や飲食業、アパレルなど、女性が主に手がける事業への融資が多く、男性よりも少ない金額での融資となる傾向があるものの、女性の消費意欲や起業意欲は高いとしました。
同社は、銀行から融資を受けられない中小企業、特に途上国の企業に対して、資金提供だけでなく、経営コンサルテーションや再建計画の策定支援、人的ネットワークの紹介、そしてコミュニティ形成といった非財務的なサポートを重視していることを強調。単なる貸付に留まらない「伴走」を通じて、事業の継続と成長を支援していると述べました。
流行に乗った投資が生み出す不幸
JPインベストメントの瀬尾さんは、日本郵政グループの一員として運用資産300兆円を抱える大企業で働く投資家の視点から語りました。
JPインベストメントの目的は「長期的な投資の力で社会のさまざまな課題を解決し、持続可能で活気ある社会の実現および地域活性化を推進する」ことであり、地域、環境、ウェルビーイングの3つを主要な投資テーマとしていると説明しました。女性に関するテーマは「ウェルビーイング」の中に包括されているが、まだ独立した投資テーマとしては確立されていない現状を認識していると述べました。

投資家の立場から、稲田さんの経験に共感し、特に初期段階の投資では「人と人とのコミュニケーション」と「信頼」が重要になるため、性別の違いが深い対話を阻害する可能性があると指摘しました。VCが直接的なフィードバックを避けがちであるのに対し、エンジェル投資家は個人の資金であるため、率直な助言を与えやすい点に言及し、稲田さんの経験は「構造の外」にあるエンジェル投資家の価値を示していると話しました。
また、瀬尾さんは、投資家が「流行っているものに投資しよう」という傾向が強いことを認めました。これが「フェムテック」や「女性起業家への投資」といったブームを一時的に生み出したものの、流行に乗って過剰な評価(バリュエーション)がなされると、本質的な力が磨かれず、結果的に事業の成長を阻害する可能性があると警鐘を鳴らしました。根本的な社会構造の理解なしに投資を行うことは、かえって流れを殺すことにもなりかねないと述べました。
女性の視点を取り入れたルールづくりを
ディスカッションでは、女性起業家が資金調達において直面する「距離感のジレンマ」(近づきすぎるとセクハラの危険、離れすぎると情報不足)が稲田さんの口から語られました。白河さんはこの点に対し、金融機関の意思決定層が男性中心であること、情報アクセスが男性に比べて少ない「ボーイズクラブ」文化が背景にあると指摘しました。
さらに、スタートアップ業界における女性起業家の52%が過去1年間にセクハラを経験しているという衝撃的なデータを示し、これによりキャリアを諦める女性もいるため、女性起業家の保護と育成が喫緊の課題であると訴えました。ハラスメントは個人の問題に留まらず、「それを許す組織」そして「それを許す社会」という構造的な問題であり、周囲が介入し、許容しない環境を築くことの重要性を強調しました。
また、社会における「成功のプロトコル」に関する議論も行われました。
田淵さんから、社会の成功が個人の能力だけでなく、社会が作り上げた「成功のプロトコル」に乗れるかどうかで評価される傾向があり、これが特に女性にとって窮屈さや困難を生む要因となっているのではないかと問題が投げかけられました。これに対して瀬尾さんも、このプロトコルは現状を知らない既存の管理職男性によって作られがちであり、格差を広げる結果につながっているという認識を示しました。
白河さんは、特許取得における男女混合チームのパフォーマンスの高さを例に挙げ、多様性がイノベーションに貢献することをデータで裏付けました。女性の管理職の数を増やすことの意義は、単なる数合わせではなく、意思決定層に女性が参画することで、女性の視点を取り入れたルールや仕組みが作られていくことにあると述べました。

ジェンダー課題は「人権の課題」である
質疑応答の時間には、大学教育機関で働くという参加者から、日本のジェンダーギャップ指数が低い現状に対し、意識変革にどのように貢献できるかという問いが上がりました。稲田さんは自身の経験から、若いうちに短期間でも海外に出て、自身の「常識」を打ち破る経験をすることの重要性を強調しました。マレーシアの若い女性支店長の例を挙げ、海外には日本とは異なる「当たり前」が存在し、そうしたものに触れることが、自身の意思決定のあり方やキャリア観に大きな影響を与えると述べました。
セクハラの話題では、自身の年齢でやっとハラスメントを気にせず対等に話せるようになったという参加者のコメントに対し、白河さんは「男性特権」の無自覚性に触れました。男性は職場や公共交通機関でセクハラを心配する経験が少ない一方、女性は常にそうした懸念を抱いているという差があり、自身の特権に気づくことがお互いへの優しさに繋がると述べました。
最後に、登壇者それぞれがファイナンスの未来と社会変革に向けたメッセージを述べました。
瀬尾さんは、ファイナンスは他者が気づかない価値に気づくことで利益を生むとし、自身の特権や他者の特権といった「差分」をネガティブなものではなく、「機会」として捉えることで、ギャップを埋める力となると締めくくりました。 稲田さんは、自身の企業が女性への投資に強みを持つことをこうした「差別化」の機会と捉え、非財務的な支援を実践することで、マレーシアの女性起業家が金融にアクセスしやすい仕組みを構築していくと決意を述べました。
白河さんは、日本がジェンダー課題において依然「発展途上国」であるという認識を示し、解決に向けては、ジェンダー課題を「人権の課題」と捉え直すことが重要であると述べました。男性もまた「人権のない働き方」を強いられてきた過去があることから、女性の苦しみを受け入れるべきものと認識している可能性を指摘。男性も女性も共に人権を享受できる社会になることへの希望を語り、セッションを締めくくりました。


PROFILE
ゼブラ編集部
「ゼブラ経営の体系化」を目指し、国内外、様々なセクターに関する情報を、一緒に考えやすい形に編集し、発信します。