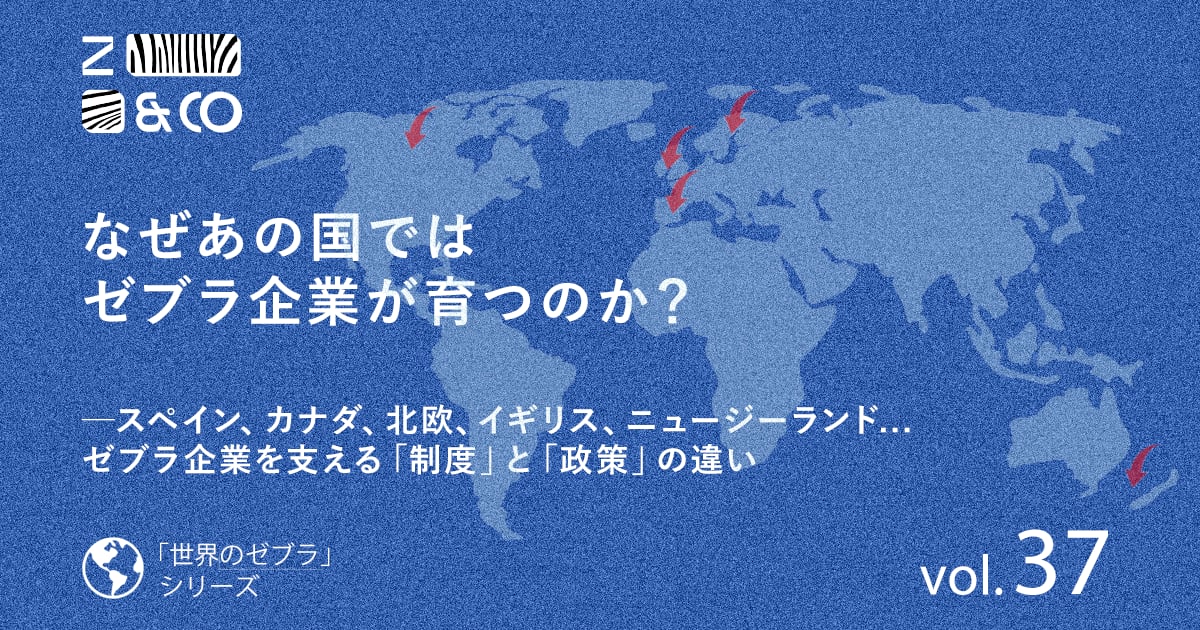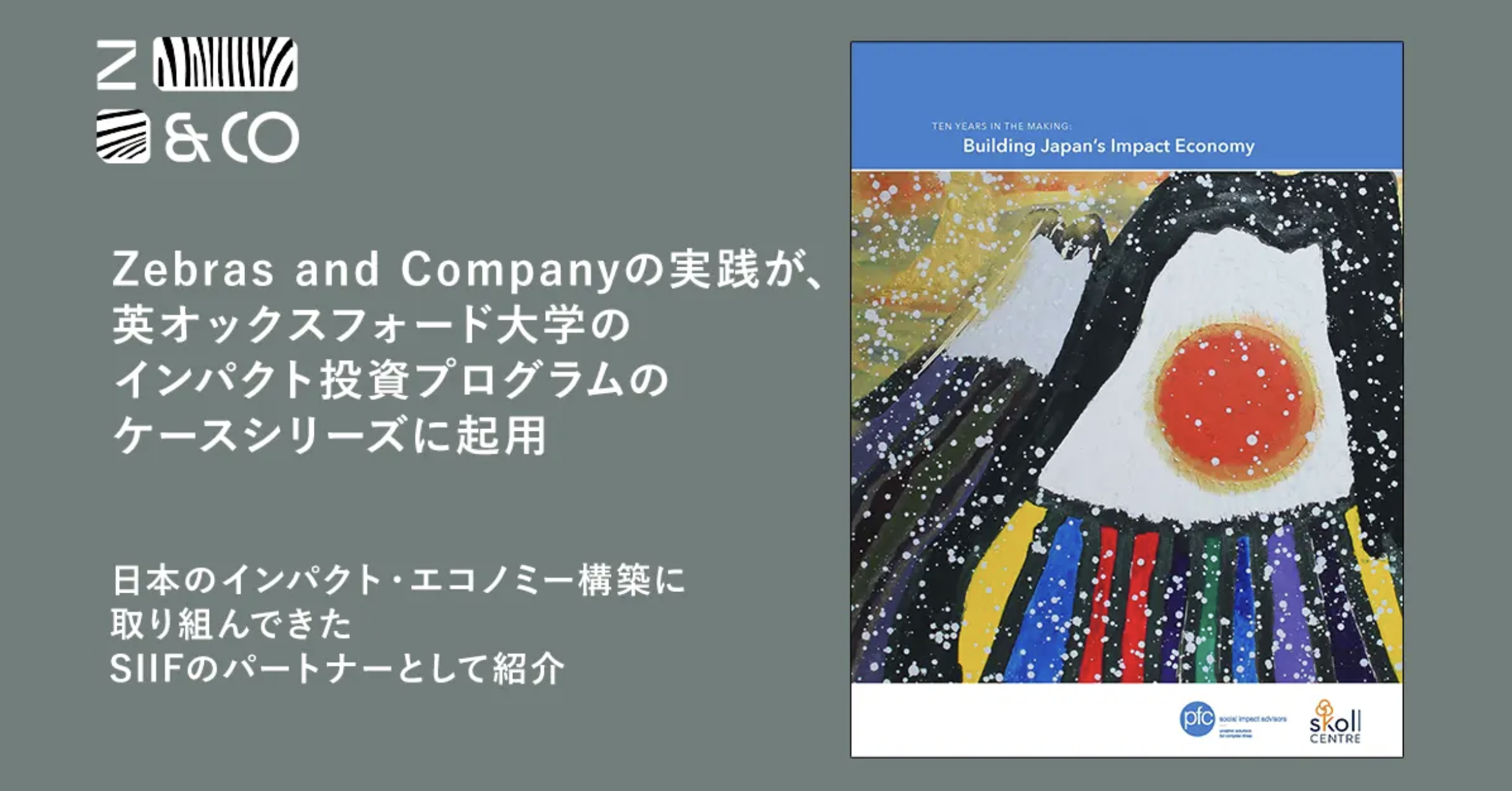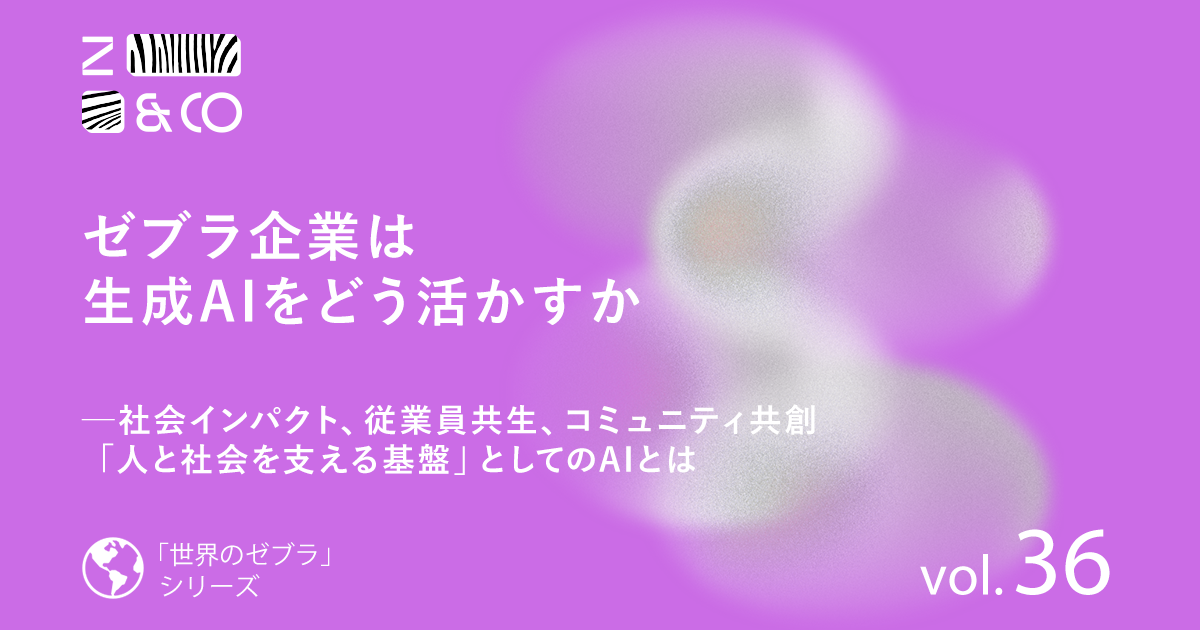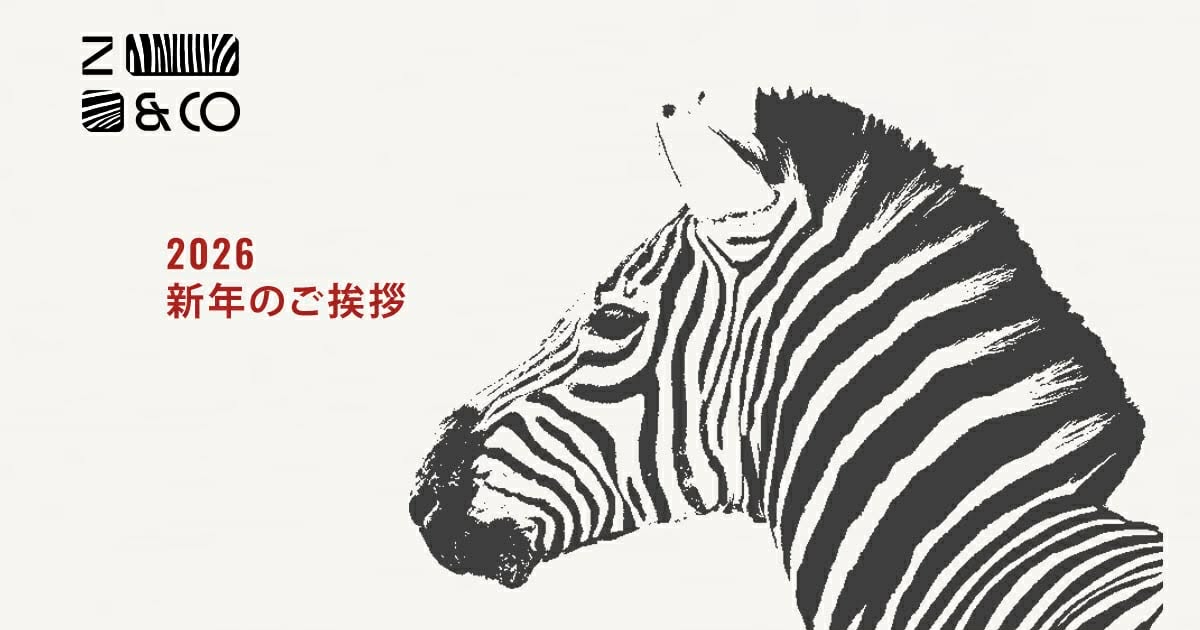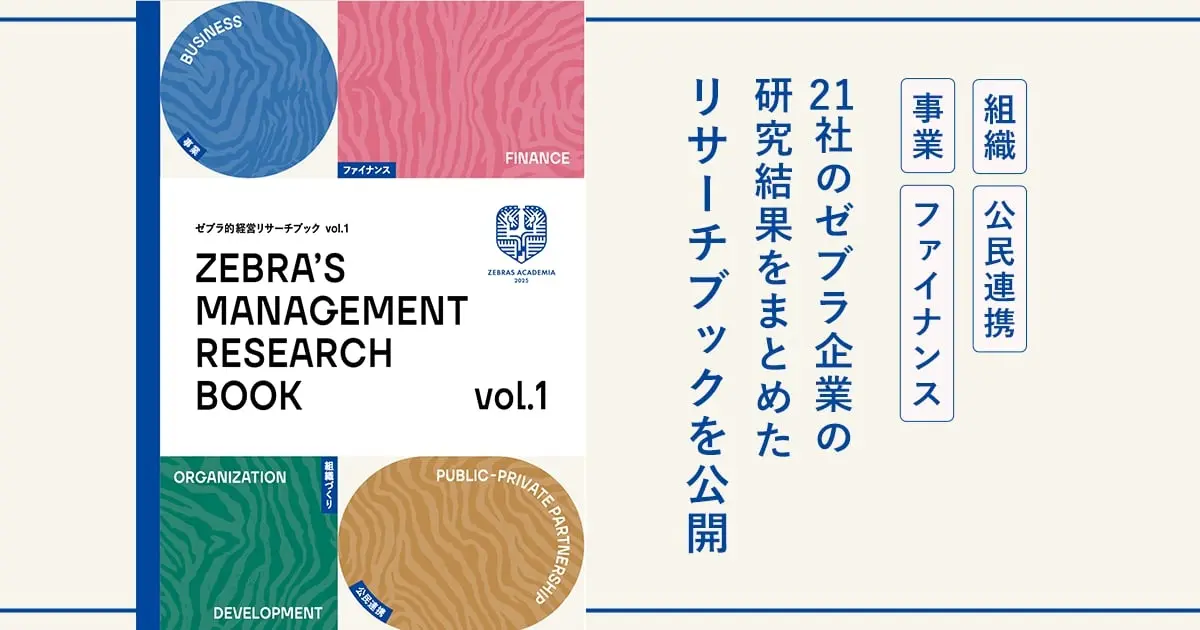2025.10.15 ZEBRAS
ジェンダード イノベーションズが未来を拓く:科学・ビジネス・社会を変える視点

大阪・関西万博の「ウーマンズ パビリオン」「WA」スペースで7月28・29の両日、「ジェンダーの視点から未来の経営と社会システムを考える」と題した一連のセッションが開催されました。この企画は、従来の経済成長に偏らない、公正で持続可能な社会をジェンダーの視点から考えることを目的に、ゼブラアンドカンパニーが一般財団法人社会変革推進財団(SIIF)と共同で手掛けたものです。
本稿では、29日に行われたセッション「ジェンダード イノベーションズが未来を拓く:科学・ビジネス・社会を変える視点」をレポートします。
このセッションでは、ビジネス、メディアの両分野で活躍する女性リーダーを招き、ジェンダー視点を取り入れることで生まれる革新を具体例と共に探りました。株式会社「陽と人」代表取締役の小林味愛さんとCEメディアハウス フィガロジャポンBusiness with Attitude事務局長の藤本淑子さんが登壇し、モデレーターはゼブラアンドカンパニーの阿座上陽平さんが務めました。

ジェンダードイノベーションズとは?
セッションの冒頭、モデレーターの阿座上さんがジェンダードイノベーションズについて解説しました。これは2009年にスタンフォード大学で提唱された概念で、「性差と交差性(人種など)の分析による創造性と発見」を指します。既存の商品開発や技術研究が、多くの場合男性の目線や身体をベースに設計されているという問題意識がその根底にあります。
ジェンダードイノベーションズの目的は、単に企業の利益追求に留まらず、以下の3点に集約されるといいます。
- 研究成果の確実性と質の確保、持続可能性の向上
- 社会ニーズに応える研究の推進、社会価値の向上
- 新しいアイデア・特許・技術の開発、技術価値の向上
具体例として、1997年から2000年の間に米国市場から撤退した医薬品の8割が女性に大きな健康リスクをもたらす可能性があったこと、車の衝突実験用ダミーが男性の体型をベースにしているため、女性ドライバーには適していない可能性、顔認証システムが男性や特定の肌の色の人種、トランスジェンダーに対して認識精度が低い問題、薬の動物実験においてオス・メス両方のデータを考慮する必要性、そして都市設計が男性のライフスタイルを前提とし、女性の視点が欠けている現状などが挙げられました。
これらは、性別や人種といった多様な視点を取り入れることで、より公平で安全な社会システムや製品開発が可能になることを示しています。

イノベーションを阻む無意識の思い込み
登壇者の小林味愛さんは、元国家公務員として過酷な労働環境を経験し、自身や同僚の女性たちの体調不良を通じて「体は男女で違う」という素朴な事実に気づいたことから、東日本大震災を機に福島で「株式会社陽と人」を設立したと紹介しました。同社は、福島の農業課題と女性の課題解決を両輪で進めています。
小林さんは、女性の健康課題が「言っちゃいけないもの」「抱え込むもの」とされてきた現状を指摘し、この課題が日本経済に年間3.4兆円以上の経済損失をもたらしていると述べました。特に、現代女性が生涯に経験する生理の回数が約450回と、約100年前の9倍に増加していることに着目。これは妊娠出産の回数減少が大きな要因であり、この増加が月経困難症や子宮内膜症、がんなどの健康リスクを高めているにもかかわらず、学校教育などで十分に教えられていない現状を問題提起しました。
また、経済産業省のアンケート結果から、女性の約43%がジェンダー課題によって正社員での働き方や昇進、留学などを諦めた経験があること、さらにマイノリティが存在しないものとして扱われることで生じる不利益の具体例として、男性の骨格に合わせて作られたオフィスの椅子や、女性がVRで気分を悪くしやすいといった例を示し、工学や医療分野における性差の見過ごしに警鐘を鳴らしました。しかし、これは同時に、新たなイノベーションのチャンスが多数眠っていることを意味すると強調しました。

小林さんの会社「陽と人」は、このジェンダードイノベーションズの実践者として、福島の特産品である「あんぽ柿」の製造過程で出る未利用の柿の皮に着目し、その成分から女性向けのフェムケア商品「明日 わたしは柿の木にのぼる」を開発しています。この事業は、地域生産者への還元と同時に、商品販売を通じて女性の健康課題の改善を目指すもので、さらに専門家との連携により、知識普及や企業研修も行っていると言います。
小林さんは、ジェンダードイノベーションズを理解する上で重要な概念として「アンコンシャスバイアス(無意識の偏見)」を紹介しました。これは誰もが持つ、自覚できない物事の捉え方や思い込みであり、自身の言動が決めつけに基づいていないか、日常的に「これって当たり前なんだっけ?」と疑うことが重要だと述べました。
特に地域社会では性別の役割分業が根強く、小林さん自身も事業開始当初は、地元の男性たちから「女のくせに何でしゃばってんだ!」「女にはできねえ!」と厳しい言葉を浴びせられたといいます。しかし、諦めずに実践を続けた結果、数年後には70代の男性たちから「味愛ちゃん、仕事に男も女もねえな」「死ぬ前にこれ知れてよかった」という言葉をもらったというエピソードを紹介。無意識の思い込みが変化する可能性を示しました。

思いを言葉にすることから始まる

藤本淑子さんは、自身が編集者を務めるフィガロジャポンが1990年の創刊以来、女性の豊かな生き方を応援する情報を発信してきたことに触れ、2021年から女性の多様な働き方や生き方を応援するコミュニティ「Business with Attitude(BWA)」を立ち上げた経緯を語りました。BWAは、「こうあるべき」にとらわれず、自分らしく生き、かつ社会に良いインパクトを生み出す女性を応援することを目的とし、オンラインセミナーやアワード、そして「思いを言葉に」をテーマにした女性向けピッチコンテストを主催しています。
BWAピッチコンテストは、投資家向けのビジネスコンテストとは異なり、ビジネスの規模や収益性だけでなく「なぜそれをするのか」という起業家の思いや志の発信を重視していると言います。参加者が「声を上げる」こと自体を評価し、温かい雰囲気の中で参加者の可能性に焦点を当てる点が特徴です。
藤本さんは、ジェンダードイノベーションズの事例として、このピッチコンテストに出場した二人の女性の取り組みを紹介しました。
1. 大桃綾子さん「Dialogue for Everyone」
大手メーカーの人事職だった大桃さんは、長年働いている50代の先輩たちが「自分のキャリアは潰しがきかない」と元気がなくなっていくことに衝撃を受け、これまでとは異なる環境で自分の経験を捉え直す大人のインターンシッププログラムを立ち上げました。これにより、例えば「自分にはこれしかできない」と思い込んでいたメーカーの技術職の男性が、農家にキャリアチェンジした男性の畑でのインターンを経て、シニアの健康を支えたいとトレーナー資格の取得を目指すなど、参加者が自身の可能性を再発見し、行動変容が起こっています。藤本さんは「同質性の高い環境に『それっておかしくない?』と問いかける存在が入ることで、解決のヒントが生まれる」ことが、ダイバーシティやジェンダードイノベーションズの大きな特徴だと強調しました。
2. 田村かすみさん「シェアオフィス来音」
学校教師だった田村さんは、呉服屋だった自身の実家を「女性の起業塾に生まれ変わらせたい」という夢を抱いていました。家族の反対を恐れ、誰にも話せなかったこの思いを、BWAピッチコンテストの場で初めて公に発表。ビジネス経験ゼロだったにもかかわらず、その強い思いが多くの共感を呼び、2年後の2025年8月月に、実際に実家をシェアオフィス来音(クルネ)としてオープンさせました。藤本さんは、この事例を通じて「やりたい思いをまず発信する」ことの重要性を強く訴えました。
藤本さんは、ジェンダードイノベーションズを起こすために特に重要なこととして、以下の3点を挙げました。
- 「おかしくない?」と率直に言える環境を作ること
- 思いつきであっても、まず話してみること
- 合理性だけでなく、個人的な「変えたい」という感性や思いを応援し、その勇気を評価する周囲の環境を整えること
また、藤本さんはメディアの役割にも言及し、現代のメディアは「これが正しい」という一方向の情報発信に留まるべきではなく、多様な視点や選択肢を提示し、読者との対話の場を作ることで、共に未来を切り開いていくべきだと述べました。

右肩上がりのビジネスでないと価値はないのか?
セッション後半のディスカッションでは、小林さんと藤本さん、阿座上さんの間で活発な意見交換が行われました。「女性活躍」という言葉の裏に、地域社会や組織内で未だに存在する「女性に前に出てほしくない」という本音や、「良かれと思って」の決めつけが、かえって当事者の意欲や可能性を阻害するミスコミュニケーションについて深く掘り下げられました。こうした問題の解決には、「対話」と、本音を話せる「信頼関係」「心理的安全性」が不可欠であるという認識が共有されました。
続く質疑応答では、ベンチャー投資家からの「事業を立ち上げ、裾野を広げるフェーズのソフトなコミュニケーションから、商業化フェーズで求められるハードなコミュニケーションへの移行における歪みをどう埋めるか」という質問に対して、二人がそれぞれ回答し、興味深い見解を示しました。
小林さんは、投資家側も「どこまで成長を目指すことが、顧客や地域の人々を最も笑顔にするのか」という問いを立てるなど、必ずしも右肩上がりの出口だけが全てではないという、投資マインドの多様化が必要だと提案しました。そして、日常の違和感から生まれた課題を解決する目的での「無理なき成長」を目指すビジネスを切り捨てる社会のあり方に疑問を呈しました。

一方の藤本さんも、「スケールしない」という言葉で女性起業家のポテンシャルが過小評価されていることを指摘しました。女性が社会に提供する多様な視点が「より多くの課題解決」を生んでいると考えれば、それはすなわちインパクトの大きさと捉え直すことができる。「わきまえて」経済的な成長のみが評価される環境に合わせてしまうと、女性起業家が生み出す多様な視点が生きてこない。だからこそ、経済的な成長だけでなく、より丁寧な支援体制が求められると述べました。
セッションの最後に、登壇者から参加者へ、日常生活で実践できるジェンダードイノベーションズ推進のためのヒントが贈られました。
小林さんは、日常で感じる「ちょっとした違和感」や「不便さ」「おかしくない?」という気持ちに「蓋をしないこと」が最も重要だと述べました。そして、会場となった大阪・関西万博の様々なパビリオンを巡り、多様な国の歴史、背景、課題の捉え方に触れることでも、「こんな見方もあるんだ」という新しい気づきやカルチャーショックを経験できると勧めました。
藤本さんは、フィガロジャポンのテーマでもある「好きなことは好き、嫌なことは嫌だ」と、自分の気持ちに正直になり、それを口に出してみることの重要性を強調しました。そして、異なる感性を持つ人との間でも、「どうしたらこの人と分かり合えるだろう」と考え、対話を試みることの価値を語りました。


PROFILE
ゼブラ編集部
「ゼブラ経営の体系化」を目指し、国内外、様々なセクターに関する情報を、一緒に考えやすい形に編集し、発信します。