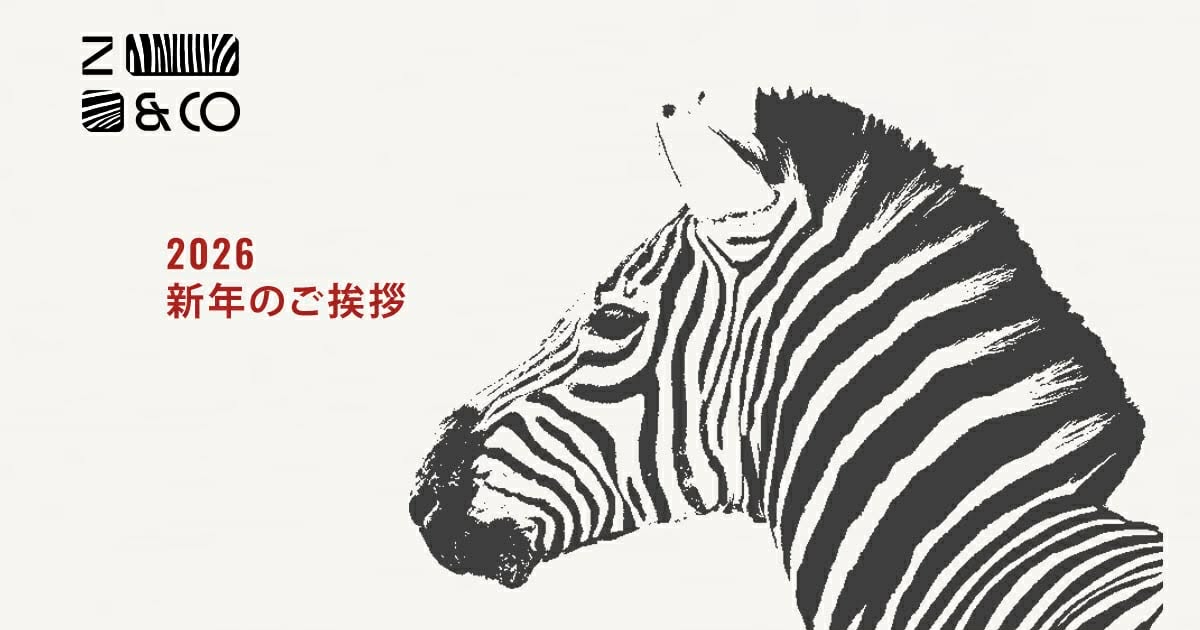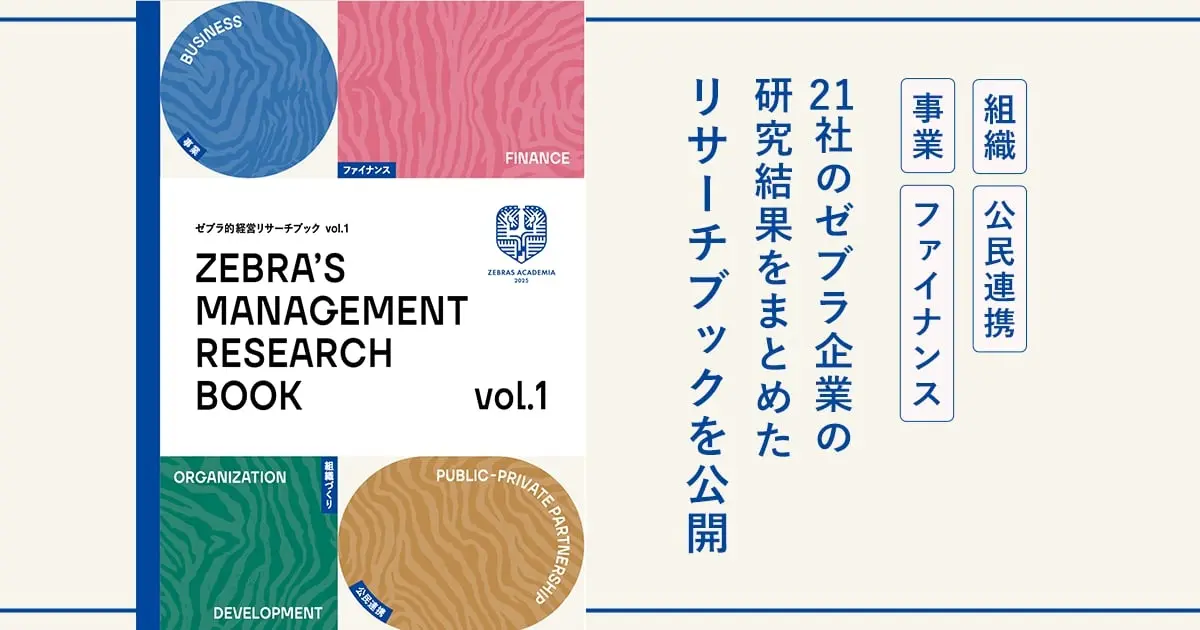2025.09.19 ZEBRAS
地域の未来は関係性から始まる——SELF/薩摩会議の実験
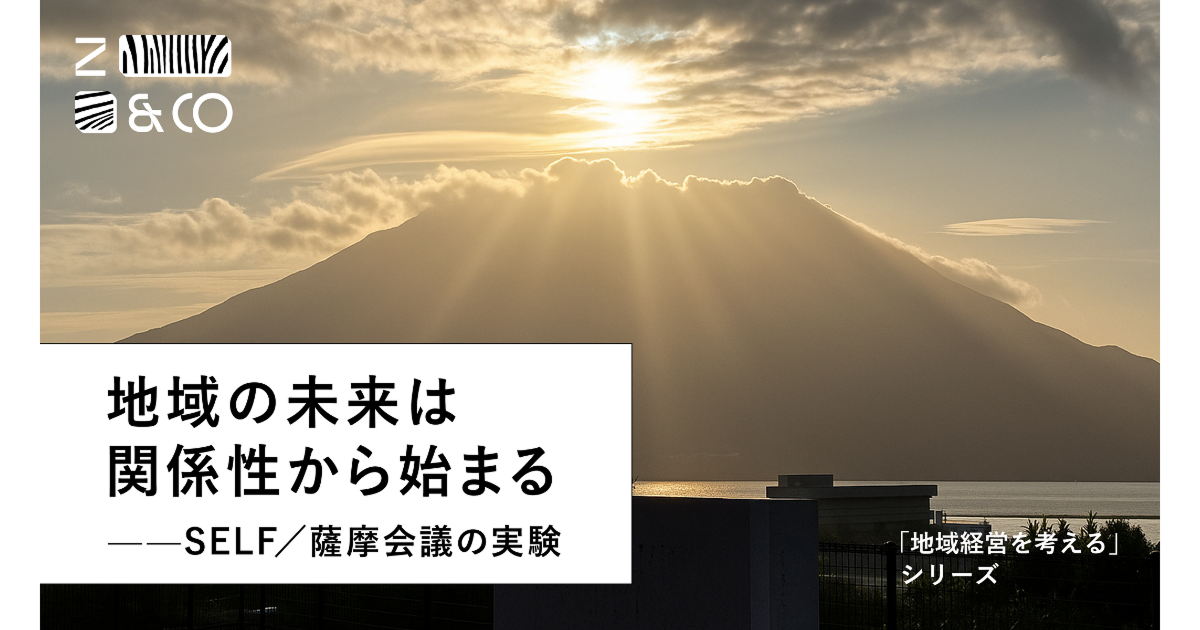
こんにちは。阿座上です。
ゼブラアンドカンパニーでは「ゼブラ企業の成長に必要な経営技術を理論化する」ということを自社事業の主軸においていることもあり、設立当初からオウンドメディアとして新たなファイナンスのモデルや海外事例、国内の新たな経営の姿になるような事例記事を発信してきました。
最近いくつか記事を出している「地域経営」というテーマの一環として、今回紹介するのはローカルゼブラ企業を目指す仲間たちの中でも最も熱量があり注目を集めているとも言える「薩摩会議」とそれを運営するNPO法人 薩摩リーダーシップフォーラムSELF(以後、SELF)の理事や運営者たちです。
今回の記事では今までのようにインタビューのみで構成するのではなく、阿座上が分析した構造をもとに、なぜ・どのようにそのエコシステムが出来上がり、これからどうしていくのかを当事者にインタビューするというアプローチを行いました。いま鹿児島で起きている運動を理解する一つのきっかけになれると嬉しいです。
(と思って、薩摩会議の開催日より前に出したいと思って書き始めたのですが、結局間に合わず。途中段階ですが皆さんの参考にと思って公開します!)
ディスカッションの出発点としたシート
https://docs.google.com/presentation/d/1JHvUMT6_7u1EqFIgwuIxQ-KbAZZ1VBO74fBbN0dYO6A/edit?usp=drivesdk
<今回お話を聞いたひと>
野崎恭平 薩摩リーダーシップフォーラムSELF 代表理事
1986年生まれ。同志社大学を卒業後、大阪にて政治家の秘書、社会起業家支援プログラムの立ち上げに携わった後に、東北の復興支援事業に関わり岩手で活動。その後東京にて参画した会社で組織開発・リーダーシップ開発の仕事をするようになり、独立。2015年9月にUターンし、鹿児島未来170人会議などを手掛けた後、仲間と共に「合同会社むすひ」を創業。対話をベースにした人-組織-社会-環境の結び直しをテーマに、様々な活動を行っている。薩摩リーダーシップフォーラムSELF発起人。
古川理沙 薩摩リーダーシップフォーラムSELF 代表理事
1977年鹿児島県生まれ。2000年から2019年まで日本語教師として韓国、中国、日本の大学、高専、民間学校、日本企業現地法人でカリキュラムマネジメントや、教科書執筆を行う。元ACTFL (American council of teaching foreign languages) OPI(oral proficiency interview) tester.海外での教師生活を起点に、新しい教育の在り方を実現するため鹿児島県霧島市に「ひより保育園」鹿児島市に「そらのまちほいくえん」を開園。また、霧島市にレストラン併設型の物産館「日当山無垢食堂」を構え、地元の生産者との連携を深め、広義の食育を実現すべく奮闘中。流通のあり方、消費者や生産者の食に対する意識をアップデートすることで、環境負荷の低減と食の豊かさ向上を同時に実現させたい。
全体像——関係性と意思決定で進化するSELF/薩摩会議
鹿児島で2017年に始まった小さな集まりが、いまや地域づくりの新しいモデルとして注目されている。NPO法人SELFと、そこから生まれた年次フォーラム「薩摩会議」である。SELFは、鹿児島の若手経営者や地域リーダーが中心となり、「150年後に何を残すか」という問いを起点に活動を広げてきた。
特徴は、カリスマ的リーダーや潤沢な資金に依存せず、関係性の質と意思決定の仕組みを磨きながら成長してきたことにある。その歩みは、次の6段階に整理できる。
1. 土壌の形成(〜2016)
鹿児島に蓄積されていた市民参加の文化(ネイチャリングプロジェクトなどのNPO活動)が下地に。
2.コア形成(2017–2019)
「150年後に何を残すか」という問い。合宿で肩書きを脱ぎ、人格でつながる関係性をつくる。
3.協働による関係性の強靭化(2019–2021)
SDGsフォーラムや県庁プロポーザルに共に挑み、協働によって関係性を裏打ちする。
4.制度化(2020–2021)
NPO法人化。「理事2名OK」と「ウルトラ兄弟モデル」により、挑戦しやすさと守るべきものを守る姿勢を両立。
5.境界拡張=薩摩会議(2022–2024)
内部の信頼を外部に接続する境界面。専門家や他地域を巻き込み、弱い紐帯を広げる。
6.自律分散(2025–)
公募制でエリアホストが自走。SELFが起点でなくても場が回る「多点発火型」へ。
これらを駆動するのは、理事を中心とした主要メンバー役割分担である。
以下に、今回のヒアリングの中で出てきた人物を記載するが、実際のSELFにはたくさんの人が関わっている。
野崎恭平(Visionary):代表理事 問いを投げ、最初に動く。
古川理沙(Guardian):代表理事 在り方を示し、守るべきを守る。
須部貴之 (Balancer):代表理事 プロジェクトを地に足つけ、行政等との連携を進める。
小平勘太(Administrator ):理事 会計などの庶務を担い、業務としての法人運営を担う。
勝眞一郎(Frame maker):理事 企画を即日形にし、議論を進める。
SELFは「関係性を深める」段階と「意思決定を整える」段階を交互に繰り返すことで進化してきた。
問いと合宿——コア形成の原点
SELFの物語は、一つの問いから始まった。2017年、西郷隆盛の曾孫との出会いの場で、坂口周一郎が野崎に投げかけた言葉である。
「150年前の彼らが今を生きていたら、自分たちが創り上げたシステムを一度全部壊すだろう。」
この言葉からSELFの根本テーマが生まれた。
「もし150年前の彼らが今を生きていたら、どんな国づくりを始めるだろうか?」
【ビジョンを掲げられなかった弱さ】
しかし野崎は当時を振り返り、こう語る。
「皆を納得させるビジョンを掲げる力が自分にはなかった。だからSDGsという“器”に逃げた。でも、それでよかったのかもしれない。」
この「逃げ」の告白は、SELFの逆説を物語る。
カリスマ的にビジョンを提示できなくても、共に考える問いを立てれば人は集まる。
【第1回合宿——25人の72時間】
2019年、SELFは25人を集めて廃校での合宿を開いた。古川は当時をこう語る。
「行きたくなかった。遅く行って早く帰ろうと思っていた。」
参加者の多くが「何をするか分からない」「期待もない」状態で集まった。自己紹介とペア面談を行い、昼は対話、夜は炊事・相撲・温泉。
「名前は知っているけど、会ったことはない」関係が、人格ベースの信頼へと変わっていった。
古川は振り返る。「初めは意味がわからなかった。でも、3日後には“この仲間となら何かできる”と思えていた。」この場で野崎が初めて掲げた言葉が、今もSELFを象徴している。
「エゴシステムからエコシステムへ」。
協働で強靭化する関係性
合宿で芽生えた信頼をさらに強めたのは、「一緒にやり切る」経験だった。
【SDGsフォーラム——外に開き、内を固める】
2019年6月、SELFは約100人を集めたSDGsフォーラムを開催した。SDGsカードゲームを使い、多様な人が「自分ごと」として参加できる器を提供した。
野崎は語る。
「当時は共通言語を持てなかった。だからSDGsを仮の旗印にした。それが皆で動ける助けになった。」
これは外に開く試みであると同時に、内部の仲間が共に挑戦する舞台でもあった。
【県庁18階プロポーザル——共通課題への挑戦】
同時期、SELFは鹿児島県庁の最上階でのプロポーザル事業に応募した。条件は「スタートアップから宇宙ビジネス、女性活躍まで全部盛り」という無茶なもの。メンバーは毎晩集まり、役割を分担して数週間にわたり企画書を仕上げた。
野崎は振り返る。「東京のコンサルに取られてはならぬ、という共通の敵と締切があった。あの緊張が一体感を決定的に強くした。」
古川も補足する。「一緒に何かをやり切った体験が、信頼を実務で裏打ちした。言葉よりも強かった。」
【協働による信頼の深化】
この経験は「外部への開放」ではなく、共通課題を協働で乗り越えることで関係性を強靭化した段階だった。関係性が心理的な「仲間意識」から、実務的な「一緒にやれる」という確信へと進化したのである。
制度化——挑戦と守りを両立させる意思決定
2020年11月、SELFはNPO法人として正式に制度化した。これは単なる形式上の法人格取得ではなく、これまで培ってきた関係性を壊さずに、次の挑戦を可能にする意思決定の仕組みを整えた転換点であった。
【「形」にする必要性】
2017年からの仲間集めと2019年の合宿を経て、SELFの輪は広がりつつあった。しかし、活動が大きくなるにつれ「誰がどこまで責任を持つのか」「何をSELFの名前でやるのか」という問いが避けられなくなった。法人格を取ることは、仲間内だけの関係性を、外部からも信頼される形に翻訳する作業でもあった。
【導入された二つのルール】
制度化と同時に、SELFはユニークな意思決定ルールを導入した。
1. 理事2名OKルール
15人の理事のうち、2名が賛成すればSELFとして事業を実行できる。野崎は言う。「自分にビジョンを掲げる力がないことは分かっていた。だから皆で考え、皆で動ける仕組みが必要だった。理事2名OKは、新しい挑戦を止めないための仕掛けだった。」
2. ウルトラ兄弟モデル
坂口修一郎が提案した。「このメンバーで団体をつくったら、やろうと思えば何でもできる。でもそれで市場を食い荒らしたら意味がない。普段はそれぞれの場所で活動し、必要なときだけ集まって力を発揮し、また散っていく。ウルトラ兄弟のように。」
このモデルは、守るべきものを守るための倫理的制約であり、SELFの行動が暴走しないためのセーフティネットだった。
【挑戦と守りのバランス】
この二つのルールは、表裏一体で機能した。
・理事2名OKが「挑戦のしやすさ」を担保する。
・ウルトラ兄弟モデルが「守るべきを守る姿勢」を保証する。
古川は語る。
「恭平が投げる提案はクレイジーに見えることも多い。でも、誰よりも動くのは彼自身。だから無責任な軽さにはならない。挑戦できる空気と、壊さない抑制の両方があった。」
勝はこう言ったという。
「僕の役割は“10%ペラ”をすぐ出すこと。アイデアが出たら、その日のうちにA4一枚にして皆に回す。完成度は低くてもいい。そうすると『そうじゃない』『こうすればいい』と議論が始まり、物事が前に進む。」
ここにも「挑戦を促し、守りを効かせる」バランスが表れている。
【意思決定のジレンマを越えて】
SELFの意思決定は、「民主的に多数決で決める」でも「リーダーが独断で決める」でもない。むしろその中間にある、挑戦と守りのバランスをとる仕組みだった。
野崎はこう言う。「大事なのは、意思決定が“進めるための道具”であること。止めるための仕組みにしたら、誰も挑戦しなくなる。でも、やりたい放題にしたら壊れる。だからその間をとる仕組みが必要だった。」
このルール設計により、SELFは次の段階——薩摩会議という境界拡張へと進むことができた。
薩摩会議——境界をまたぐ結節点
2022年、SELFは「薩摩会議」を始めた。
これは単なるカンファレンスではない。内部で育んだ信頼を、外部に接続するための境界面であった。
【「境界面」としての会議】
それまでのSELFは、合宿や共同プロジェクトを通じて、内部の関係性を深めてきた。
しかし、それをさらに進化させるためには「境界」を広げる必要があった。
野崎はこう語る。
「薩摩会議は、内部で積み重ねてきた信頼を、外に翻訳するための場だった。内部だけで閉じていたら、やがて硬直する。だから外部の人を呼び込み、自分たちの物語を見てもらう必要があった。」
会議は境界を広げると同時に、内部を新陳代謝させる装置でもあった。
【第1回——SELFが企画した全セッション】
初回の薩摩会議は、SELFメンバーが全てのセッションを企画した。
「この機会でなければ呼べない人」を呼び込み、それぞれが自分のテーマでセッションを設計した。
古川は言う。
「第2回・3回は、ほとんどが恭平の人脈?で成り立っていた。でも、それは“SELFの仲間がどういう人を呼び、どういう問いを投げたいか”を一番よく示す場でもあった。」
初回の薩摩会議は、SELFの内部ビジョンを外部に翻訳する最初の試みだった。
【第2回・第3回——外部との協働が深まる】
回を重ねるごとに、外部との協働が増えていった。
特に第3回では、外部からの参加者が主体的にセッションを担う場面も多くなった。
小平は語る。
「薩摩会議は“幹部候補との出会いの場”だと言われる。つまり、ここで人材と企業が出会い、事業が変わる。鹿児島のローカルにとっても、これ以上ない実利的な価値がある。」
外部の人が関わることで、SELFの内部に新しい問いや手法が持ち込まれ、内部の関係性が更新されていった。
【境界での信頼の試行錯誤】
境界を広げることは、同時にリスクも伴った。
「誰を呼ぶか」「SELFの名前で何を語るか」という葛藤は常にあった。
古川はこう語る。
「外部に開いた瞬間に、SELFが誰かのビジネスのために利用される危険もある。でも、閉じていたら進化しない。だからこそ、ウルトラ兄弟モデルの“守るべきものを守る”という制約が効いていた。」
薩摩会議は、内部での信頼を外に翻訳しながら、守るべき価値を壊さないための試行錯誤の場でもあった。
【境界拡張がもたらした変化】
薩摩会議は、SELFに3つの変化をもたらした。
弱い紐帯の増加
専門家、行政、金融、他地域の経営者との新しいつながり。
内部の更新
外部から持ち込まれる視点や人材が、内部の役割分担を再編した。
社会的共通資本としての認識
古川は言う。> 「薩摩会議やSELFは、社会的共通資本としてのインフラ。誰か一人の利益のためではなく、皆が希望を持ち合うためにある。」
薩摩会議は、内部と外部の境界を越える「翻訳装置」として機能したのである。
自律分散——公募制と希望の相互扶助
2025年、薩摩会議は大きな転換を迎えた。
それは「公募制」の導入である。
【公募制への移行】
これまでの薩摩会議は、SELFのメンバーが主体的に企画を担ってきた。しかし2025年からは、エリアホストと呼ばれる人たちが公募で参加し、「自分が呼びたい人」「自分が問いを投げたいテーマ」でセッションをつくるようになった。
野崎は言う。
「薩摩会議をSELFだけのものにしてしまったら広がらない。公募にすることで、僕らの想像を超える人やテーマが現れる。それが場を自律的に動かす力になる。」
この移行は、SELFが「主催」から「媒介」へと役割を変える瞬間だった。
【多点発火するエコシステム】
公募制によって、薩摩会議は多点発火型に進化した。
各エリアホストが、自分のネットワークで人を呼び、独自のテーマを設定する。
それぞれの点で関係性が生まれ、意思決定がなされ、また次の挑戦が起こる。
古川は語る。
「SELFが起点じゃなくても場が回るようになった。むしろ、SELFが前に出すぎない方がいい。いろんな人が“自分の薩摩会議”をつくっていけるようになった。」
これは単なる分散ではなく、関係性が自走する仕組みへの進化だった。
【事例:小平株式会社の会社変革】
SELF/薩摩会議がもたらす影響は、抽象的な理念にとどまらない。
小平勘太の会社の変革は、その象徴的な事例である。
Before
・100年続く企業だがその在り方が現代のビジネス環境に適合せず、組織や事業の停滞を招いていた。
Trigger
・SELFの活動を通じて池田亮平と出会う。この出会いが、新しい人材の流入と発想転換をもたらした。
Intervention
・ともにMVV(ミッション・ビジョン・バリュー)を再定義。本社を移転し、第4創業と題して会社の大きな変革を行う。
小平は語る。
>SELFの存在で自身や社内の視座が高められている。薩摩会議は年に1回、大きな問いをもらう場所でそこからの1年間、経営を通じてその問いに向き合うことで鹿児島の経営層のレベルアップが起こされる構造になっている。
After
・会社を180度変える人材と出会えた。鹿児島ローカルの視座が更新された。
薩摩会議は「人生が変わる出会いの場」とも言われる。
企業と人材が出会い、事業が変わる。これは地域企業にとっても実利的な価値を生み出している。
【希望の相互扶助】
野崎はこう語る。
「一人で希望を持ち続けるのは難しい。でも誰かと語ると希望を持ち続けられる。」
SELFと薩摩会議は、希望の相互扶助システムとして機能している。一人の資質に依存せず、仲間と希望を持ち合うことで、場は持続し、広がり続ける。
古川も同調する。
「ここに集まると、誰かが『自分はもう無理かもしれない』と思っていても、別の誰かが希望を語る。そのリレーで場が前に進んでいる。」
薩摩会議の自律分散化は、SELFが「場を独占するのではなく、共に使うもの」と位置づけ直した結果である。それは単なる組織拡張ではなく、社会的共通資本としてのエコシステムを形にする試みでもある。
ダニエル・キムのGood Cycle Modelから見たSELFと薩摩会議
SELF/薩摩会議の進化を「関係性の質」と「意思決定の仕組み」の連続として見てきたが、その背後には組織論で知られるダニエル・キムのGood Cycle Modelがはっきりと重なる。
キムは、組織の成果は「好循環」か「悪循環」かで大きく変わると説いた。
その好循環は、関係性の質 → 思考の質 → 行動の質 → 結果の質 → 再び関係性の質という流れで回っていく。
SELFをこのモデルに当てはめると、次のように整理できる。
1. 関係性の質
SELFはまず「関係性の質」を耕した。
・合宿で肩書きを脱ぎ捨て、人格でつながる信頼を形成。
・SDGsフォーラムや県庁18階プロポーザルへの挑戦を通じ、共通課題を一緒にやり切る協働体験を積み重ねた。
・薩摩会議の実施によって、内部の信頼を外部に翻訳し、さらに強固な関係性を築いた。
信頼を土台にしたことで、互いに遠慮せず、本音でぶつかれる関係が生まれた。
2. 思考の質
関係性の上に育ったのは、思考の質の変化である。
・「150年後に何を残すか」という長期的な問い
・「エゴからエコへ」という、個の利益から共同体全体へ視座を変えるビジョン
年に一度の薩摩会議で、普段の業務では得られない深く強い概念や情報のインプットを受ける。信頼をベースにした関係性があるからこそ、こうした大きな問いや概念に向き合える。
3.行動の質
思考は具体的な行動に変わる。SELFの行動は、試行と協働に特徴がある。
・「理事2名OK」や「10%ペラ」といった、挑戦を止めない仕組み。
・「SELFの関係者だからこそできる」全員にとって意味がある強い施策の実行。
・一人の想像を超えたアウトプットが、仲間と協働する中で形になる。
行動が「個人プレー」ではなく「協働からしか生まれない成果」になっている点が重要である
4. 結果の質
その結果として表れるのは、単なる事業成果ではなく、一人ひとりの深い内面の変化だ。
・各人が「自分はどう在りたいか」を見直す契機になった。
・個々の事業においても、事業変革や人材獲得といった具体的成果につながった。
・薩摩会議は年々変化し、外部へ広がる「多点発火型」のプラットフォームへと進化している。
結果の質が高まると、再び関係性の質が高まり、次の循環が始まる
【好循環の実装】
SELFが示したのは、「思考」や「行動」から始めるのではなく、まず関係性の質を耕すことが好循環の起点になるということだ。
古川は語る。
「最初の合宿で、みんな“何をするか分からない”まま集まった。でも一緒にご飯を作り、相撲をとり、時間を過ごすうちに信頼ができた。そこから考えや挑戦が始まった。」
この順序が、SELFの強さを支えている。
再現可能なエッセンス
SELF/薩摩会議の経験は、他地域でも応用可能な普遍原理を示している。
そしてそれは、ダニエル・キムのGood Cycle Modelの循環(関係性→思考→行動→結果→再び関係性)に対応している。
【普遍原理 5つ】
1. 合宿プロトコル(関係性の質)
非日常の場で肩書きを脱ぎ、人格でつながる。参加者は携帯を預けて日常から切り離され、自己紹介やペア面談、余白の時間を共にする。こうして「一緒に過ごした体験」そのものが信頼の土台を形成した。
2. 協働による関係性の強靭化(関係性の質 → 思考の質)
共通課題を一緒にやり切る。SDGsフォーラムや県庁プロポーザルのように、締切や外部要求といった「適度な圧」を組み込み、信頼を実務で裏打ちする。その経験が「次の問い」を共有できる状態をつくる。
3. 長期の問いと深いインプット(思考の質)
「150年後に何を残すか」という長期の問い。「エゴからエコへ」という視座の転換。さらに年に一度の薩摩会議では、普段の業務では得られない深く強い概念や知識をインプットし、思考の地平を広げてきた。
4. 意思決定の仕組み(行動の質)
挑戦しやすさと守る姿勢の両立。理事2名OKによる試行の自由と、ウルトラ兄弟モデルによる倫理的制約。これによって「小さく速く試す」と「壊さない」の両立が可能になった。
5. 役割アーキタイプと希望の相互扶助(結果の質 → 関係性の質)
・Visionary(前衛):問いを投げ、動き出す。
・Guardian(守護):在り方を示し、守るべきを守る。
・Balancer(調和):プロジェクトを地に足つけ、行政等との連携を進める。
・Administrator(運営):会計などの庶務を担い、業務としての法人運営を担う。
・Frame maker(具現化):企画を即日形にし、議論を進める。
この関係者の補完関係に加え、希望を一人で抱え込まず、仲間と持ち合う仕組みがある。
成果は一人ひとりの内面の変化と事業の変革として現れ、その結果が再び関係性を強めていく。
【チェックリスト】
・肩書きを脱いで人格で信頼し合う場を設計しているか
・共通課題を一緒にやり切る経験を組み込んでいるか
・長期の問い(哲学)や深いインプットの場を用意しているか
・意思決定に「挑戦」と「守り」の両輪があるか
・Visionary/Balancer/Operatorの役割が揃っているか
・希望を個人ではなく、仲間と持ち合えているか
地域それぞれの未来へ
地域の未来は「計画」からではなく「関係性」から始まる。
そして、挑戦を促しつつ守るべきを守る意思決定が、その関係性を持続させる。
SELFと薩摩会議が示したのは、150年先を見据えながら、今この瞬間の関係性を大切にするというシンプルな原理である。
あなたたちの地域は150年後に何を残しますか?
執筆後記
この記事は多くの地域で真似て欲しいと思って作りました。
しかし、ただここに書かれたことを行動としてやればいいと思ってしまうようなガサツな人ではきっと成し遂げられない。それくらい、綱渡りのようなバランスで、相互の信頼を一歩づつ積み上げた結果にある関係性です。
SELFや薩摩会議に関わる登場人物は一人一人が主人公である。鹿児島の外部から、薩摩会議だけをみていると野崎恭平という1人のリーダーがいるように見えるが、そうではない。
『鬼滅の刃』において、炭治郎と鬼の物語をメインストーリーとしながら、仲間の柱達の人生や、敵キャラクターが鬼になる背景など一人一人が主人公とも言えるほどの物語を紡いだことで、多数の創作ストーリーが生まれ、いまだに愛され続けているように、鹿児島でSELFに関わる人々は一人一人が主人公だった。
SELFで理事を務めるりささんは、恭平に巻き込まれたかのように戯けるが、彼女が始めた「ふつうの小学校」というプロジェクトも、彼女が主役のように見えて、それを支えるウッシーや勝さん、みずきちゃんも、一人一人が秋田や奄美大島や広島で物語を持つ主人公である。
これを彼女は、「SELFは能の面であり、踊りの舞台である」と表現する。能の舞台では役割があり、自分なりの表現を行うが、舞台を降りるとそれぞれの物語がありそれを続けていくのだ。
こうして、一人一人が自分のビジョンを持ちながらも時にお祭りや神楽のように一致団結し、150年後に向けたある種の祈りを捧げるような場が「薩摩会議」である。
薩摩会議は3日間のこれからの鹿児島や日本の未来を共に作っていく鹿児島県内外の仲間を集めた約600名規模のカンファレンスである。
特に前回から始まった2日目に13の鹿児島の地域に分かれてフィールドダイアログを行うことが特徴となっている。そして13の地域に分かれても、十分に一つ一つの地域で衝撃的な体験が待ち受けているということもまさしく薩摩会議やSELFに人々が一人一人主人公だからである。
今回、恭平くんとりささんへの複数回のインタビューを通してこの大きなうねりがどのように起きたのかを構造化しようと試みた。
その過程の中で感じたのは近年DAOのような自律的な組織を目指す様子を散見するが、そこには「脱中心」という構造を見るような気がする。しかし、自律分散ということは「脱中心」ではなく「多中心的」であるということが重要だと感じたのが大きな感覚である。
この記事を読んで9/21からの薩摩会議に申し込んだり、参加する前の参考にしてもらえると嬉しい。

PROFILE
ゼブラ編集部
「ゼブラ経営の体系化」を目指し、国内外、様々なセクターに関する情報を、一緒に考えやすい形に編集し、発信します。