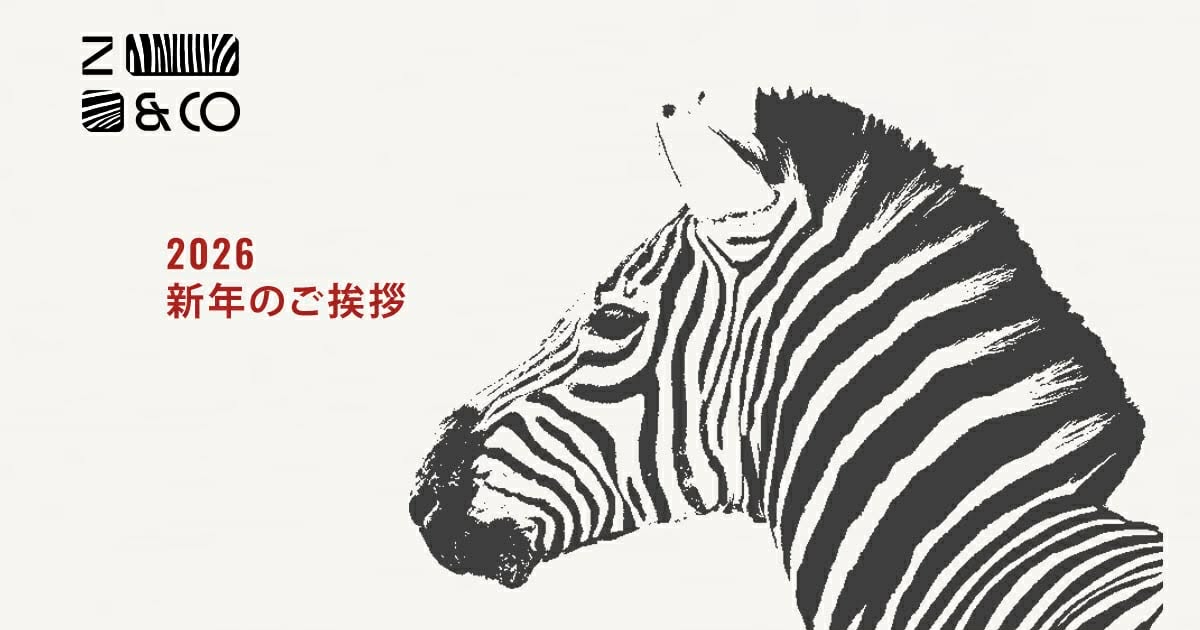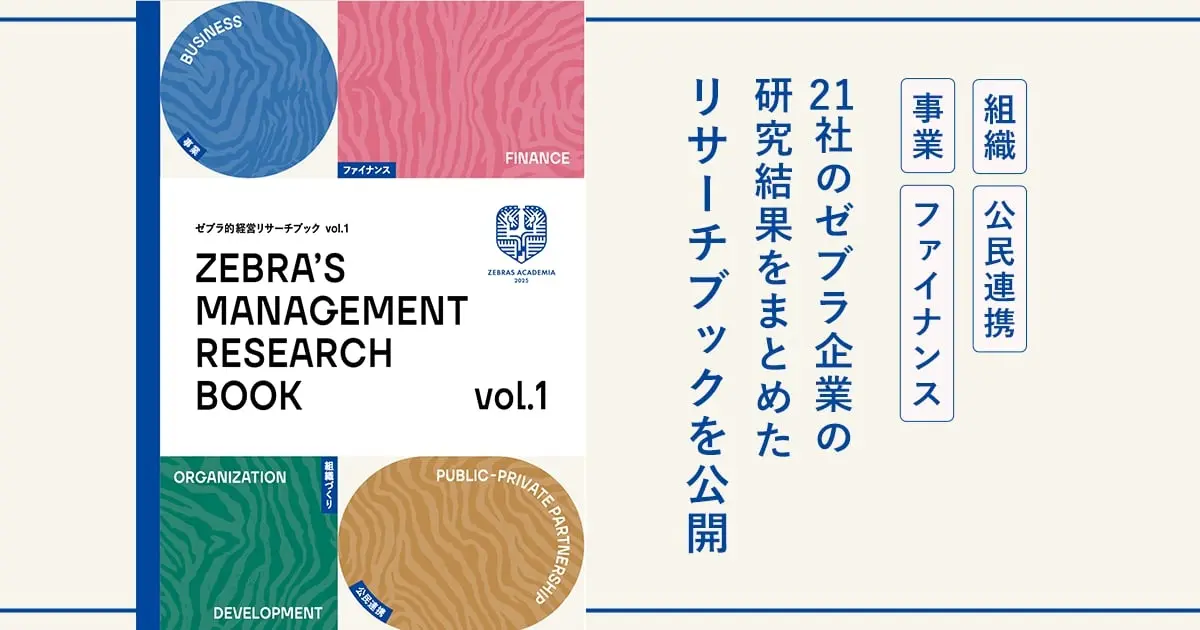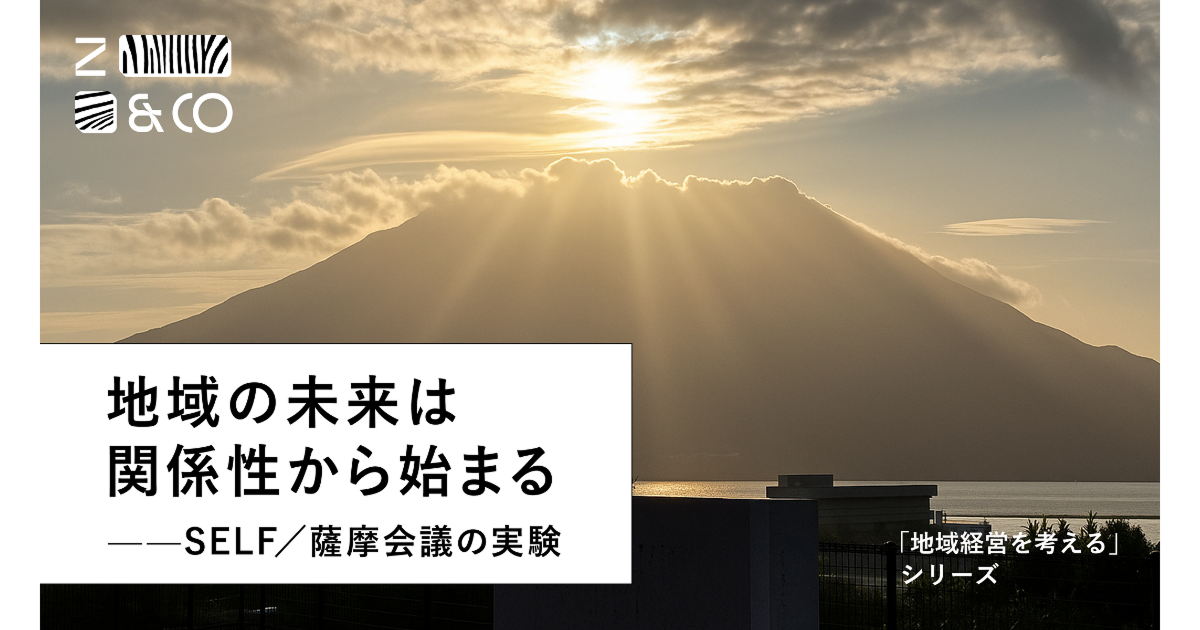2025.07.31 ZEBRAS
“自然に投資する”という挑戦~EU発「ネイチャークレジット」始動、日本へのヒント

自然にお金を「投じる」時代が始まった
2025年7月、EUが「ネイチャークレジット市場」の制度設計に正式に着手しました。これは、森林再生や湿地の保全、生物多様性の回復といった自然環境への貢献活動を“クレジット”として認証し、それを企業や国が購入できるようにするという仕組みです。
目的は、自然を守ることに直接的な資金を流し、経済活動と自然保全を両立させること。環境保護を「コスト」ではなく「投資」と捉える発想の転換が、いま欧州から始まりました。
とはいえ、制度はまだ走り始めたばかり。具体的な市場整備はこれからであり、その評価や運用方法についても議論が続いています。しかしその未完成さこそ、私たちにとっても学びと行動のきっかけになり得ます。
本稿では、ネイチャークレジット制度の基本とその背景、そして日本にとってのヒントを読み解いていきます。
ネイチャークレジットとは何か?
ネイチャークレジットは一言でいえば、「自然にポジティブな変化を与えたこと」に対して発行される証券のようなものです。たとえば、
- 森林の再生(CO₂の吸収、生物多様性の回復)
- 湿地や川の保全(浄水・洪水調整などの生態系サービス)
- 再生型農業の導入(土壌保全、害虫抑制)
といった取り組みに対して、第三者による認証を受けることでクレジットが発行されます。このクレジットは、企業が自社の環境貢献として購入できる仕組みです。
カーボンクレジットとの違いは?
このモデルの特徴は、従来のカーボンクレジット(=二酸化炭素削減量の売買)とは異なり、“生態系の多面的な価値”に着目している点にあります。削減量だけでは測れない、自然そのものの「質」や「豊かさ」を経済の文脈で捉え直そうという試みです。
カーボンクレジットは、温室効果ガスの排出削減量を「1トンのCO₂削減」など定量化された数値で取引する仕組みです。そのため、指標が明確で説明責任を果たしやすく、市場でも既に一定の成熟度があります。一方、ネイチャークレジットが扱うのは、より複雑で場所に依存する価値です。
つまり、ネイチャークレジットは「見えにくい価値をどう見える化し、市場の中で取り扱えるようにするか」という点で、よりチャレンジングな仕組みです。日本ではカーボンクレジットに比べてなじみが薄いですが、自然の保全活動そのものに報酬を与えるという観点では、地域経済やローカルイニシアティブとの親和性が高いとも言えるでしょう。
EUがこの制度に踏み切った理由
背景には、EUが抱える深刻な資金不足があります。EU委員会によれば、EU全体で生物多様性の保全に必要とされる年間投資額はおよそ370億ユーロ(約6兆円)に上りますが、現状の公的資金では大きく不足しています。
そこで欧州委員会は、市場の力を活用して自然保全に資金を呼び込むという新たな道を模索しました。「この制度は自然を商品化するものではなく、自然を守る人々に報酬を与えるための仕組みです」と、EUの環境担当委員ジェシカ・ロスウォール氏は強調します(出典:Reuters)。
2025年中に専門家グループを設置し、2027年にはEU域内でのパイロットプロジェクト実施が予定されています。制度設計には、政府機関だけでなく科学者、地域住民、農林関係者、NGOなど多様なステークホルダーが参画する見込みです。
なぜ今なのか?
国際的な背景として、生物多様性条約(COP15)で掲げられた「30by30」目標(2030年までに陸と海の30%を保全)や、金融業界におけるTNFD(自然関連財務情報開示)の枠組みが登場したことも見逃せません。これらの動きは、自然資本を単なる環境政策ではなく「投資や財務の対象」として捉え直す転換点を示しています(参考:CBD、TNFD)。
企業サイドの関心も高まっています。一部の先進的なグローバル企業は、生物多様性を可視化・評価する仕組みを求めてネイチャークレジットに関するパートナーシップ検討を進めています。ESG投資の深化にともない、「自然を守る行動をどう測定し、報いるか?」という問いが、企業の経営課題として浮上してきているのです。
すでに始まっている欧州の実践
ネイチャークレジット制度はこれから設計される段階にありますが、すでに欧州各地では自然価値を可視化・取引可能にしようという取り組みが動き始めています。
イタリア:3Bee
イタリアのネイチャーテック企業「3Bee」は、生物多様性スコアを用いたBiodiversity Creditを開発。ミツバチに装着したセンサーを使って、周辺環境の健全性をリアルタイムでモニタリングし、そのデータをもとに保全活動の成果をクレジット化する仕組みを展開しています。
スウェーデン:CreditNature
スウェーデンでは、NatureCreditをはじめとしたスタートアップが、EU制度を見据えて独自の認証基準や衛星データによるモニタリング手法を開発中です。自然資本の評価を客観化・標準化する技術開発が、制度設計と並行して進行しています。
オランダ・フランス:再生農業プロジェクト
また、オランダやフランスの再生型農業のプロジェクトでは、土壌中の炭素貯留だけでなく、昆虫や鳥類など生物指標を加味した「複合的な生態系価値の計測とクレジット化」が模索されています。こうした動きは、単一の数値で自然を評価するのではなく、多層的・多様な自然のあり方を捉え直すアプローチとして注目されています。
問いを残す制度、だからこそ関われる
もちろん、制度設計の難しさは少なくありません。生態系の価値は測定が難しく、「どの活動がどれだけの貢献になるか?」という定量的評価には限界があります。また、認証制度が不十分なまま進めば、“グリーンウォッシュ”の温床になるという批判もあります。
実際、森林保全をうたった一部のパイロットでは、かえって森林が伐採されていたというNGOの調査報告もあります(参照:Fern/Canopée)。
それでも、こうした批判や問いかけは制度を否定するものではなく、むしろ「どうつくるか」「誰が守るのか」という本質的な対話を引き出す契機になるはずです。
まだ制度が未完成だからこそ、私たちもその形成過程に関心を持ち、ローカルな現場と照らし合わせながら参画の可能性を探ることができるのではないでしょうか。
日本へのヒント──ローカル経済に広がる可能性
ネイチャークレジットの考え方は、日本の地方や企業にとっても他人事ではありません。
たとえば、里山や森林、湿地などを活かした地域再生の取り組みは各地で進んでおり、既に一部では「地域独自のクレジット(ローカルカーボン)」の仕組みが模索されています。 農業・林業・漁業といった一次産業に関わるプレイヤーが、自然資本の守り手として新たな価値を生み出す可能性もあります。
さらに、企業にとっても、CSRやESG投資の一環として、炭素だけでなく「自然そのもの」に対する投資をどう設計するかは今後のテーマになり得ます。 日本でも独自にネイチャークレジット制度が始まるとは限りませんが、EUの設計プロセスや思想からヒントを得て、地域×企業×自然の新しい関係を構想することは十分可能です。
“守るだけ”から“育てて支える”へ
ネイチャークレジットは、まだ評価も不安定で、制度として完璧なものではありません。けれど、「自然を守る活動に経済的な価値がある」と明示するこの制度は、ひとつの問いを私たちに投げかけています。
「自然を守ることは、未来を支える経済活動たりうるのか?」
その問いの先にあるのは、補助金やボランティアに頼らない、“自立可能な自然保全”というビジョンです。この未完成な仕組みに目を向けることが、逆説的に、私たちの足元にある資源や関係性を見直すヒントになるかもしれません。
文:岡徳之(Livit)

PROFILE
Noriyuki Oka
編集プロダクションLivit代表。サステイナビリティー先進国・オランダを拠点に、ゼブラ企業や地域循環型モデルを調査・執筆。有力メディア(NewsPicks、東洋経済オンラインなど)や企業オウンドメディア向けにコンテンツ制作を手がける。 https://livit.media/