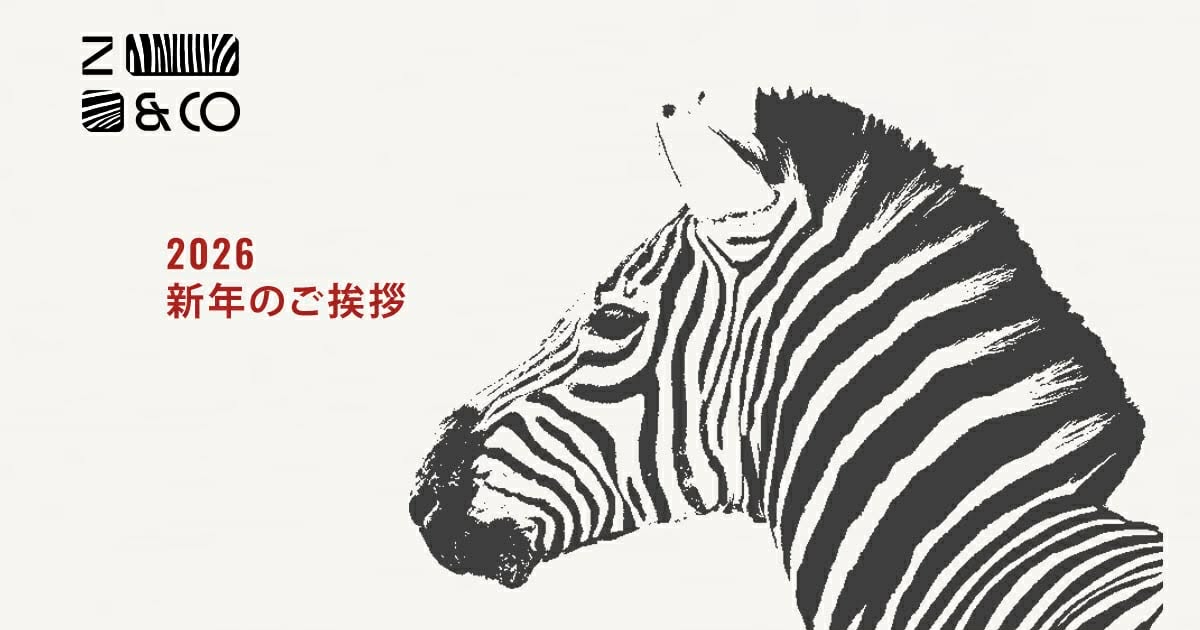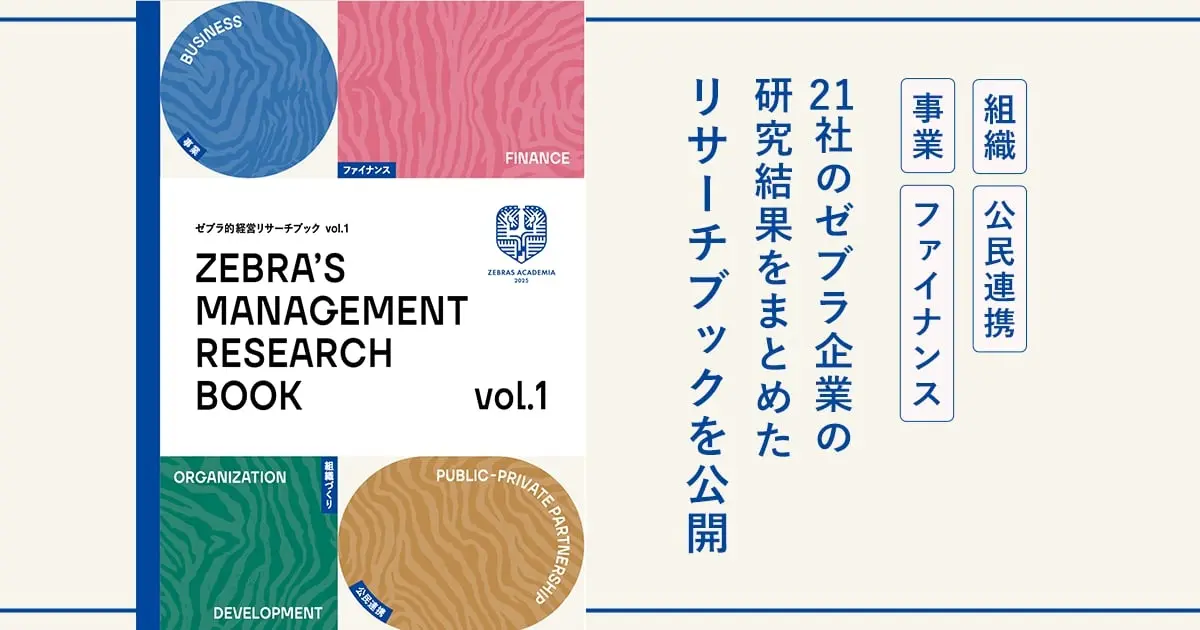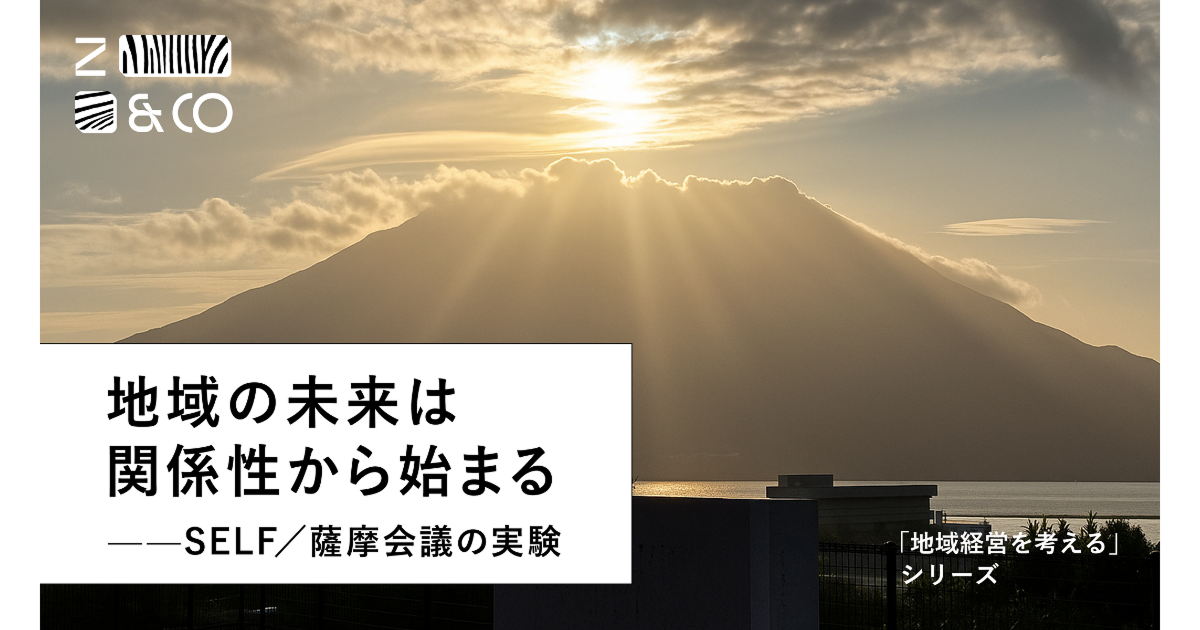2025.05.20 ZEBRAS
Z&C出資先のNEWLOCALがシリーズAとして4億円を調達。地域で事業を行うゼブラ企業が、新たにVCも株主に迎えた選択の背景と学び

地域にまつわる事業を手がける企業が、ベンチャーキャピタル(VC)を株主に迎えてシリーズAの資金調達を行う。そんな珍しい動きを見せたのが、Zebras and Company(以下、Z&C)の出資先である株式会社NEWLOCALです。代表取締役の石田遼さんは、2025年5月16日に、4億円の資金調達を完了しました。
なぜ、NEWLOCALはVCを新たな株主に迎えたのか。資金調達の背景と、その過程で得た学びとは。そして、新たな株主との連携や事業の展望をどのように描いているのか。Z&Cの阿座上陽平さんと田淵良敬さんが聞きました。
実行力と透明性を武器に“ハードシングス”を乗り越えた1年半
阿座上さん:
まずは資金調達お疲れ様でした。今日は4億円という、ゼブラ企業にとっては大型の資金調達の裏側を聞きたいと思います。2023年9月に出資をさせてもらったときは、野沢温泉、男鹿、御代田の3地域で事業を行っていました。そこから約1年半の事業進捗から聞かせてください。
石田さん:
ありがとうございます。出資してもらったときからでいうと、事業を行う地域が2つ増え、合計で5つとなりました。あの時はまだ私と社員1名だけでしたが、5月には社員も12名になり、組織も順調に拡大しています。
野沢温泉はようやく宿泊施設の工事が進み、近いうちに旅館業の免許も取れそうです。男鹿では宿泊施設がオープンし、もうひとつの蒸留所とレストランの複合施設についても計画が進んでいます。
新たに加わった地域のひとつ「丹後」は、先行する男鹿と同じくらいの進行状況です。現地の事業責任者が非常に優秀、かつ既存の地域で得たナレッジをうまく活用できているため、かなりスムーズに進められています。
また、この1年半の変化として大きかったのは、野沢温泉のまちづくりを主導する「株式会社野沢温泉企画」が、令和6年度「地域の社会課題解決企業支援のためのエコシステム構築実証事業(ローカル・ゼブラ推進政策)」に採択されたことです。地域外の方の知見や目線を取り入れたり、外部の様々なプレイヤーとつながることができました。
阿座上さん:
ひとつの地域がうまく回り出すと、他の地域も加速度的に進んでいく。まさにNEWLOCALが創業時から掲げていた「スピード・スケール・再現性」が実践され始めていますね。そして、ローカル・ゼブラ企業に選ばれたことで、地域内外での対話も進んだということですね。
順調に見える一方で、いろいろな苦労もあったかと思います。一番の成功要因はなんだと思いますか?
石田さん:
ひとつは、「実行力」です。簡単にいえば「必要なことは全部やる」ということ。よく周囲の経営者から、採用や資金調達のコツを聞かれますが、特別な方法があるわけではありません。必要なことを愚直に実行してきただけです。
ゼブラ的な経営と言っても取るべき方法は、既存の経営学の中でもある程度出尽くしていると思います。あとはそれをどれだけ実行できるか。人はつい楽なほうに流れてしまいますが、僕は過去にそれで痛い目を見たこともあるので、その反省を活かして、甘えずにやり切ることを意識してきました。
もうひとつ大事にしてきたのは、「透明性」です。特にネガティブなことや困難な状況に関しては、関係者に対してオープンに共有することを心がけてきました。たとえば、後でも話しますが、資金ショートの危機があったときは、その状況をきちんと社員にも伝えました。
一度隠してしまうと、あとから取り返すのは難しくなるので、最初からオープンにする。それができたのは、ネガティブなことや困難も一緒に受け止めてくれるメンバーだと、信じていたからです。
阿座上さん:
過去の学びをもとに、経営者としてのスタンスを貫いたということですね。今回はZ&Cの記事でもあるので、我々との関わりのなかでよかった点があれば教えてください。
石田さん:
Z&Cは、単なる出資者ではなく、対等なパートナーでもあると思っています。創業時期も近く、共同創業者がいない僕としては、同じ目線で相談できる相手がいるのはとても助かりました。
また、ゼブラの特徴である「群れ」を感じられたのもありがたかったです。阿座上さん、田淵さんとは様々なイベントで顔を合わせましたね。経営者同士だけではなく、メンバー同士もつながっていけたらいいなと思っています。
阿座上さん:
田淵さん、出資者側の立場からNEWLOCALの1年半をどのように見ていますか?
田淵さん:
出資したころから「10地域展開・売上100億円」という目標を掲げていましたが、思った以上のスピード感で進められていて素晴らしいなと思っています。また、事業成長の仕方や組織のつくり方など、この1〜2年でNEWLOCALから学ばせてもらうことも多くありました。
石田さんとのやりとりで印象的だったのは、昨年末、資金ショートの危機に直面したときのことです。新規投資家に対してその状況をどこまで伝えるか、伝えたら資金調達がうまくいかないのではないか、ということに石田さんは葛藤していました。
そこで相談を受けて、「長期的な信頼関係を大切にするため全部共有しよう」「契約条項に引っかかる可能性もあるから共有すべき」と、感情と論理の両面で考えを一緒に整理をしました。結果的に、正直に状況を伝えたことで、投資家のみなさんも理解・納得してくれて、資金調達をうまく進めることができました。
石田さん:
本当にあれはハードシングでした。でも、あの局面で素直にコミュニケーションがとれたことで、関係者との信頼がより深まったんです。
田淵さん:
一緒に乗り越えられて本当によかった。こういう正解のない問題について相談をしてもらえるのは、出資側としてもありがたいことです。
「ビジョンを共有した“同志”になれると思った」サムライインキュベート参画の背景
阿座上さん:
では、今回の資金調達の話に移っていきます。地域のまちづくりの会社で「シリーズA」、しかも4億円規模のVCも交えた資金調達は珍しい事例だと思います。その選択の背景から教えてもらえますか?
石田さん:
不動産を起点とした地域事業やまちづくりを進めていくうえで、融資だけではゆくゆくは調達が賄いきれず資金がボトルネックになることはわかっていたので、最初からエクイティでの調達を計画していました。ただ、出資を受け入れるということは、見合うリターンの約束をするということでもあり、変に利益重視になりすぎたり、成長の形が歪んでしまう懸念もあるため、お互いの理想を目指すために投資家たちと検討を重ねてきました。
本来の計画でいえば、このシリーズAのタイミングでは事業会社によるCVCを中心に約3億円ほど調達する予定でした。しかし、先ほどから話している資金ショートの危機を背景に、VCへもアプローチをすることに。そこでの対話を通じて、調達額も1億円追加して4億円となりました。
阿座上さん:
なぜ当初の計画ではCVCを中心に資金調達しようと考えていたんですか?
石田さん:
NEWLOCALはまちづくりを事業にしているので、事業会社と連携できる余地が大きいと考えていたからです。それに、「短期イグジット・ハイリターン」ではない考えを持っている事業会社も多いため、ビジョンに共感してもらいつつ「同志」のような関係を築くには、そっちのほうがいいのではと考えていました。
阿座上さん:
なるほど。そこからVCを入れることにした経緯を教えてください。
石田さん:
CVCの担当者と話を進めるなかで、「リード投資家を入れる必要がある」ことや、「各社の1社あたりの出資額では3億円に届かないかもしれない」といった現実的な課題が見えてきたんです。
さらに、そのタイミングで、資金ショートの件が顕在化しました。年末までの約2ヶ月間で、資金を確保しなければならなかったのですが、そこまでに投資を決めてもらうのは現実的ではない。そこで、間口を広げてVCにもアプローチを始めたんです。今回のリード投資家であるサムライインキュベートは、SANUの福島弦さんから紹介していただきました。
阿座上さん:
サムライインキュベートをリード投資家に迎えた決め手はなんでしょうか?
石田さん:
事業の性質上、上場までにある程度の時間がかかる可能性があることや、イグジットの形も柔軟な選択肢を持っておきたいことを理解してくれたのが大きかったです。また、「経済価値よりも地域価値を重視する」という僕らの考え方にも共感を示してくれました。既存株主と近い考え方を持っている投資家だと感じたので、リード投資家をお願いすることにしました。
リード投資家となったサムライインキュベートのサポートは、とても手厚いものでした。他の投資家との窓口になってくれたことで、話もスムーズにまとまり、年内にファーストクローズが完了。無事、資金ショートをまぬがれました。
阿座上さん:
ファーストクローズ後の動きについても教えてください。
石田さん:
年始に入ってから、「今のタイミングで、多少持分を下げてでも、もう少し調達額を増やしたほうがいいのでは」という話を、サムライインキュベートの方からもらいました。今回は、理念に共感して投資してもらえる、いわゆる「理念型投資」の最後のチャンス。次のラウンド以降は、より実績やリターンを厳しく見られるようになるから、ここで集められるだけ集めておこうと。
田淵さん:
投資家を増やすことで、ダイリューション(株の希薄化)の懸念もあったかと思います。
石田さん:
そこは慎重に考えなければと思っていました。ただ、数十人の投資家と話す中で、「次の資金調達は決して楽ではない」ということも肌で感じていたんです。さらに、調達には半年ほどかかるので、2年後に次を予定するなら1年半後にはもう動き出さないといけなくなります。そう考えると、多少持分を下げてでも、調達額を増やすべきだと判断しました。
阿座上さん:
VCとの対話を通して、次回以降のラウンドまで見通すことができたからこその決断だったと。田淵さんからも、サムライインキュベートの参画や関わり方についてどう捉えているのか、教えてもらえますか?
田淵さん:
NEWLOCALと新株主、既存株主の間を取り持ってくれた存在でした。また、追加の資金調達も提案して具体的なアドバイスをしてくれましたし、リード投資家として、今回の資金調達を引っ張っていってくれたのは間違いありません。
また、NEWLOCALの未来に真剣に向き合っていることを感じました。僕と阿座上さんとサムライインキュベートの担当者で顔合わせをしたときのこと。VCとしてファンドの期限があるのは前提ですが、仮にNEWLOCALのイグジットのタイムラインが伸びた場合にも備え、「LPと交渉する」「セカンダリーでバトンを渡す」といった、具体的な対応策を検討していることを話してくれました。
石田さん:
サムライインキュベートのLPには地域金融機関もいるので、もともと地域というテーマを持っていました。また、生々しい話ですが、セカンダリーで地域金融機関のCVCにバトンを渡すというようなプランBも含めて、いろいろな選択肢を一緒に考えてくれたんです。
阿座上さん:
資金調達を考えるうえで、VCの投資方針に加えて、「LPの意向や事業内容とフィットしているのか」という観点も考えられると、取りうる選択肢が変わってきそうですね。
「VCへのイメージが更新された」資金調達の実務内容と気づき
阿座上さん:
資金調達の全体像がわかったところで、具体的に石田さんがどのような実務をしていたのかを教えてもらえますか?
石田さん:
最初に取りかかったのは、資金調達用の提案資料と、アプローチする投資家リストの作成です。最終的には100名ほどピックアップして、面談は累計で70〜80時間ほど行いました。
提案資料の内容は「どんな事業をしているか」「なぜ資金を集めるのか」といった基本的なもので、企業ごとの個別提案までは手がまわりませんでした。その代わり、データルーム(デューデリジェンスに必要な資料をまとめたもの)は最初から準備しておき、NDAを結べばすぐに共有できるようにして効率化を図っていました。
あとは、今のフェーズでは回答できない、もしくは回答するのが適切ではない質問に対しては、線引きをしていました。質問対応にリソースを割きすぎて事業を止めるわけにはいかないので、面談内でできるだけ回答させていただくスタンスをとりました。
田淵さん:
全部で半年くらいかかったと思いますが、その間の稼働状況はどのくらいでしたか?
石田さん:
年末の2カ月間は、リソースの半分以上を資金調達にあてていました。資金ショートを回避するのが最重要だったので、社内にも「この期間は返信が遅れるかもしれない」と事前に伝えていました。
年始からは、サムライインキュベートのサポートもあり、自分の稼働は1〜2割に落ち着きました。このころには投資家側の検討フェーズに入るので、僕ら側でやることはそこまでありません。ただ、サムライインキュベートが投資家との窓口になってくれていなければ、後半戦も質問対応などで忙しくなっていたと思います。
阿座上さん:
実務面でも、サムライインキュベートの存在は大きかったんですね。今回の資金調達を振り返って、大切なポイントはどこだったと思いますか?
石田さん:
まず自分たちのスタンスを明確にすることですね。「調達をすべきか」「どんな株主と組みたいか」「イグジットの形をどうするか」といった方針が定まっていないと、外部との対話のなかでブレが生じてしまいます。
また、事業ロードマップを持っておくことも重要です。NEWLOCALでは、創業当初から「10地域展開・売上100億円」という目標を掲げています。もちろん、日々の進捗や環境変化にあわせて細かな部分は修正していますが、大枠の方向性はぶれていません。
素案でもいいので、あらかじめ道筋を描いておくことで、投資家との対話を通じてアップデートしていくことができます。
阿座上さん:
投資家のなかでも、VCと正式に対話をするのは今回が初めてだったと思いますが、それによる気づきはありましたか?
石田さん:
もともとVCに対して「リターン重視の存在」という印象を勝手に持っていましたが、中にはいろんなスタンスの方がいるんだと知りました。
また、今まで接点がなかった十億円規模の出資が可能な投資家とも話すことができ、「野沢温泉以外の地域でも1億円規模の事業ができれば、出資を検討できる」といった基準も知れました。事業のロードマップをアップデートする際の参考になっています。
さらに、サムライインキュベートのアドバイスもあり、既存の資本市場のルールや慣習なども知ることができました。総じて、今後のラウンドに向けたいいステップになったなと思います。
資金調達を毛嫌いせず、VCも含む多様な投資家との対話を
阿座上さん:
シリーズAの調達を無事終え、今後の事業の展望や株主との協業についてどう考えていますか?
石田さん:
まずは、既存地域での事業をしっかり伸ばしながら、新しい地域への展開も進めていきます。足元では開業準備が進んでいるところもありますし、これまでのナレッジを活かして、10地域まで着実に増やしていきたいと思います。
株主との協業については、もともとNEWLOCALの事業としても考えていたBtoBコンサルや事業開発支援を、さらに加速できればと考えています。JR東日本スタートアップ・JR西日本イノベーションズ・KDDIといった新しい株主とも連携しながら、企業が地域でどう関わっていけるか、具体的な形を模索していきたいです。
阿座上さん:
既存株主と新株主間のコミュニティづくりについて、何か考えていることはありますか?
石田さん:
新株主を交えた顔合わせも予定しています(編集注釈:取材時期は顔合わせ開催前)が、まずは新株主のみなさんと個人対個人でしっかり関係を築いていきたいです。既存株主と同様に、ビジョンへの共感をベースにつながっていきたいと考えています。
阿座上さん:
田淵さんから、今後のNEWLOCALに期待することはありますか?
田淵さん:
これからは、描いてきたビジョンを実現していくフェーズだと思います。新たな株主が加わって、NEWLOCALがどう成長していくかが楽しみです。
加えて、Z&Cが投資で研究しているテーマのひとつである「Place-Based Impact Investing(地域協働型インパクト投資)」のあり方も、新株主や地域に関わる様々なステークホルダーのみなさんと一緒に探求できればと思っています。
阿座上さん:
最後に、これから資金調達を考えているゼブラ企業や経営者に向けて、伝えたいことはありますか?
石田さん:
資金調達を毛嫌いせずに、チャンスとして捉えてほしいと思っています。また、ゼブラ企業だからといって、最初からVCの選択肢を除外するのももったいない。ゼブラ企業が多種多様なように、VCのあり方も様々です。
逆に、今回インパクトVCの方々ともたくさん話しましたが、インパクト測定の粒度間の違いなどで「相性が合わない」と感じることもありました。「社会課題解決型の事業だからインパクト投資」と安易に結びつけるのも、視野を狭くしてしまうかもしれません。
資金調達は大変ですが、得られるものも大きいです。自分たちのスタンスがクリアになったり、事業を前に進めるきっかけになる。実際にするかどうかに関わらず、資金調達のことを考えてみたり、投資家と対話をしてみたりするプロセスに価値があると思います。
田淵さん:
同感です。ゼブラ企業の多くは地域に根ざしている企業ですが、そうした企業だからといって、すべてを地域内で完結させる必要はないと思います。特に創業初期は、外部から資金を取り入れたほうが成長につながるケースも多い。そのうえで、大切なのは、外から入れた資金をきちんと地域に還元する設計をすることです。
同時に、投資する側にも「どんな意思を持ってお金を出すのか」という視点が求められます。今回のNEWLOCALの資金調達が、投資家とゼブラ企業の双方にとって、ひとつの参考になればと思っています。

PROFILE
Fumiaki Sato
編集者・ライター・ファシリテーター。「人と組織の変容」を専門領域として、インタビューの企画・執筆・編集、オウンドメディアの立ち上げ、社内報の作成、ワークショップの開催を行う。趣味はキャンプとサウナとお笑い。