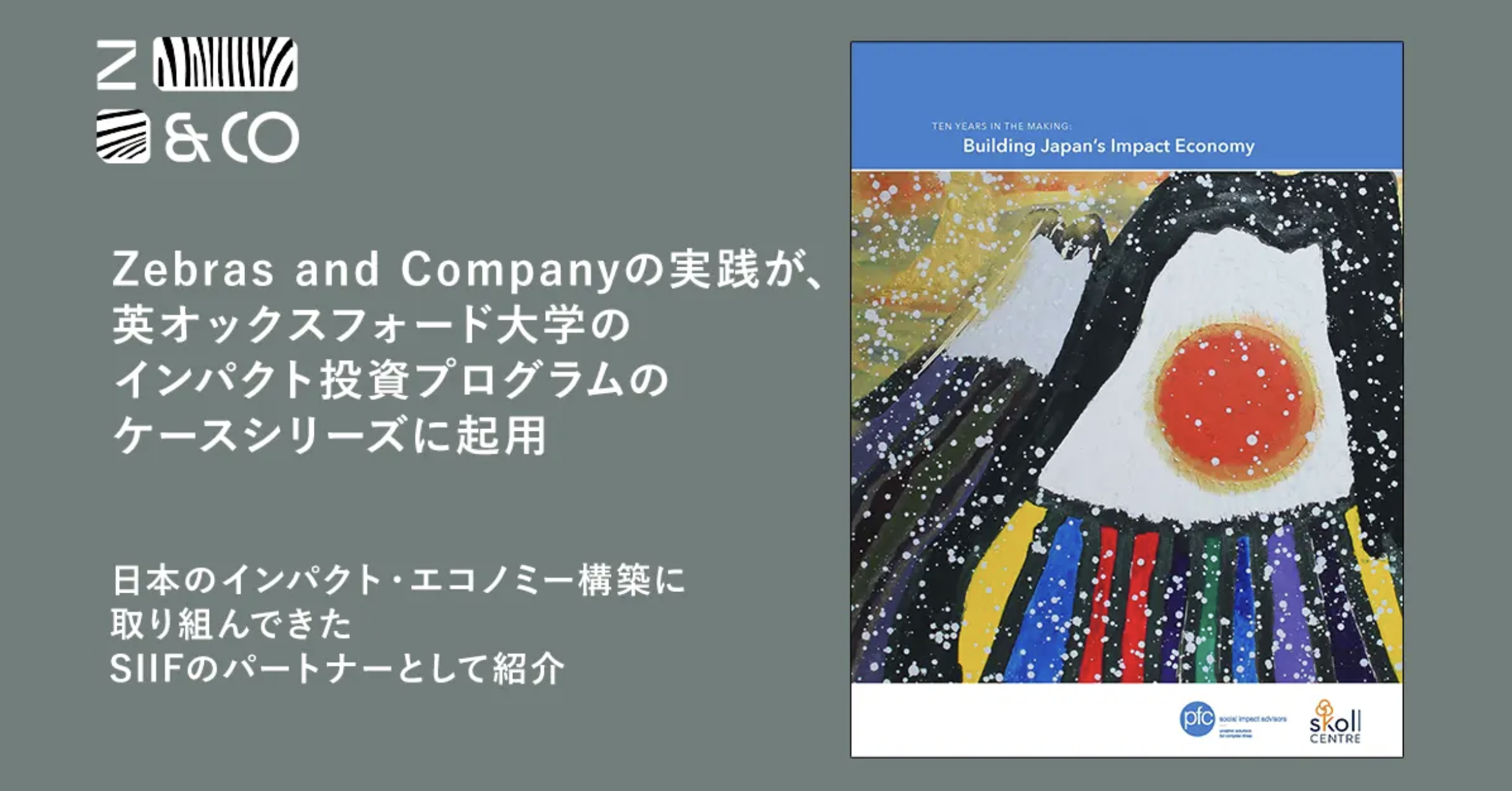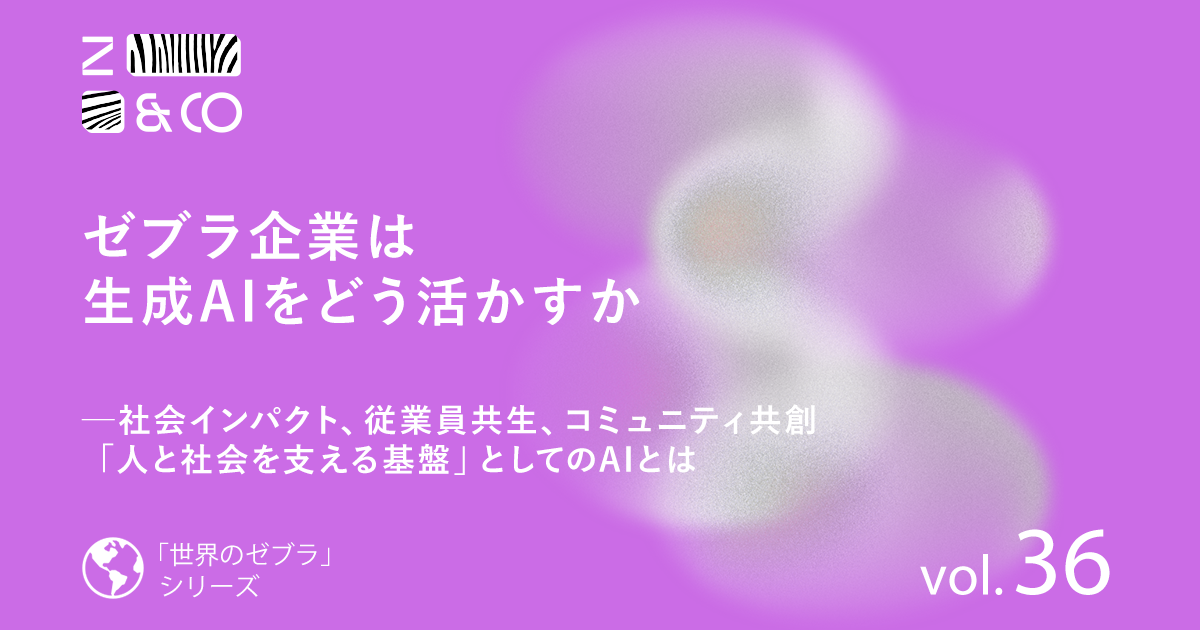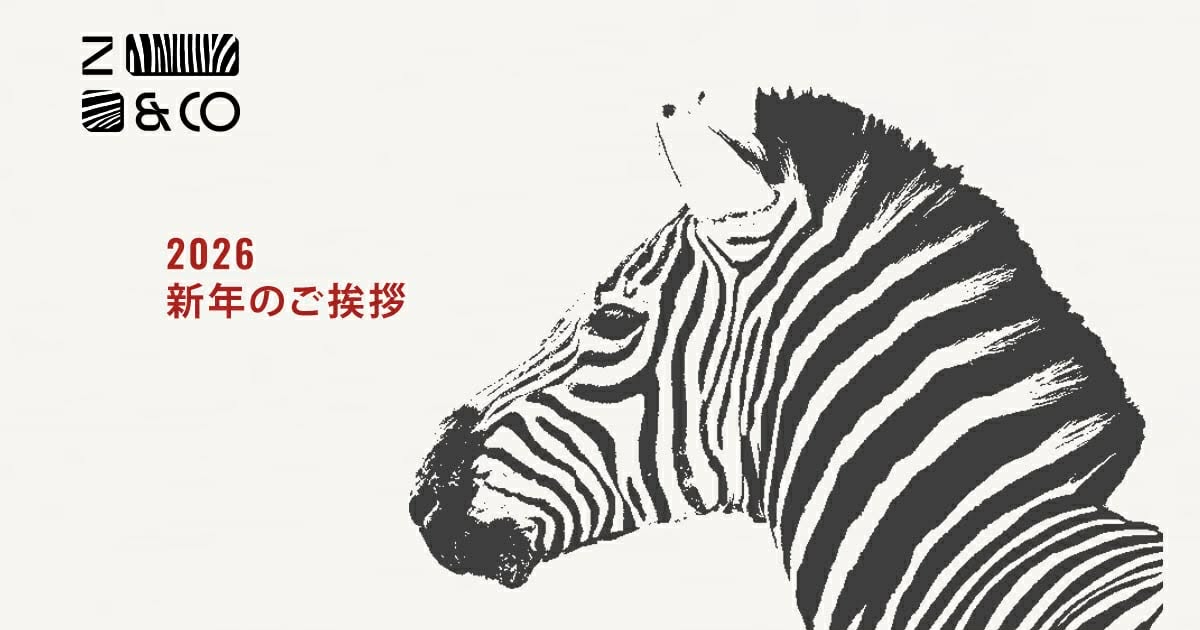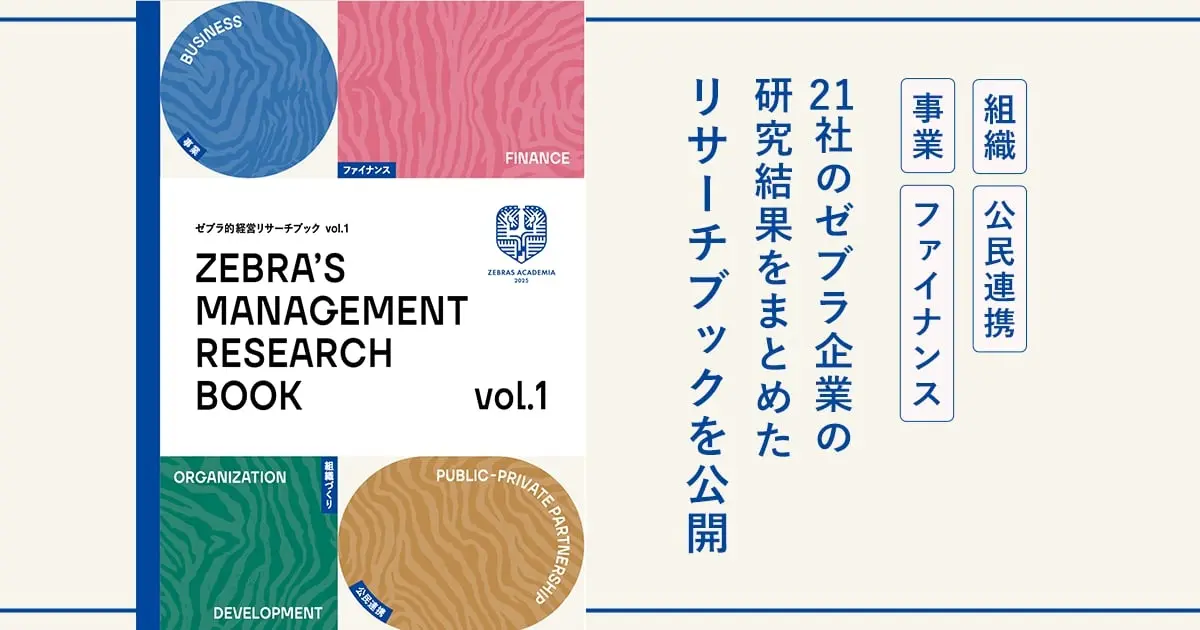2025.03.13 ZEBRAS
組織を超えてつながると「地域で働く」はもっと面白い。コミュニティ型伴走プログラム『Work Cross』に込めた思い

ゼブラアンドカンパニーは「働く環境の総合商社」ウエダ本社とともに、京都の地域企業のミドルマネジャー層に向けたコミュニティ型伴走プログラム『Work Cross』を新たに立ち上げることをこのほど発表しました。
『Work Cross』とはどのようなもので、立ち上げの背景には地域企業、中小企業のどのような課題があるのか。運営責任者であるウエダ本社の森島啓太さんに、一緒にプロジェクトを実行するゼブラアンドカンパニー阿座上さんが聞きました。

森島啓太
京都市出身。新卒で上場企業の経営企画に5年間従事。そこでの経験や葛藤を経て、「働くとは何か?」という問いを持つようになり、ビジネスの現場で実践しながら探究できる環境を求め、ウエダ本社へ転職。現在は、新サービスやプロジェクトの企画推進、採用など幅広い業務を担当。
自律的に働ける環境を求めてウエダ本社へ
阿座上:本日はウエダ本社として『Work Cross』になぜ取り組むのか、背景にどのような課題意識があるのか、どういう世界観を目指しているのかといったことを運営責任者である森島さんの口から語っていただきたいと思っています。まずは森島さんご自身について伺いたいのですが、どういう経緯でウエダ本社に?
森島:新卒では兵庫県の上場企業に入社しました。そこで5年間働いたのですが、社会人として実際に働き出したことで「どう働くか」という問いに自分ごととして向き合うことになりまして。もっと規模の小さい会社の方が裁量も多いし、手触り感を感じながら働けるのではないか。そういう観点で改めて会社を探し始めて、出会ったのがウエダ本社でした。惹かれたのは求人の内容というより、会社の考え方や理念といったところ。地元京都の会社ということにも縁を感じて、7年前に入社し、現在に至るという感じです。
阿座上:「働き方に興味を持った」という部分をもう少し詳しく聞いてもいいですか? 『Work Cross』にもつながる部分だと思うので。
森島:働いていく中で徐々に「働くとはどういうことなのか」「どうしたらもっと楽しく、働きがいを持って働けるのか」と考える時間が増えていきました。新卒で配属されたのは経営企画の部署で、まったく現場を経験することのないまま、IR的なデスクワークを任されたので。「この仕事の意味って?」「自分は社会に対して本当に貢献できているんだろうか」という思いが募っていきました。大学の同期が他の会社で生き生きと働いている様子をSNSで見たりもして、比較して焦る部分もあったかもしれません。
阿座上:今の若い世代に話を聞くと、SNSで目に入る同級生の動きをすごく気にしているのを感じますね。働くことがなんなのかもまだ分からない段階だと、確かに揺さぶられてもおかしくない。ただ、そこでせっかく入った大手企業を離れてまで、働き方に関することをやろうとするのはすごいですよ。

森島:具体的に「これがしたい」というものがあったわけではないんですけどね。むしろ環境とか、どういう思いでやっている会社なのかということが自分にとっては重要でした。社長は常々「(社員が)30人いれば、それは30人の社長がいるのと同じこと」と発言していて。それくらいに社員に自律性を求める会社なんだな、と。そういう風土はいいな、面白そうだなと思ったことが大きかったです。
阿座上:入社後もいろいろと変遷はあると思うんですが、今は主にどんなお仕事を?
森島:部署ではないんですが、ここでも経営企画という肩書きで活動しています。やっていることとしては、新規事業を立ち上げたり会社として新しく何かに取り組んだりするときの、サポートだったり推進の動きがほとんどですね。
阿座上:同じ経営企画でも前職とは手触り感が違う?
森島:まったく違います。規模も違うし、内容としても。前職ではそれこそIR的なことを含めて、予算があり、中間期の報告があり、それをどう説明すればいいかみたいなことをやっていました。今はもっと幅広く、新しいことをどんどんやっていける環境です。その分しんどいこともありますが、それを引き受けた方が結果的に面白いことができるということを日々感じています。
自分たちの「いい会社」をともに模索する場
阿座上:『Work Cross』に参加する企業の中にも、ウエダ本社のそうした価値観や企業姿勢に共感している会社は多いのではないかと思っています。というわけで、昨年御社が立ち上げ、今年からは僕たちも一緒になって推進していく『Work Cross』がどのようなものなのか、紹介してもらってもいいですか?

森島:ひとことではなかなか言い表しにくいのですが、地域企業、中小企業で働く社員が集まり、その人たちが自律的に働き、会社をよくしていけるようなコミュニティを目指しています。みんなでいい会社を目指していく土壌を作る、というのが目指しているところ。そこに向けて場作りだったりコンテンツ作りだったりに取り組んでいきます。
阿座上:各企業からミドルマネジャークラスの人3、4人に参加してもらい、ともに学ぶことによって、京都の中堅企業のコミュニティができていく、というイメージですかね。
森島:
そうですね。この時代、地域企業、中小企業とすると、人手不足は所与のものとして考えなくてはいけないと思うんです。ウエダ本社も30人くらいの会社なので、これは自分ごとの問題でもあります。1社で完結して考えるのでは、いろいろなところで絶対に限界が来る。だからこそのコミュニティということです。我々は事業のサポートというより、ずっと人や組織のことをやってきました。人や組織のところは、異なる会社間でも共通する部分が多く、一緒にやることの意味やメリット、目的を作りやすい。ということで、人作りや組織作りにフォーカスした地域企業の集まりをやりたいと考え、立ち上げたのが『Work Cross』です。
阿座上:中小企業からすると、1社で採用から育成までをやるのは大変ですし、大企業のようにノウハウを共有できるわけでもない。地域でやるというのは合理的ですし、一緒に地域を盛り上げていこうという雰囲気も作りやすい、いい取り組みだと思いました。1期目となる昨年は、どんな会社が参加し、どのようなことを行ったんでしょうか?
森島:昨年は5社に集まってもらいました。いずれも社員数50〜100人ほどの会社で、業種・業態はバラバラ。製造業もあれば商社も、エレベータの製造・メンテナンスの会社やゴミの中間処理の会社もあり、バラエティに富んでいました。
取り組んだことは大きく二つあります。
一つは、各社のミドル層、30〜40代の社員の方に集まってもらい、自分たちの会社を自分たちの手でどのようによくしていきたいかという理想を語ってもらうワークショップを開催しました。一方でこれまで積み上げてきたものもあるので、もちろん現在地にも目を向けてもらって。現在地から理想に近づけていくために、どのようなアクションをしていけばいいかを考えるところまでやってもらいました。
これが自社に関して「深める」取り組みだとすれば、もう一つは「広げる」取り組みです。ウエダ本社はありがたいことに「京都流議定書」などの取り組みを通じてさまざまなパートナーとのお付き合いがあります。そういう中小企業1社では決して出会えない人にゲストとして来てもらい、対話することを通じて、働くことに関する新たな視点や気づきを得るという試みも行いました。
阿座上:いいですね。最終的にどんな結果につながったかまではまだわからないと思いますが、「自分たちで会社を変えていけるんだ」という自己効力感なども含め、いろいろなものを得られたのではないかと想像します。経営者からの評判はどうでしたか?
森島:内容もさることながら、マインドセットの部分を喜んでもらえましたね。「指示通り動けなどといったことは一切ないのだけれど、自然とそういう雰囲気になってしまうところに課題がある」とおっしゃる経営者は思いの外多くて。そのマインドセットが変わる兆しが見えたのが良かったと言ってもらえました。また、参加メンバー同士は普段別の部署にいるので、仕事ではなかなか接点がない。会社を主語にしてがっつりと喋る機会を得ることで、メンバー間の絆が深まったのが、私から見ていてもよく分かりました。そこも喜んでもらえたポイントでしたね。

阿座上:参加企業同士の横のつながりが生まれることにも意味があるんじゃないかと思うのですが、その点はどうでしたか?
森島:「他の会社の人はこんなにも頑張っているんだから」という刺激にもなったでしょうし、その逆に「こういう悩みを抱えているのは自分たちだけではないんだ」という安心にもなっていたと思います。あと、これは狙って起こせることではないですが、ここで出会った企業を「いい会社だから」と知り合いに紹介し、転職が成立したということもあったようです。
阿座上:それはすごい!ホームページや会社概要で社長が語っているのは「表の言葉」であって、本当にその会社がどういう会社なのかが分かるのは、社員がどういう風に働いていて、自分の会社をどう思っているのかだと思うんですけど、そこがいい感じにシェアされる場になっていたということなんでしょう。
地盤はありつつ余白がある、地域企業の面白さ
阿座上:では、2期目となる今年はどんなことをしたいと考えていますか?
森島:大きくは変わらないですが、ゼブラさんとご一緒することで深める動きをブラッシュアップしていきたいと考えています。昨年の取り組みは社内のことを考えることが中心になっていました。それはそれでいいのですが、「社会における自社の存在意義」「社会に対してどういうインパクトを与えているのか」といった、外とのつながりの視点をもうちょっと入れていきたい。内向きで、自分たちだけでいい会社を目指すというのはちょっと違うのかな、と。「世の中がこうだから、こういう会社に」という視点はやっぱり必要。そこをボリュームアップしてやりたいというのが2期目になります。
阿座上:一緒に企画させてもらっている立場として僕が伝えたいのは「経営者はみんな孤独」だということです。なぜかといえば、経営の数字的な部分、全体感を分かっているのは経営者一人しかいないから。PLやバランスシートのようなものには「どんな経営をしていきたいか」が数字として表れているわけですが、一般の社員はそこまで見ないし、理解が及ばない。でも、現在地としてそこを知った上で「どんな未来を紡ぎたいのか」と考えることには意味があるのではないでしょうか。そうすると社長と社員の関係ではなく、同じ前を向いた仲間になれるのではないかと。そういう思いがあって、今回のプログラムを一緒に作らせてもらっています。
森島:ありがたいです。

阿座上:テストプロセスとして3回くらいセッションをやってみて、森島さん自身はどう感じましたか?
森島:全6セッションの中の2回目が「3年分の財務指標から現在地を知ろう」というものだったんですが、これが非常に面白かったです。ウエダ本社は数字的なものが開示されている環境にありますし、社員が自律的に動くことも比較的できている会社だとは思うんですが。それでも日常的に経営の数字をもとに喋るというところまではできていませんでした。
実際に取り組んでみると、まず、同じものを見ても違う切り口・視点で見るといろいろなことが浮かび上がってくるのが面白いですし、深掘りすればするほど語れることが出てきて、終わりがない。いつもとは違う脳を使っている感覚というか、会社の見え方まで変わってくる実感がありました。
阿座上:そのようなプログラムを展開する今年、どんな会社に来てほしいと考えていますか?
森島:これまでは価値観レベルで共感してくれる会社さんとお付き合いさせてもらってきました。それは非常にありがたいことでしたが、今回に関しては、より具体的なプログラムやメリットを通して仲間になれるというところもある。今まではなかなか出会えなかった企業にも入ってもらえたらいいですね。
阿座上:事業としてもある程度いい状況だし、会社の中の雰囲気もいいのだけれど、もう一段ステージアップしたいというときなどにうまく使ってもらえるといいですよね。
森島:そうですね。現状の延長線上ではなく、新しいインパクトを起こすことに取り組みたいという企業だと、このプログラムはもちろんですが、今後もいろいろなことでご一緒できそうです。そういう視点を持っている企業とはぜひ仲良くさせてもらいたいです。
阿座上:地域は人口減少で働き手が少なくなる課題が大きいと言われる中で、自分たちだけ儲かればいいというのでは、地域としても産業としても難しくなってきています。自分たちがある程度いい状態なのであれば、周りの人たちも含めた成長を考えていくことが大事になるのではないかと。そういう企業であれば、ここでの学びを通じて社内の人の成長速度も上がるでしょうし、横のつながりで新しい事業やインパクトも生み出せるかもしれない。
森島:そう思います。学びのプログラム自体はたくさんある中、そういう価値観で集まれるというのが我々がやっていることの特徴ですし、我々がやる意義だと思います。決して門を狭めるわけではないですが、その思いを共通してやれると、濃い関係性、いいつながりが生まれると思っています。
阿座上:では最後にその思いの部分、『Work Cross』を通じて作りたい未来をお願いします。
森島:今は大企業の初任給が上がっていることもあり、若者と話していても「大企業に行くか、それとも成長を求めてベンチャーに行くか」という選択肢になってきているのを感じます。その中で、地域企業、中小企業という選択肢はどのようにして成り立つのだろうかと考えたときに、ある程度の地盤はありつつも、そこに変化を起こしていける、チャレンジできる余白がある、そういう環境は他にはあまりないのではないかと思っているんです。
経営者だけでなく、働く個人にもそういうことを面白がれる人が増えるといいなと思います。そうすると経営者同士だけでなく、社員同士もつながっていって、もっといろいろなことを起こしていけるのではないかと。ですから私たちとしては「会社は違うが、働く人同士の顔が見える」という関係性を作っていきたい。『Work Cross』をそういう場所にしていきたいと思っています。

プロジェクトにご興味のある方はこちらをご覧ください。
Work Cross紹介ページへ
https://www.ueda-h.co.jp/news/12112/

PROFILE
ゼブラ編集部
「ゼブラ経営の体系化」を目指し、国内外、様々なセクターに関する情報を、一緒に考えやすい形に編集し、発信します。