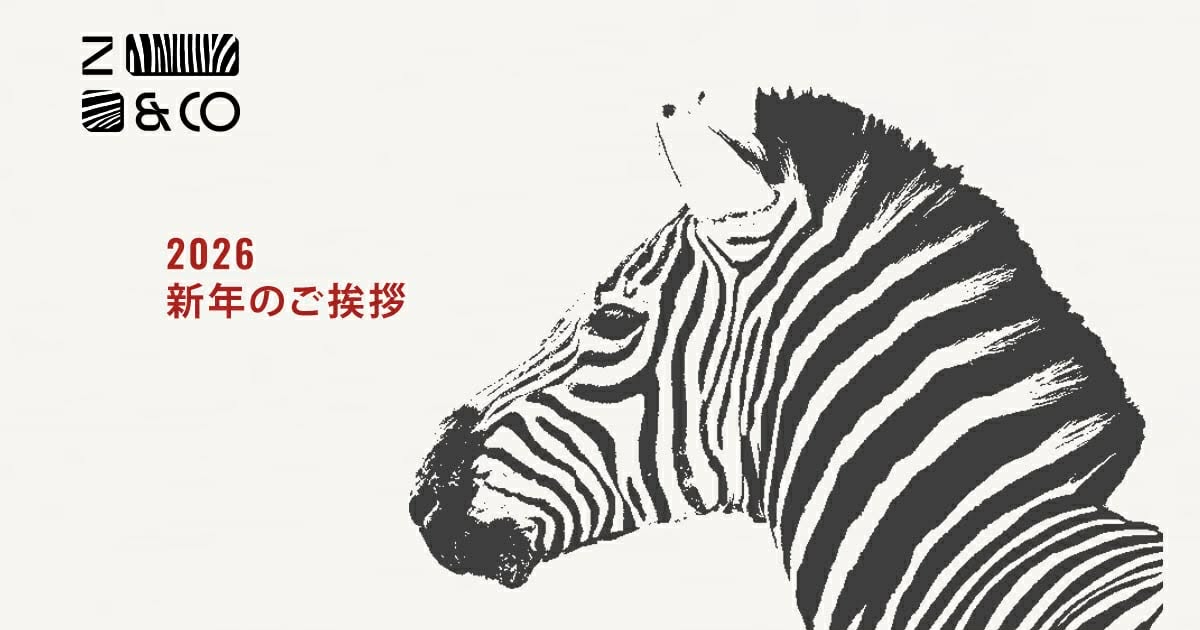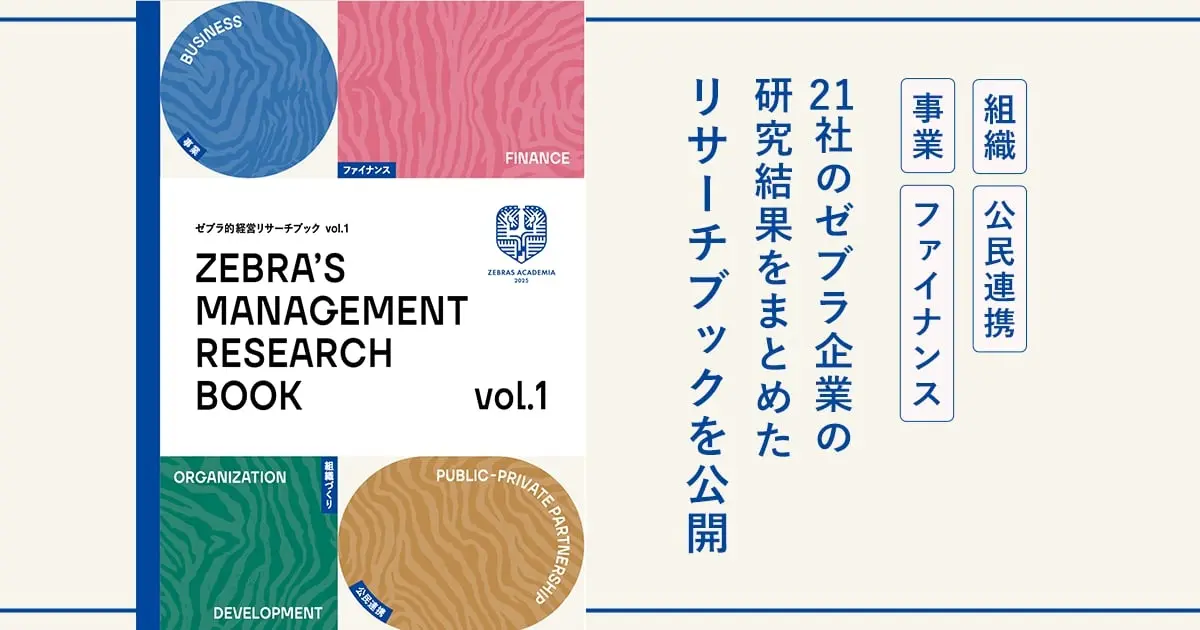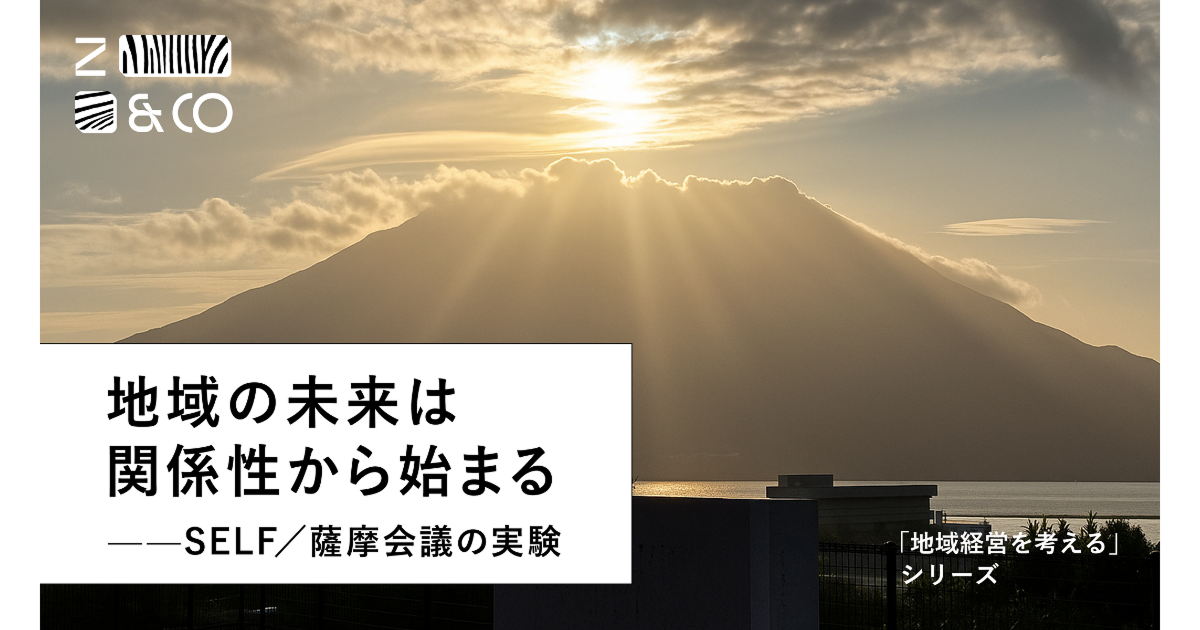2025.03.21 ZEBRAS
リジェネラティブ・カンパニーとして事業を可視化したグリーン・ワイズ。自然と文化を再生する0次産業の全貌を聞く

暮らしを支える「一次産業」。その土台となる自然や生態系自体が失われつつあります。日本では近年、こうした自然や生態系のリジェネレーション(再生)自体を産業とする『0次産業』という概念や取り組みが、同時多発的に見られるようになりました。そこで、Zebras and Company(以下、Z&C)では、0次産業の現在地を探る連載をスタートします。
第2弾で取材するのは、明治から続く植栽の会社、株式会社グリーン・ワイズです。「環境共生社会の実現」を掲げ、コンサルから環境認証取得支援、デザイン、施工、緑地管理、緑地活用プログラム循環までのサービスを提供しています。NHKテレビ草創期1961年の以来、スタジオでの植物設置や映像緑化なども担っています。
また、同社のプロジェクトのひとつである調布の深大寺ガーデンには、リジェネラティブレストラン「Maruta」を展開。地域のオーガニックな食材や、季節の植物を取り入れた料理と共に「自然との共生」を感じられる体験を提供しています。「Maruta」は、WIRED主催の“都市の未来を再生する次世代カンパニー”を表彰する「THE REGENERATIVE COMPANY AWARD 2024」を受賞しました。
グリーン・ワイズが最近、環境共生という理念に共感する仲間を増やすためにビジョンを可視化しました。その際に参考にしたのが、Z&CとWIREDで共同制作した、企業の“リジェネラティブシフト”の過程を記した「リジェネラティブ・カンパニー・プロセス」です。
そこで、多摩市にあるグリーン・ワイズ本社に伺い、功刀優子さん(サムネイル右)とコミュニティグリーン事業部の宮下明穂さん(サムネイル左)から、可視化したビジョンから見える未来について聞きました。聞き手は、Z&C共同創業者の阿座上陽平さんです。
※記事冒頭は、取材前に行った「オフィスツアー」の様子をお届けします。
自然と共生するグリーン・ワイズのオフィス
オフィスツアーの冒頭、功刀さんが紹介してくれたのは六角形のマークがあしらわれた盆栽鉢でした。この鉢は、120年以上の歴史を持つグリーン・ワイズ(当時は株式会社東光園)が、創業時から行う貸植木のサービスで用いられていたもの。グリーン・ワイズで50年以上働く社員が「入社した時にはすでにあった」というほどの歴史があります。
オフィスの周りをぐるりと歩くと、グリーン・ワイズの敷地内にある様々な植物が目に飛び込んできました。日本でここにしかない植物もあるといいます。国際会議で展示された大きな盆栽や、NHKのドラマで使用された桜の枝など、グリーン・ワイズの植物は、文化的・歴史的に象徴となるような数々の場面を彩ってきたのです。
「植物を貸し出して終わりではありません」と、功刀さんは言います。
「傷んだ植物は、温室で養生させ再生します。剪定した枝葉は分解して肥料にするなど、リジェネラティブな活用を行っています」(功刀さん)
その言葉通り、オフィスの敷地内には「バイオネスト」がありました。肥料の元となる草ごみなどを山のように積み重ねることで内部の温度が高まり、分解発酵が進んで堆肥になります。グリーン・ワイズさんは、それを庭園の植物を育てることなどに活用。自社で植物との共生のあり方、循環のさせ方を研究してお客様に提案します。
次に訪れたのは、2Fの執務スペースに併設された屋上庭園。ここには、100種類以上の植物が植えられています。季節の移ろいとともに、青々と茂る緑の姿から、枯れゆく風情ある趣まで、さまざまな表情を楽しめます。
お客様も招待し、環境共生を体験する場として、スプリングカットバック(刈り込み)を行ったばかりだそうです。屋上は交流を深める場であり、四季の移ろいや庭の楽しみ方を知ってもらう場にもなっています。
「庭園や植栽は、人の行動を変える“仕掛け”になります。例えば、オフィスビルに屋上庭園があることで、社員同士の自然な交流が生まれます。自然を活かして人の行動変容につなげることが、私たちの生業です」(功刀さん)
最後に訪れたのは3階の屋上庭園でした。グリーン・ワイズの庭園にはさまざまな測定機器が設置されています。緑化された土壌の水分量の変化や、CO2の吸収量、ヒートアイランド現象や寒暖の緩和効果の程度などを計測し、グリーンの価値を定量化しています。
「植物のスケッチもしています」と功刀さん。専門の担当者が、植物のライフサイクルを伝える手段として、植物の枝や茎一本に集中して定期的にスケッチしているといいます。
グリーン・ワイズは、このように定量・定性の両面から「植物の生態や価値」を可視化し、お客様への提供価値へとつなげています。植物のライフサイクルを見つめ、その知見を事業へと昇華させていく——そんな会社のあり方を体感できたオフィスツアーでした。
※ここからはグリーン・ワイズの功刀さん、宮下さんと、Z&Cの阿座上さんの対談をお届けします。
自然の叡智を活かして「環境共生社会」を実現する
阿座上さん:
素敵なオフィスを紹介いただきありがとうございました。ここからは、改めてグリーン・ワイズさんの事業について伺っていきたいと思います。
今回の取材のきっかけは、Z&CとWIREDで制作した「リジェネラティブ・カンパニー・プロセス」のワークを活用して、環境共生という会社の理念に基づく事業を可視化されたことです。その背景や、そこで整理された事業の全体像について教えていただけますか?
詳細はこちら WIRED VOL.49 THE REGENERATIVE COMPANY 未来をつくる会社
功刀さん:
グリーンワイズは、自然と人をつなぎ環境共生社会を実現するために、緑を軸とした様々な事業を展開しています。
今回、事業全体を通じて、人・社会・地球に対してどのような影響を生み出しているのか、そして生み出していきたいのかを整理するため、「リジェネラティブ・カンパニー・プロセス」を使わせていただきました。まずは、4ステップを経て作成した「システム図」を見ていただきながら、全体像を説明できればと思います。
功刀さん:
図の中心の3つの円で表現しているように、グリーン・ワイズは、地球から「自然の叡智」を受けとり、「環境共生のノウハウ」を活かして「楽しい体験の場」をつくっています。
例えば、商業施設の屋上に、楽しい体験ができる屋上庭園をデザインすることで、人々が自然と足を運びたくなる空間を生み出します。さらに、その場所で自然を体験できるイベントなどを開催し、訪れた人に楽しい時間を提供。その結果、施設の集客が増えたり、環境への取り組みが評価されて商業施設を運営するディベロッパーが投資を受けやすくなったりするなど、ディベロッパーの社会的な評価につながります。
一方、その庭園を訪れた人は、「楽しい体験」を通じて自然の大切さや環境共生の魅力を実感し、自然への意識や行動が変わっていく。そうした人が増えることで、環境共生の考えを取り入れた場所や仲間が広がる。最終的には、叡智を与えてくれた自然そのものに恩返しができる、という循環をつくっています。
自然と文化を再生するグリーン・ワイズの0次産業
阿座上さん:
一番外側の「恩恵・感謝」は、何を表しているんですか?
功刀さん:
阿座上さんから0次産業の話を聞いて、「私たちにとって、0次産業とはどういうことか」を考えて言語化したのが、このループです。
自然からの「恩恵」を受けて、「感謝」で還元することによって、自然の営みをさらに豊かにしていく。そのおかげで、人間が受けられる恩恵は大きくなり、経済的なインパクトも大きくなっていくということを示しています。
阿座上さん:
0次産業を成り立たせる上で悩ましいのは、自然資本を再生することで人に恩恵がある一方、自然資本への還元をどうデザインするかということだと思っています。その点、グリーン・ワイズさんは、「感謝(をもとにした人の行動変容)」によって循環をさせている。人の意識や行動が変わることによって、自然資本が増えていくように設計しているのが素敵です。
功刀さん:
ありがとうございます。もうひとつ、私たちなりに0次産業について考えたことがあります。それは、自然や文化資本そのものも0次産業と呼べるのではないかということ。
そもそも、農業などが一次産業となったのは、産業革命以降。大量生産や経済成長の要求に答えて産業化していきました。それなら、それ以前から行われていたもの、例えば経済のための営みではない文化や慣習、行事なども、0次産業にあたるのではないかと思います。
阿座上さん:
たしかに、産業や人の暮らしの土台である文化資本の再生も0次産業の範囲に入ると思います。
功刀さん:
そうですね。実は、グリーン・ワイズがやっていることは、文化資本の再生にも当てはまると思います。私たちはお客様の場をつくる時、気候や土壌などを調べるとともに、その地域の歴史や文化、慣習なども深掘りします。
例えば、横浜の商業施設「マークイズみなとみらい」の屋上に設計した果樹園・菜園「みんなの庭」。ここでは、横浜で昔から育種されている柑橘をはじめとした果樹などを植え、それらを使って楽しむワークショップを年間100回以上開催しています。
すると、その文化をよく知る地元の人たちは、施設への愛着を持てるようになり 、外からくる人は、その場にしかない体験ができるようになります。体験して価値を感じる人が増えれば、その文化を未来に残していくことにもつながっていくはずです。
考えを押しつけず「楽しい体験」を通じて自然と広げる
阿座上さん:
グリーン・ワイズさんは、もともと貸し植木の事業からスタートしています。どのような経緯で「土地の歴史や文化」まで捉えた造園事業などを手がけるようになったんですか?
宮下さん:
この会社はもともと貸し植木からスタートし、その後、屋上庭園や屋内外の緑化事業へと展開していきました。事業を進めるなかで、単に緑を増やすだけでなく、「緑と人との関わり」にも目を向けるようになったんです。
さらに深く考えていくうちに、「その土地ごとの植物の特性」や「そこに住む人々との関係性」、さらには「昆虫など他の生き物との共生」にも関心が広がり、自然全体のつながりを意識するようになりました。
グリーンをビジネスとして活用するだけではなく、その先にあるものを突き詰めていった結果が、現在の事業になっています。
キャプション:グリーン・ワイズ 宮下さん
阿座上さん:
突き詰めていった結果、より広いステークホルダーのことまで考えるようになっていったんですね。オフィスツアーでは「社内で試したことをお客様に提案することもある」という話がありましたが、それも事業展開に影響しているのでしょうか?
宮下さん:
そうですね。例えば、社員が興味を持って学んだことを社内で共有し、発展して事業につながることもあります。興味や「楽しい」と思う気持ちがきっかけになり、新しい展開が次々と生まれる環境です。
功刀さん:
送別会や歓迎会などの社内イベントひとつをとっても、社員それぞれの個性が表れる場になっています。植物の切り株や根っこを使って空間を装飾した会があったり、趣味の蕎麦打ちを体験する会があったりと、社員が自分なりに「プロトタイプ」します。
社員一人ひとりの興味や意思を大切にしているからこそ、グリーン・ワイズの経営方針も「みんなで考え、みんなで決め、みんなで実現する」スタイルをとっています。今日の午前中には全社会議がありましたが、経営陣から方針を伝えるのではなく、「環境共生社会を実現するために何ができるか」を全員で話し合いました。
阿座上さん:
みなさん、自分の興味に従い、楽しみながら働いているんですね。
功刀さん:
たしかに、「楽しい」ということは、すごく大事にしています。「環境共生は大事だ」と真正面から伝えてもなかなか伝わらないですからね。まずは社員が楽しみ、お客様やその先の人たちに対しても植物を活かした「楽しい体験」を届ける。
それによって、「またこの体験がしたい、環境をもっと良くしたい」と思ってくださる仲間が増えたら、環境共生の輪が自然と広がっていくと考えています。
理想的なシステムの起点となる「社内評価制度」の大切さ
阿座上さん:
仲間を増やすことを重視されているんですね。
功刀さん:
一社でできることには限りがあるので。環境共生社会を実現するためには、領域外の人たちや、他社さんとのパートナーシップが不可欠だと思います。植物が他の植物や昆虫たちと共生しているように、「自然の叡智」から学ぶ私たちも、人や組織だけではなく、植物や昆虫たちと共生するような関係性、自然のメタファーを大切にしているんです。
阿座上さん:
自然のメタファーが、組織のあり方や日常の振る舞いに落とし込まれている。
功刀さん:
そうですね。「人間も自然の一部だ」という視点を大切にしてきました。
阿座上さん:
仲間づくりの話につながると思うのですが、「リジェネラティブ・カンパニー・プロセス」のステップ2では、ステークホルダーとの関係性を可視化しますよね。どのように整理しましたか?
功刀さん:
ステップ2で、ステークホルダーに対するインパクトを可視化したものをもとに、「仲間を作るためのオープンシステム」としてアウトプットしました。
功刀さん:
現時点のものですが、この図は、グリーン・ワイズの会社や社員を中心に広がっていくコミュニティを表現しています。お客様や取引先など環境共生社会を実現する仲間の「コアコミュニティ」、その周りのリジェネラティブに関心のある人たちの「リジェネラティブコミュニティ」。そして、さらに広いコミュニティが広がっています。中心に近づくにつれて、環境共生への興味度や共感度が高まっていくイメージです。
こうしたコミュニティの広がりを捉えた上で、私たちの事業や取り組みがどこに作用しているのかを整理しました。例えば、深大寺ガーデン「Maruta」は、「リジェネラティブコミュニティ」と「コアコミュニティ」をつなぐ場所。ここで環境共生の事例を体験してもらい、仲間に一歩近づいてもらいたいと考えています。
他にも様々な事業や取り組みを通して、限られた範囲ではなく、できる限りオープンに仲間を増やしていけるようにしたいと思います。
阿座上さん:
中心に「社内評価制度」と記載されているのが興味深いです。
功刀さん:
「社員の何を評価するか」ということは、会社のあり方や生み出すインパクトにとって、とても大事な要素だと思います。「みんなで考えて、みんなで実現する」会社として、みんなで評価制度のあり方も追求していきたいと思っています。
阿座上さん:
最後にそのお話が聞けてよかったです。どんなに理想のシステムを構想したとしても、それが実際に社員のみなさんの行動につながらなければ、理想論で終わってしまう。「自分たちの何をどう評価するのか」というところを起点に、システムを成り立たせようとしているのが、本質的な部分を捉えられているなと勉強になりました。また別の機会に、社内制度について詳しく聞かせていただきたいです。
功刀さん:
ぜひ、お話させてください。色々な角度からグリーン・ワイズのことを深掘りしてくださり、本当にありがとうございます。今日のお話が、リジェネラティブカンパニーやゼブラ企業のみなさんにとって、少しでも参考になってくれたら嬉しいです。

PROFILE
Fumiaki Sato
編集者・ライター・ファシリテーター。「人と組織の変容」を専門領域として、インタビューの企画・執筆・編集、オウンドメディアの立ち上げ、社内報の作成、ワークショップの開催を行う。趣味はキャンプとサウナとお笑い。