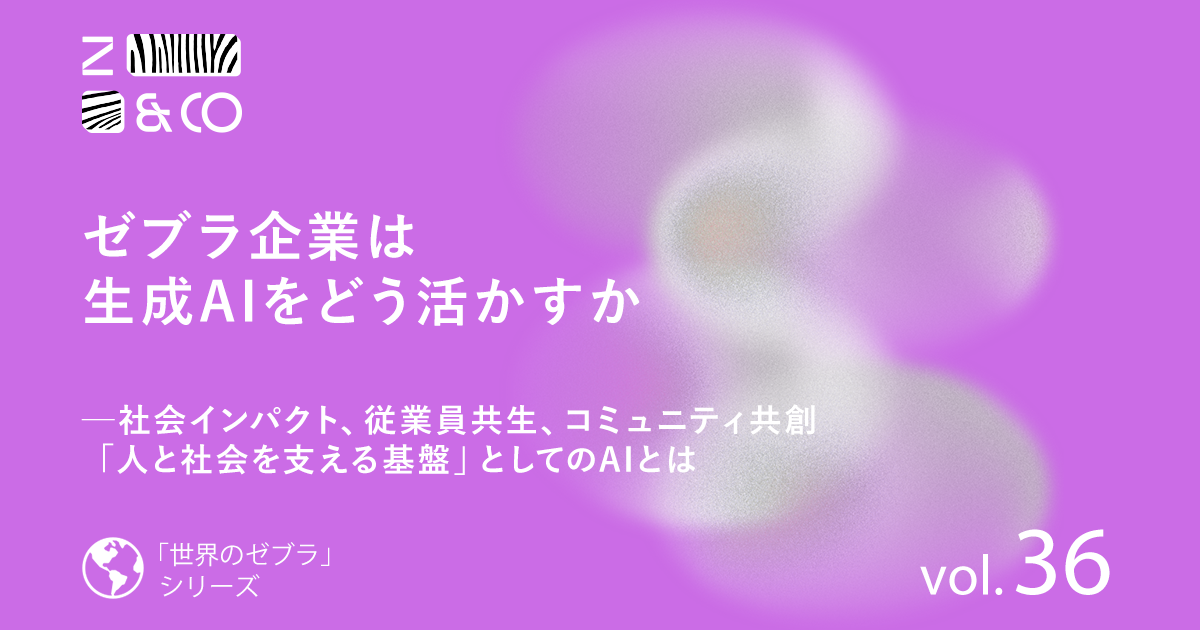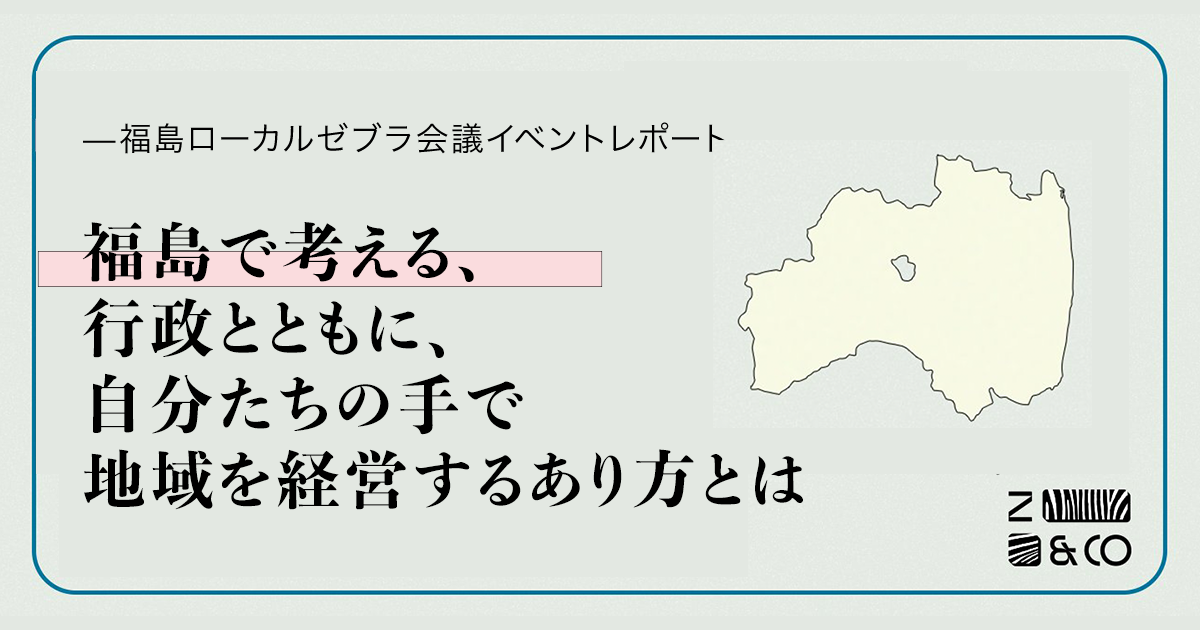2021.08.17 ZEBRAS
ダウン症のスタッフが運営するオランダのカフェチェーン「Brownies & downieS」が躍進を続ける理由

大躍進中のカフェチェーン
オランダ旅行中、街の中心にあるこじゃれた普通のカフェに入ると、「いらっしゃいませ」と知的障がいのあるスタッフが数人であなたを出迎える。面食らうあなたをよそに、彼らは完璧な接客であなたをもてなし、オランダではちょっと珍しいレベルの(失礼)美味しい料理を出し、何事もなかったかのように会計を済ませ、「また来てね」と見送る。
こんなことがあなたの身にも起きるかもしれません。
11年前に小さなコンセプトカフェとしてオープンした「Brownies & downieS」は、現場も事務職も基本的にダウン症を中心とした知的・発達障害を持つスタッフを雇用する方針をつらぬきながら、今や九州ほどしか面積のない国で53店舗まで拡大。レシピ本のリリースやオンラインショップの開始など、躍進中のフランチャイズチェーンです(うち1店舗は国外)。
コロナ禍直前の2020年1月には、国内のチェーン店を対象とした、利用者の投票でランキングを決める「フードサービスアワード」で、ドミノピザなどの大手を差し置いて大賞を受賞しました。
オランダ国内はもちろん、日本でも「障がい者の働く飲食店」は今や特段目新しいことではありません。数年前にNHKのプロデューサーだった小国士朗氏が仕掛けて日本で話題になった、認知症を持つ店員さんがもてなす「注文を間違える料理店」を覚えている方もいるでしょう。
ただ、「注文を間違える料理店」が、おおらかな心を日本中に広めることを目的としたプロジェクトであったのに対し、「Brownies & downieS」はバリバリの「営利企業」。成功の秘訣は何なのでしょうか。創業者の見据える「一歩先を行く」インクルーシブな社会とはどんなものでしょう?

ターゲットグループは「従業員」
経緯はあとでお話ししますが、創業者のThijs Swinkels氏は「私の会社のターゲットグループは、お客さんではなく従業員だ」と明言しています。企業の意義を「職場」としてのカフェに振り切り、「知的に障がいのある人が、安心して仕事を学び、働いてまっとうな賃金を得る場の確保」をビジネスの第一義としています。
現在、1200人前後の従業員を雇用していますが、うち80%は何らかの発達障がいを持つスタッフ。現場のみならず本社の事務職にも知的障がいを持つ従業員が配置され、定型発達の(障がいを持たない)スタッフと全く同等の賃金を得ています(現在、21歳以上でフルタイムの最低賃金は時給9,82ユーロ≒1280円、オランダの労働法によりパートタイムでも各種社会保障あり)。
もちろんこの方針には当初疑問もあり、実際Swinkels氏は起業から数年後に、ホスピタリティと料理の質を追求したかったビジネスパートナーと袂を分かちました。
ただ、彼が「残念だったが、その後のビジネスの展開を見れば結果オーライだ」と語るように、「障がい者の職場でありつつも高品質の料理を提供する」というコンセプトは社会の支持を得て、企業は急成長を遂げています。
そもそも第一号店が大成功を収めても、彼の頭の中には「フランチャイズ展開」の意図は全くなかったといいます。その可能性を開いたのは、ハンデ以外の持てる能力を発揮し、独立した社会人として社会に貢献できる職場を熱望していた、障がい者本人たちとその保護者の説得でした。
3店舗目をオープンした時点でマニュアルと研修制度を整備し、正式に「フランチャイズ」の門戸を開くと、同じようにまっとうな職場を探していた各地の障がい者の家族や団体が手を挙げ、時にはクラウドファンディングなどで資金を調達して次々に支店をオープンし、全国的に知名度を上げていきました。
コロナ禍で度重なるロックダウンにより多くの飲食店が閉店を余儀なくされたここ一年も、従業員が職場の存続に全力を尽くしたため、閉店した支店はほぼありませんでした。
「従業員は家族」 収益を支える3つの柱は「スタッフ・品質・(多分)国民性」
Swinkels氏が「ビジネスのターゲットはスタッフ」と明言するには理由があります。
まだビジネスを立ち上げて間もないころ、あるスタッフのお父さんが亡くなったのですが、彼は真っ先にSwinkels氏に電話で伝え、葬儀に招いてくれました。このことが強烈な印象を残したと言い、それからずっと「大きな『家族』であるスタッフたちの真っすぐな貢献と、熱心で陽気な勤務態度、彼らの保護者からの多大な感謝」が経営者としての彼を焚きつけ、ビジネスを縁の下で支えていると語ります。

しかし、もちろんそれだけでは商売は成り立ちません。Swinkels氏ははっきりと「Bagels&Beans」(サステイナブルな方針でやはり鋭意展開中のカフェチェーン)と「他の障がい者が働く福祉系飲食店」をライバルとして挙げ、「そのどちらでもない(言い換えれば、それらのいいところどりの)」運営を心がけているといいます。
近年、実業家兼教育者として、講演でも大人気の彼があちこちで言っていることを大まかにまとめると、「福祉施設としての政府からの補助金を得てはいるが、それはカフェの収益にはカウントせず、全て従業員の教育と福利厚生に回す。それにより組織としての士気を維持し、お店ではこだわりのクオリティのフード・ドリンクとサービスを提供する」といったところ。
ポリシーに賛同したサプライヤーと密な提携関係を築け、上質な食材を確保できることも料理の質を支えていると言いますが、あくまで「運営をもらいものに頼らない」ポリシーを通しています。
そして、これは筆者の邪推ですが、人気の背景には社会貢献への意識が高く、合理的で一石二鳥が大好きなオランダ人の国民性もあるのかもしれません。「カフェでおいしいものを食べられて、同時に福祉のサポートもできる」という点。
しかし、単なる国民性の問題ではなく、「自分なりの正義にお金を落とす」ポリティカル・コンシューマリズムの台頭などの時代的な背景ももちろん影響しているでしょう。
「彼らはイメージよりはるかに多くのことができる」
そもそもこのユニークなビジネスはどのようにして始まったのでしょうか。
Swinkels氏は元々、飲食店でバイトをする体育教師志望の学生でした。しかし、インターン先がなかなか決まらず、「仕方なく」配置された特別支援学校で、生徒たちの真っすぐな愛着、熱心に学ぶ姿勢、そしてなにより「彼らは自分が勝手にイメージしていたよりもはるかに多くのことをできるし、学ぶこともできる」という事実に感銘を受けます。
そして、卒業後にバイト経験のあった飲食業界で、「彼らを含む誰もが安心して学び、働ける職場」を立ち上げました。
それまでの教育・社会システムの中で見過ごされてきた障がい者のポテンシャルに金鉱脈を見出したのか、それとも自分を感銘させた彼らに活躍の場を作ることに使命を見出したのかは推測するしかありません(多分両方でしょう)。
ただ、彼はそれから10年後の今も、「私はただの実業家以上のものになりたい」と常に語り、社員を「家族」と呼びます。
念願だった「アカデミー」の創立
そんなSwinkel氏は、長年「学校」の創設を夢見てきました。
知的障がい者に対するオランダの特別支援教育では、標準的に16歳でインターンを開始し、18歳で卒業しますが、彼はそれに「最も教育を必要とする人たちが、最も早く教育を終えるのはおかしい」と、かねてから苦言を呈していたのです。
2020年、コロナ禍でカフェ事業が一時停止を余儀なくされる一方、トレーニング施設としてのキッチン棟が本社隣に完成しました。
現在、生徒受け入れ準備が進められており、開校の暁にはバリスタ訓練や衛生トレーニングなど各種の単位を取得し、2~3年で「卒業証書」をもらえるアカデミーとして機能する予定です。営利企業でこの種の「学校」を創設した会社は国内初で、Swinkels氏は「他の企業がこれに続いてくれること」を願います。

「うちの会社で学び、働くうちに才能が開花し、転職していく従業員も多くいます。私はその踏み台になりたい。でも、やはり圧倒的に多い転職先は飲食業。今の社会では、例えばカーディーラーで車の説明をしてくれる販売員が知的障がい者だったら受け入れてもらえないから。でも、私はそういう世間のマインドセットを変えたい。彼らは実際、誰よりも豊富な車の知識を持ち得るのですから」
「理想的な社会であれば、障がい者は必要なだけ教育を受け、その後、通常の労働市場で自分にできる仕事を見つけられるはず。20年後に真のインクルーシブな社会が実現すれば、私の会社は社会から不要になるでしょう。それが夢です」
「誰をも受け入れる場所」
この「Brownies&downieS」、実は現在オランダで暮らす筆者の家の近所にも一軒支店があるのですが、わりとよくお世話になっています。
あるときは、レジに行ったらサッと英語のできる店員さんが対応してくれましたが、数的処理が苦手な人だったらしく、近くで接客以外の仕事をしていた同僚にお釣りをそろえてくれと頼んでいました。ある時は頼んでいない紅茶が来て、「頼んでいません」と言ったら、店長が来て「こういう場合は無料です」と笑いました。
ブラウニーやハイティーがおいしいのも魅力ですが、あちこちから「ミスはあるよね」「できることをそれぞれやればいいよね」といった、職場としてのおおらかな雰囲気が感じられて、いつも子連れの外国人である私も分け隔てなく接客してくれるのでありがたいです。カフェの方針のひとつにも「誰をも受け入れる雰囲気を提供すること」があります。確かにそれは、職場としてハンデのあるスタッフを排除していたら実現しないことかもしれません。いつも「インクルーシブ」とはこういうことかな、と考えながら、店をあとにします。
文:ウルセム幸子
編集:岡徳之(Livit)http://livit.media/

PROFILE
ウルセム幸子
3児の母、元学校勤務心理士。出産を機に幸福感の高い国民の作り方を探るため、夫の故郷オランダに移住。現在執筆、翻訳、日本語教育など言語系オールラウンダーとして奔走中。