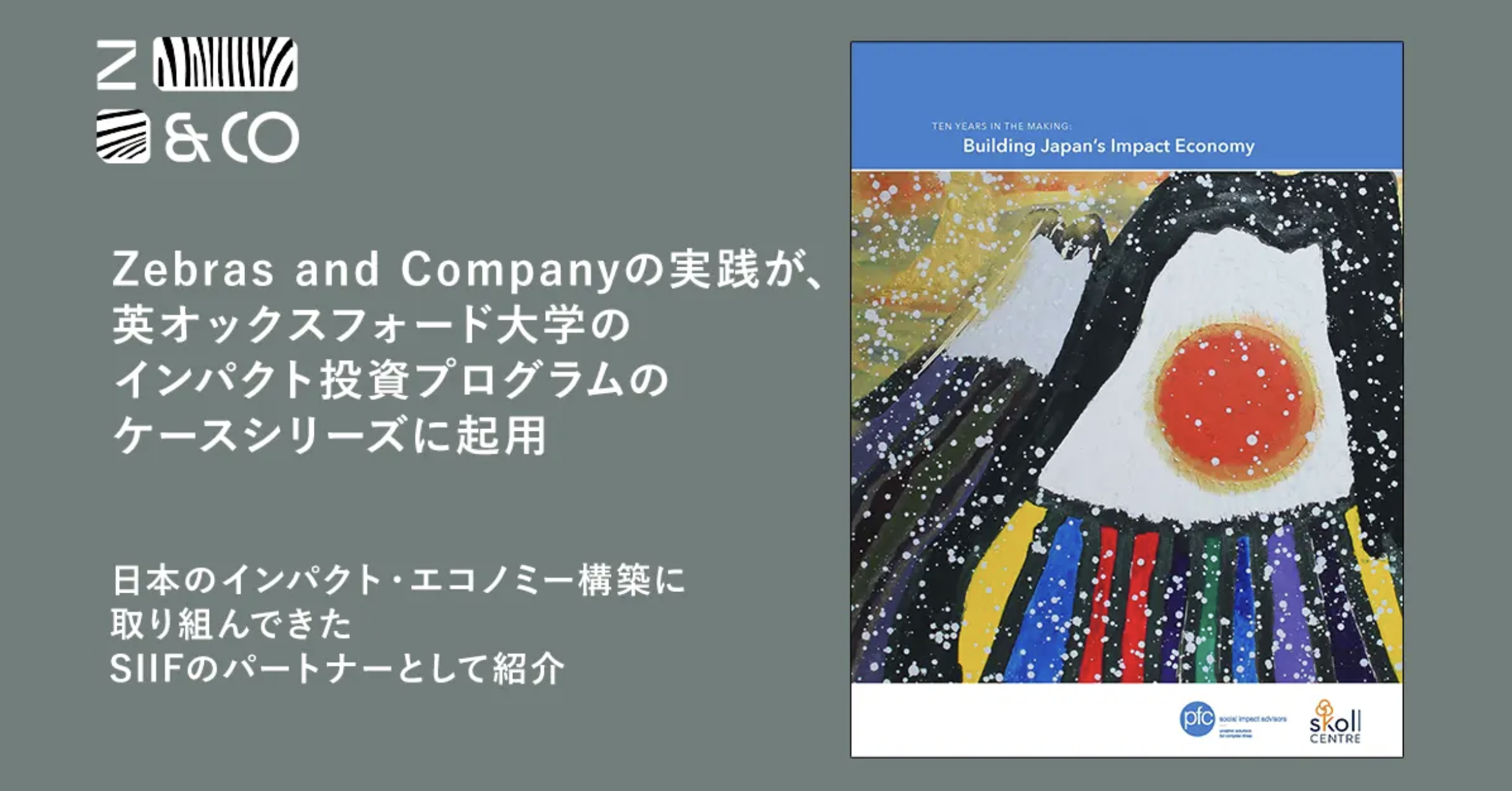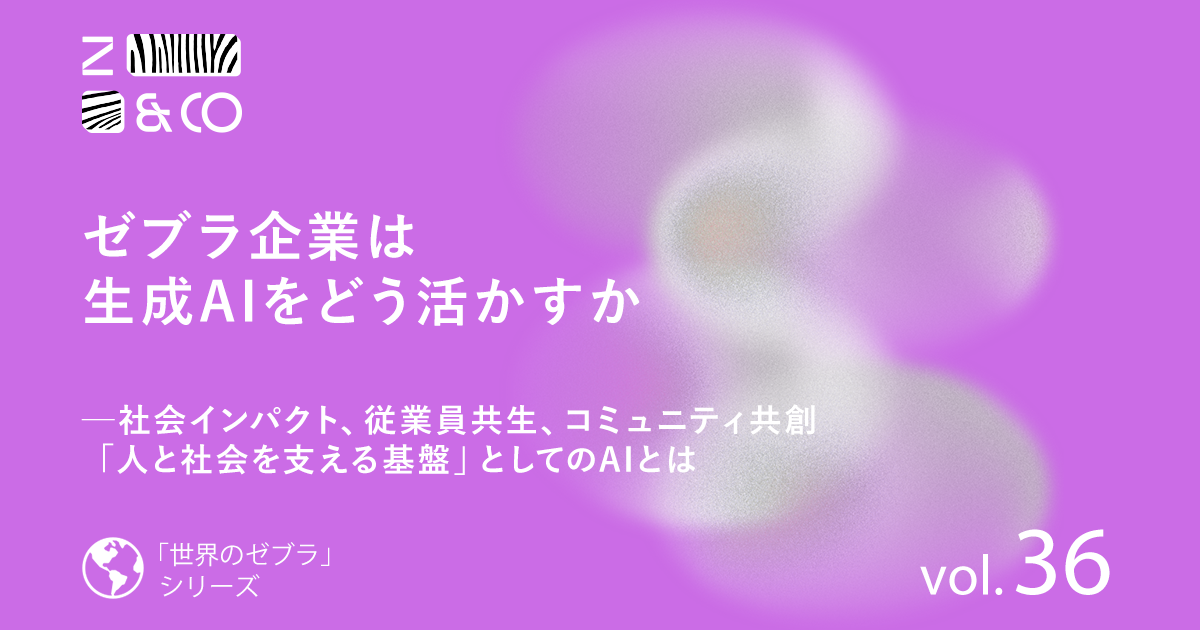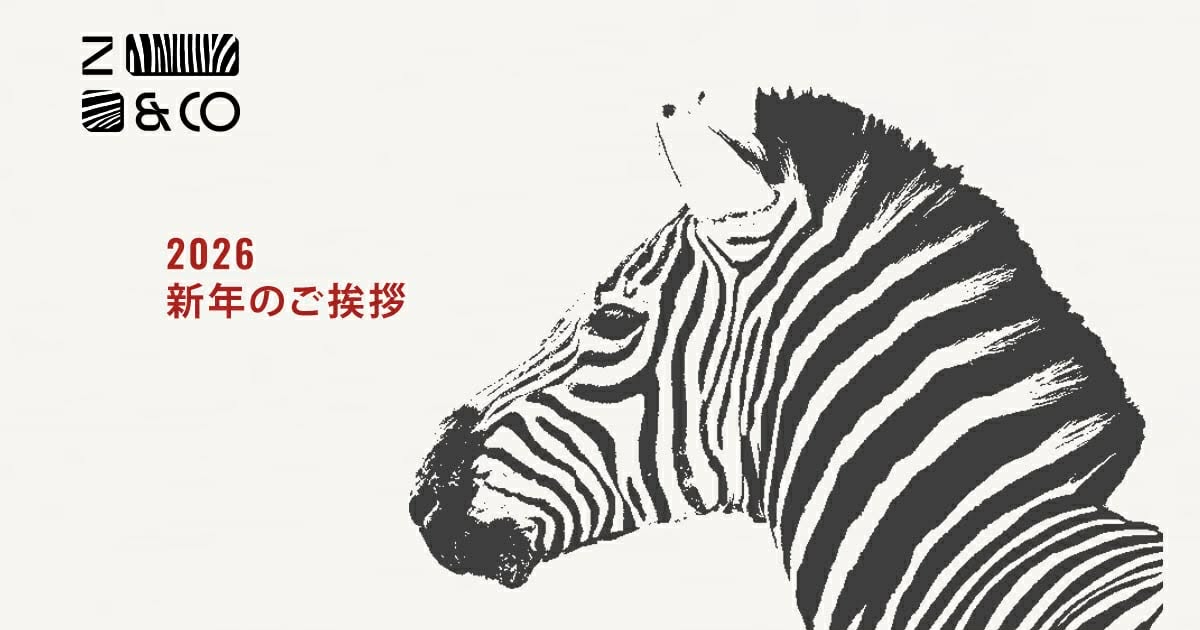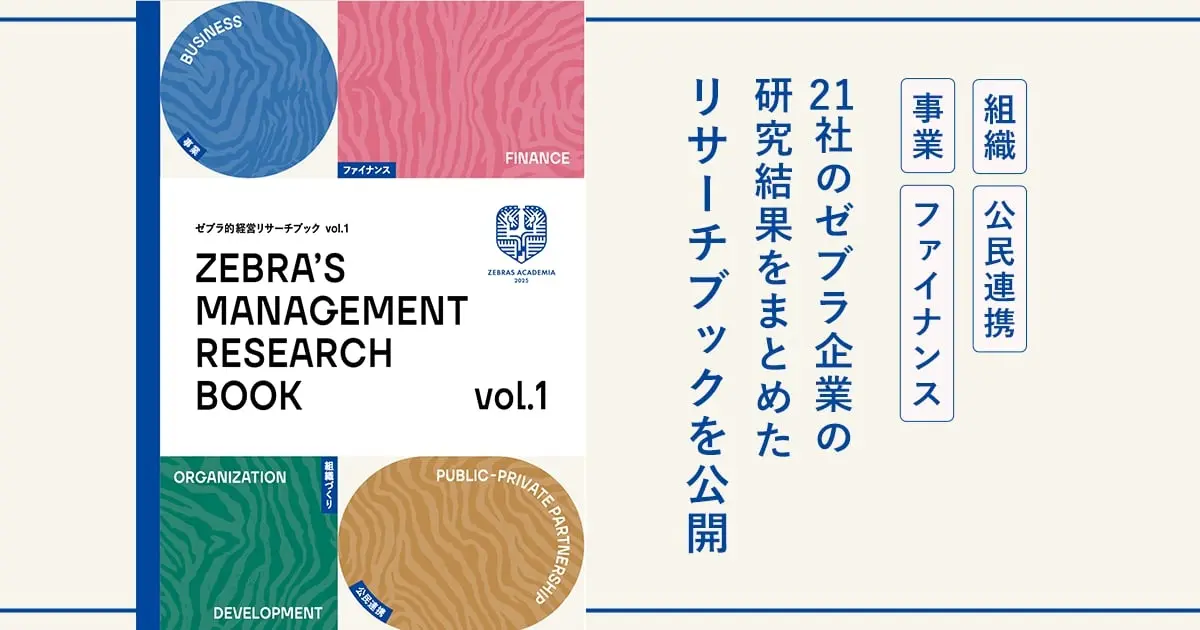2024.12.10 ZEBRAS 所有をめぐる旅
世界最大級にして160年の歴史を持つ「従業員保有企業」。イギリスJohn Lewis Partnership社の歴史とガバナンスシステム

イギリスのデパート「John Lewis」とその経営母体「John Lewis Partners」
イギリスに旅行したり、住んだりしたことのある方なら、老舗デパート「John Lowis」の名前に馴染みがあるかもしれません。90年代から続くトレードマークのモノクロ斜めストライプの紙袋や、2007年から毎年リリースされている、思わずほろりとしてしまうハートウォーミングな同社のクリスマス限定TVCMを覚えている方もいらっしゃるでしょう。
創業1864年、イギリス全土に35店舗(2023年時点)を構える同デパートは、複数の店舗が「王室御用達」に指定されていたり、2012年ロンドンオリンピックの公式デパートに任命されたりと、HarrodsやMarks & Spencerなどと並ぶイギリス屈指の格式あるデパートチェーンです。
しかし同デパートの経営母体のJohn Lewis Partnership(JLP)社が、小売業のほかに金融・不動産業なども展開する「イギリス最大の従業員所有企業」であることは、デパートの知名度のわりにあまり知られていない事実です。
なんと約100年わたって続いている民主的な評議会制度により、パートタイマーなども含む従業員全員が企業の所有・利益分配・経営方針決定に参加しています。
民主的な同社のガバナンスシステム
同社の歴史やポリシーは後ほどゆっくりお話しするとして、ユニークな民主的ガバナンスシステムをざっとお話しします。
同社においてはパートタイムの店舗スタッフなども含めた7万4000人の被雇用者すべてが民主的に(選挙で)選出した「パートナー」と呼ばれる代表者が58人で評議会を形成し、全従業員の声を収集すると同時に経営陣と同等の決定権を持ちます。この評議会はポリシーや定借の管財人の選出などを担う他、会長を辞任させる権力も持っています。この中からさらに選出された3名からなるパートナー委員会と、事業の各部門から任命されたディレクターが混在した取締役会が、ボーナス、戦略、投資計画などの重要な決定に参加することで、経営の方向性に全従業員の声が反映されるようになっているのです。
自らを「従業員所有企業」と呼ぶ同社の所有システムはしかし、私たちが想像するよりも少し間接的です。店舗や事業などすべての資産を「John Lewis Partnership Trust」という信託組織が保有しており、全従業員はそのトラストの受益者として上記のような経営への参加や、会社の全事業からの利益の分配(下記の方法でボーナスに反映される)を保証されます。この形式をとっているのは、株式を従業員に分配するといった直接的な「共同所有」よりも、従業員が株価の変動による影響から守られており、事業の持続可能性と安定に焦点を置けるというメリットがあるという理由からだそうです。
ボーナスの割合はその年の同社全体の業績(純利益)に応じて先述の取締役会で決定され、全ての従業員が各自の年収に対し一律の割合でボーナスを受け取ります。歴史的におおむね5~20%の間で変動していますが、パンデミックによる業績の著しい落ち込みを経験した2021年には史上初となる「ボーナス0」という事態に陥ったそうです。こうして事業全体の利益を賞与に直接反映させることで、従業員一人一人が会社全体の業績を自分事として受け止められるようになっています。
評議会設立の背景には「2代目」の信念
この非常に先進的なガバナンス、一体どうやって近年このスタイルにたどり着いたのか…と思えば、なんと同社がこのシステムを取り入れたのは戦前の1910年代。
同社の前身となる呉服店を、現在でもロンドンのショッピングストリートとして名高いオックスフォード・ストリートに1864年に開業した「初代創業者」のJohn Lowis氏は、7歳で孤児になり14歳から地元の呉服店に丁稚に出た、典型的な「叩き上げ」でした。商才は申し分なかったようで事業はどんどん成長しましたが、一方で家族を旅行に連れていくようなことはなく、仕事においても恣意的に従業員を解雇するなどワンマン的な面があったとのこと。息子のSpedan Lewis氏は成人してから段階的に事業を引き継ぎましたが、そんな父親と折り合いが悪く、さらに経営に参加してすぐに「自分と父と兄の3人はそれぞれが、(当時300人いた)全従業員の給料の総額と同じ額を受け取っている」ことに気づきショックを受けます。そんな折に落馬でひどいけがを負い、働きたくても働けない2年間の療養生活を送る中、「従業員と利益を分かち合いたい」という思いを募らせていったと言います。
また父親から受け継いだ(押し付けられた?)経営不振の店舗の立て直しにあたり、従業員のモチベーションが低いのは事業の利益が彼らの利益と一致しないからだと考えました。そこで労働時間を短縮したうえで歩合制を導入、1918年には全従業員に経営状況を周知するための社内報「The Gazette」を発刊し(同紙の発行は現在も継続しており、イギリスでもっとも長い歴史のある社内報となっています)、従業員全員加入の健康保険や休暇の延長・寮の環境改善など福利厚生にも力を入れて全従業員が知識・権力・利益を共有するための「産業の民主化」に取り組みます。
1919年にパートナー評議会の前身を設立、1920年に全従業員に初の利益還元パートナーボーナスを給付など精力的に現在まで引き継がれる経営スタイルを形成していきました。1928年に父親のJohn氏が亡くなり全権力を手にすると、即座に正式にビジョンを定義したパートナー憲章を定め、このパートナーシップ自体を有限会社として登記(このためパートナー評議会の設立は公式には1929年となっています)。この経営スタイルの目的は「利益を完全に従業員間で分配すること」であり、この形が完成してから同社は破竹の勢いで事業を倍々増させていきました。父親のように最期まで権力を握ることはなく、会社の所有権を管理する母体としてのトラストを完成させた1950年に会社オーナーの座を退きました。
同社ではその後、初代が存在しなかったかのように二代目のSpedan氏が『創業者』として扱われています。もちろん従業員の誇りである現在のスタイルを築いたからという意味合いもあるでしょうし、ある意味故人の陰口を言うようで気は引けますが、初代と二代目の人望の差を勘ぐらずにはいられません。
先進的なサステイナビリティへの取り組みも
さてそんな同社は現在、「よりハッピーな人々、よりハッピーなビジネス、よりハッピーなコミュニティ」をスローガンとし、「公正で持続可能なパートナーシップを築くために利益を使う」ことをビジネスの目的としています。
社会課題への取り組みに関しては列記するととてもスペースが足りませんが、特にサプライチェーンに関わる人すべてが公正な対価と労働条件を得られるためのさまざまなプロジェクトが目立ちます。ユニークなところでは、多様性歓迎のため全店舗で「静かな時間」の実施(月~土曜日の朝の1時間機械音やBGMなどの騒音を抑えている)、施設で育った若者への就職支援、英国初となる流産した従業員とそのパートナーへの6か月の「育児休暇」の給付などがあります。
また、情熱的な自然史家であった「二代目創業者」の文化的財産か、サステイナビリティへの努力も「老舗なのにサステナにも熱心」の域を超えています。サーキュラリティや責任ある原料調達、エネルギー対策といったマテリアルレベルから、生物多様性保護や脱炭素、気候変動対策といった環境レベル、「公平で包括的な社会」を実現するための社会活動、さらにはビジネスに関連するすべての人の健康とウェルビーイングまで、包括的かつ具体的な戦略が定められ、アグレッシブに目標を達成しています。
続いていく壮大な「従業員保有」の実験
「従業員保有=従業員の労働によって上げた利益は、従業員の手に再分配される」スタイルが最も公正で、利益を生みやすく、持続可能なものであるという理念を100年以上体現し続けているJohn Lewis Partnership社。しかしそんな同社も決して盤石な一枚岩ではありません。例えば1999年には一部の従業員から「株式上場」を求める声が上がり、実現すれば一人平均10万ポンドの臨時収入が得られるはずでしたが、結果として全社投票で否決されています。2023年には「株式売却」が議論されましたが、具体的なアクションには至りませんでした。
同社はこの従業員保有による経営スタイルを、ひとつの「実験」とみなしているふしがあります。そういった意味では様々な従業員から様々な声が上がり、そのたびに民主的にワーワー議論しながら結果としてビジネスが続いている時点で、実験は大成功なのでしょう。「デパート」にとって決して容易ではないこの時代、この先の100年をどう舵取って行くのか、色々な意味で興味深い会社だと感じます。
文:ウルセム幸子
編集:岡徳之(Livit)http://livit.media/

PROFILE
ウルセム幸子
3児の母、元学校勤務心理士。出産を機に幸福感の高い国民の作り方を探るため、夫の故郷オランダに移住。現在執筆、翻訳、日本語教育など言語系オールラウンダーとして奔走中。