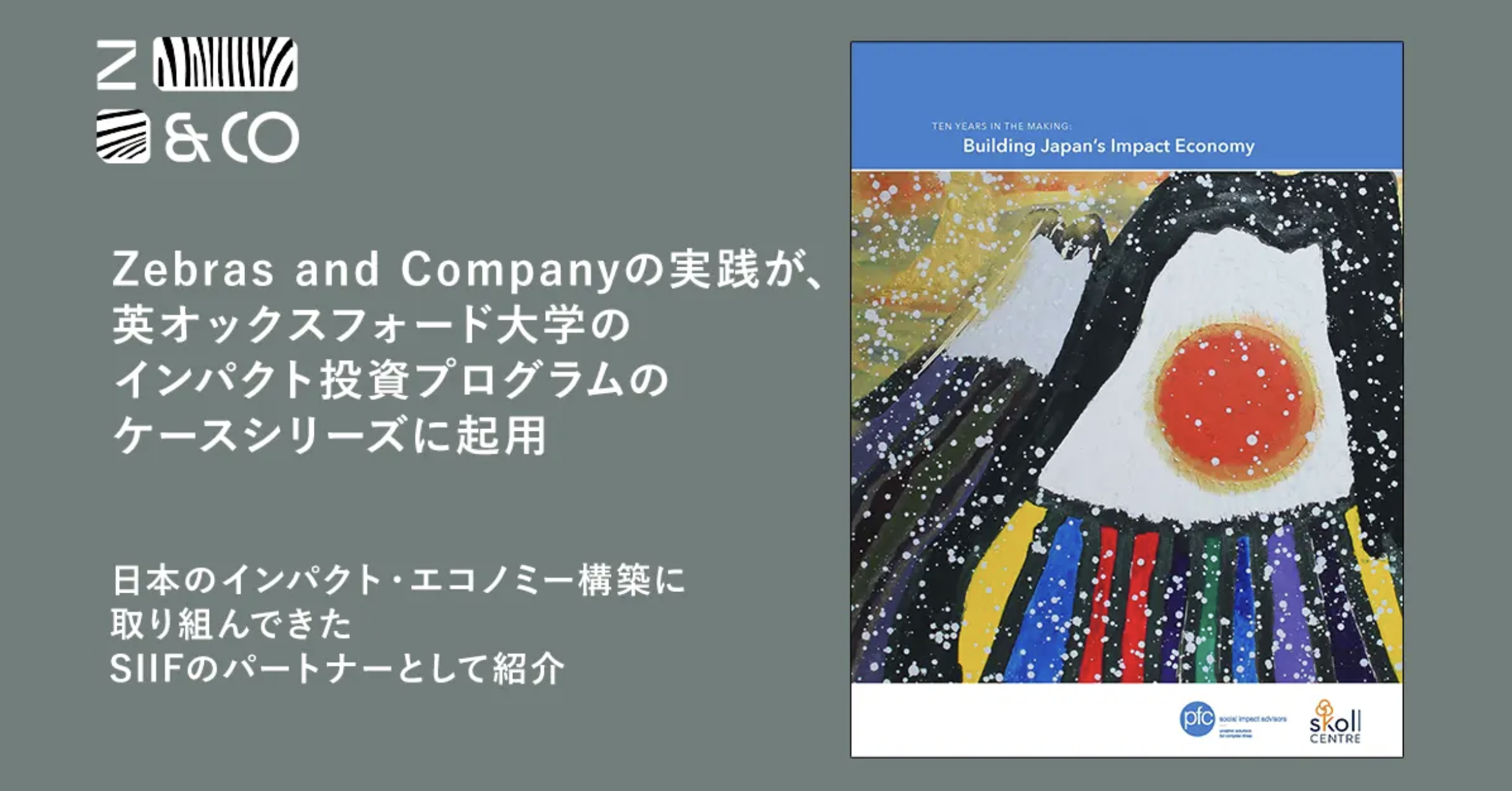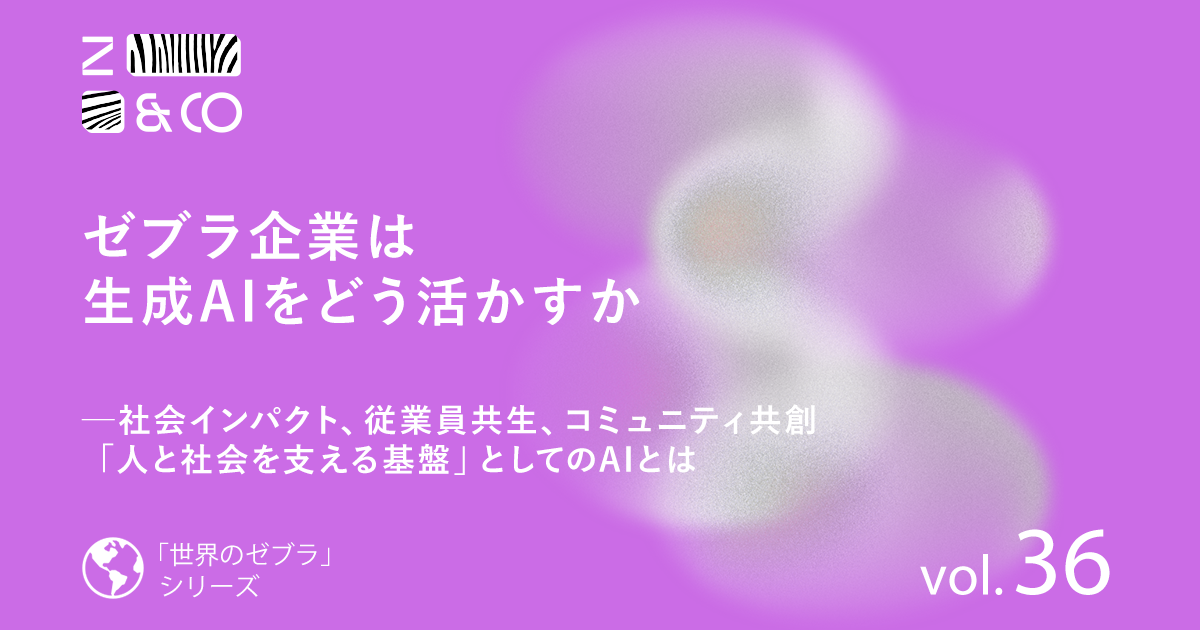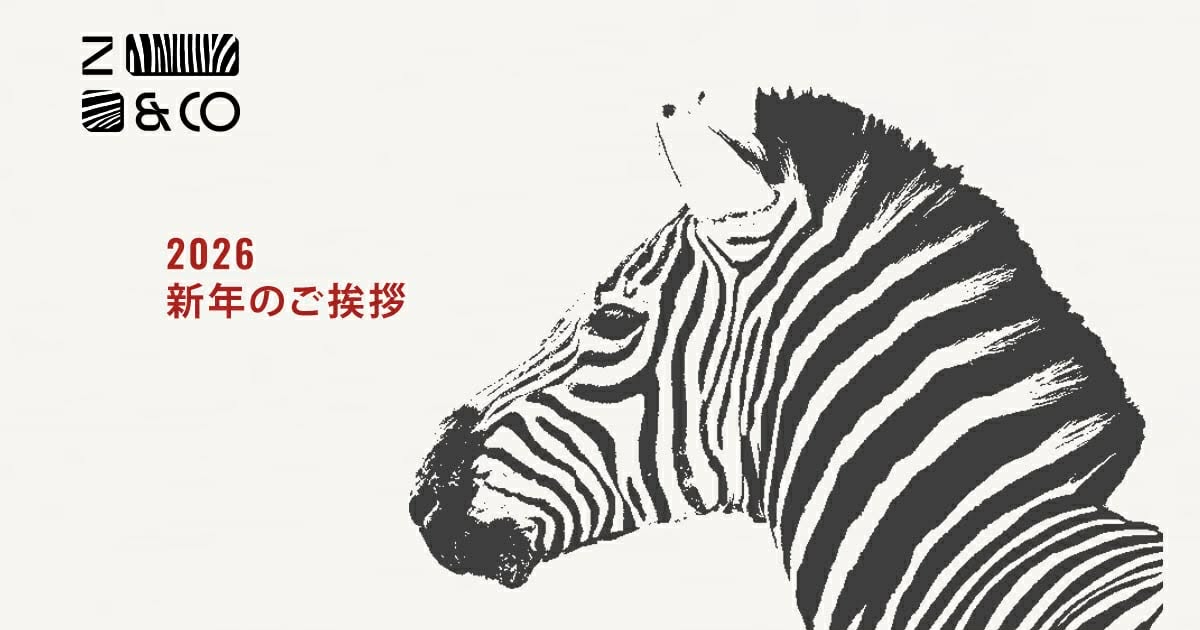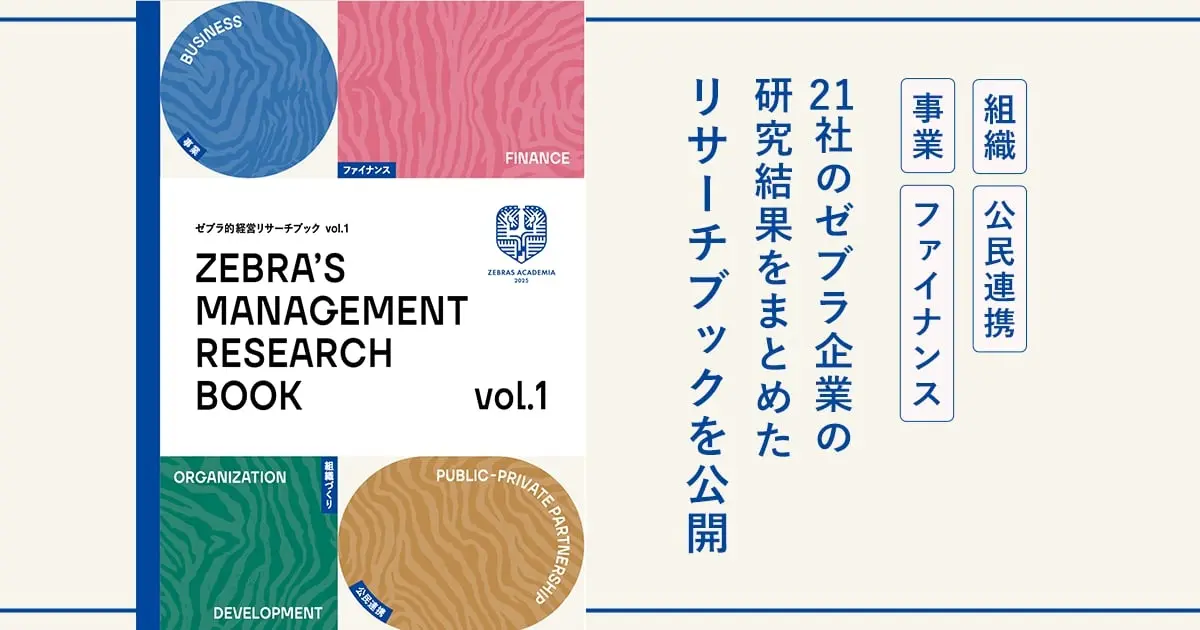2025.03.25 ZEBRAS
「地域の庭」を通じて都市と自然に手触り感を取り戻す。グリーン・ワイズ宮下さん・for Cities石川さんと考える、植物と都市と0次産業

暮らしを支える「一次産業」の土台となる自然や生態系自体が失われつつあります。日本では近年、こうした自然や生態系のリジェネレーション(再生)自体を産業とする『0次産業』という概念や取り組みが、同時多発的に見られるようになりました。そこで、Zebras and Company(以下、Z&C)では、0次産業の現在地を探る連載をスタートします。
第3弾となる今回は、前回に引き続きグリーン・ワイズの宮下明穂さん(写真右)に出演いただき、一般社団法人for Citiesの石川由佳子さん(写真左)と一緒にお話を伺います。
for Citiesは「都市体験のデザインスタジオ」として、アーバニストのプラットフォームや人と都市をつなぐ場、コミュニティ、プロダクトをつくる活動を行っています。今回は、「植物と都市と0次産業」をテーマに、環境共生と都市の視点から0次産業について語っていただきます。聞き手は、Z&C共同創業者の阿座上陽平さんです。
※グリーン・ワイズについて詳しく伺った第2弾の記事はこちら。
アーバニストをつなぐ“都市体験のデザインスタジオ”for Cities
阿座上さん:
今回の連載のメインテーマは「0次産業」です。第1弾では、海藻栽培で海の生態系を再生する事業をされているシーベジタブルさんにお話を伺い、「海(ブルー)」の視点から0次産業を考えました。そして今回は、「植物と都市と0次産業」をテーマに、都市デザインを手がけるfor Citiesさん、植物を扱うグリーン・ワイズさんの取り組みをもとに議論していきたいと思います。
まずは石川さんから、for Citiesの活動を紹介いただければと思います。
石川さん:
一般社団法人for Citiesは、2020年に私と共同代表の杉田真理子で立ち上げた「都市体験のデザインスタジオ」です。都市というと、建築やインフラなどのハード面の話をイメージしがちですが、私たちが着目しているのは、都市と人の関係性といった「ソフトな体験」のほう。
現在の都市における課題のひとつは、「都市の作り手と使い手の乖離」だと考えています。都市化が進むと、多くの人は「都市を使う」ことに慣れ、都市を「つくる」感覚がなくなる。例えば、街を歩いているときに、「ここにこんなものがほしい」と思っても、自分からアクションをとることはなかなかないですよね。
その場所に住む人たちの「こうしたい」という思いが、手触り感を持って都市や暮らしに反映されていくように、「都市の作り手と使い手をつなげる」体験をデザインしているんです。
阿座上さん:
創設以来どのように事業を展開してきたのですか?
石川さん:
最初に立ち上げたのは、アーバニストたちのオンラインプラットフォーム「forcities.org」です。きっかけとなったのは、私と杉田がコロナ禍のオランダに滞在していたときのこと。オランダでは、都市計画の専門家や行政関係者だけでなく、その街のDJやアーティスト、パン職人など多様な人々が「自分の街をどうしたいか」という意思を持ち、積極的に街づくりに関わっていました。日本やアジアでも、こうした都市のあり方を実現していくために、まずは人や情報をつなげることから始めたんです。
現在は、そこから派生して、アーバニストを育てる学びの場をつくったり、体験を促すプロダクトをつくったりもしています。また、行政と組んで、日本のローカルな課題に対して海外のクリエイターやアーバニストの視点を入れ、新しい解決策を考える取り組みも行っています。例えば、最近ではベトナムのクリエイターを神戸の空き家に招き、建築家やデザイナーと一緒に廃墟の活用方法を考えるプロジェクトを実施しました。
阿座上さん:
ベトナムにある知見やノウハウを意識しているということですか?
石川さん:
はい。ベトナムを始めとするアジアの国には、リジェネラティブの考え方を体現する知恵や技術が、古くから根付いています。例えば、エアコンに頼らず、風の流れを活かして室内を涼しくする建築技術や、川から冷気を取り込む住居の設計。他にも、日陰をつくるための独自の工夫など、気候や環境と共生するための方法が、生活のなかに取り入れられています。こうした土着の知恵を「Everyday Regenerative Practices(日常のなかのリジェネラティブな実践)」として体系化し、現代の都市づくりに活かせないかと考えているんです。
具体的には、今年の2月から、ベトナムに「everyday studio」という名前で研究開発拠点を設け、こういったアジアの日常の中でのまちづくりや、建築の実践をアーカイブし発信しています。
阿座上さん:
日本も熱帯化が進んでいるので、そうした知恵が役立つ場面が増えそうですね。
石川さん:
そうなんです。技術革新だけでなく、「過去の文化や知恵を再編集すること」も持続可能な都市づくりにつながると思います。
また、アジアには、日本よりも規制が緩いため、モノづくりや実証実験がしやすい環境があります。新しいプロトタイプをそうした国々で試し、その知見を日本に持ち帰って実装する。このように、アジア全体をダイナミックにつなぎながら新しい都市のあり方を模索していきたいと思っています。
庭園を通じて、植物の魅力や活かし方を伝えるグリーン・ワイズ
阿座上さん:
続いて、グリーン・ワイズの宮下さん。簡単に自己紹介とお仕事の内容を教えてください。
宮下さん:
グリーン・ワイズは、その名の通り「自然や植物の叡智」を借りて、環境創生のノウハウを生み出し、人や企業、マルチスピーシーズにとっての価値をつくる企業です。そのなかで、主に私は商業施設やオフィスビルの屋外庭園の管理を担当しています。また、庭の植物を使ったイベントの運営や、室内の観葉植物の管理にも関わっています。
庭園管理の仕事は、設計チームがお客様の想いを反映させてデザインした庭園を、その意図を受け継ぎながら維持していくというものです。お客様に対して、設計の思いや植物を活用する方法を伝え続けていくことも大切にしています。
阿座上さん:
具体的にはどのような事例がありますか?
宮下さん:
商業施設でいえば、グリーン・ワイズは横浜の「マークイズみなとみらい」の屋上にある「みんなの庭」の管理を担当しています。植物の手入れに加え、土日には植物と触れ合うイベントを開催し、地域特産の湘南ゴールドなどの柑橘収穫や野菜の水やり・収穫体験なども行っています。
宮下さん:
また、オフィスでいえば、カメラ・レンズメーカーのSigmaさんの新社屋にあるグリーン・ワイズが設計から携わった庭園の管理をしています。社員さんがリフレッシュできる場所や、交流の機会をつくるために、春のガーデンツアーや、ハーブを使ったドリンクづくりなどのイベントを実施しています。
さらに、カメラ・レンズメーカーらしく社内フォトコンテストでは、「身近な自然や植物をテーマにしてはどうか」と提案し、私たちも協賛しました。グリーン・ワイズ賞を設けたのですが、そこに選出されたのは、枯れゆく花とそこに集まる蜂の姿が写された作品でした。綺麗に凛と咲くだけではない「植物のありのままの美しさ」と「生物との共生の姿」が、私たちの大切にしている価値観と重なったんです。
石川さん:
審査基準が玄人ですね。でも、Sigmaの社員さんからこの写真が出てくるということは、普段の関わりのなかで、グリーン・ワイズさんの大切にしたいことがきちんと伝わっている証拠だと思います。
宮下さん:
定期的に、庭の管理に入るので、そこで社員の皆さんとお話しています。季節の花を切ってカフェテリアのみなさんが見えるスペースに置いておくと、家に持ち帰ったり、デスクに飾ってくれたりすることもあるんです。
私たちの仕事は、庭をつくって引き渡して終わりではなく、「どういう想いでつくられた庭なのか」「どういう過ごし方ができるのか」といった部分まで伝えていくことだと思っています。もちろん、植物を眺めて「綺麗だな」と感じてもらえるだけでも嬉しいのですが、そこからさらに「自然の中でこんなことができるんだ」「この植物にはこんな一面もあるんだ」と、新たな気づきにつながるような時間を提供できたらと思います。
石川さん:
庭園が素敵な場所であり続けるには、お客様側の意識も大切ですよね。管理にしっかりコストをかけて、定期的にメンテナンスをすることを受け入れてもらわないといけない。でも、それって企業にとってはコスト削減の対象になりやすい部分でもあります。宮下さんたちが価値をしっかり伝えられているからこそ、継続的な管理ができているんですね。
宮下さん:
庭があることで働き方が変わったり、社員さん同士の交流が生まれたりすることに価値を感じてもらえているのだと思います。私たち自身も、自社のオフィスで「スプリング・カットバック(刈り込み)」の会を開き、お客様を招くこともある。そういう場で自然に触れながら会話をしていると、普段とは違う気づきや対話が生まれるんです。植物が様々なものをつなぐことで、働き方や会社にとってのプラスの影響が生み出せる。そんな価値を、これからも届けていきたいと思っています。
植物と都市と人をつなぐ「地域の庭」という可能性
阿座上さん:
自然環境、特に植物の再生に取り組むグリーン・ワイズさんと、リネジェラティブな文化を編集し都市に反映していくfor Citiesさん。ここからは、0次産業の両者のかけ合わせで見えてくる可能性について話していければと思います。石川さん、ここまでの話を聞いて何か思いついたことはありますか?
石川さん:
先ほど「手触り感のある都市づくりをしたい」という話をしましたが、この「手触り感」というテーマは、グリーン・ワイズさんとも共通していると感じました。グリーン・ワイズさんは、ただの観賞用の庭園ではなく、自然と自分とのつながりを感じられる場所をつくっている。そういう意味で、まさにアーバニストです。
また、ここ数年、屋上庭園やオフィス内への植栽の導入を通じて、企業内の共有空間をつくる取り組みが増えています。今後は、これがさらに発展し、複数の企業や地域の人々が協力して「地域の庭」をつくる という新たな可能性が広がるのではないかと思います。
阿座上さん:
「庭」ですか。
石川さん:
そうです。例えば、私がもうひとつ理事を務める一般社団法人ソーシャルグリーンデザイン協会のメンバーで、株式会社フォルク代表の三島由樹さんが手がける「シモキタ園藝部」という取り組みがあります。世田谷区の北沢・代沢・代田エリアを拠点とするコミュニティガーデンです。
ここでは、都市設計や建築などのハードを手がけてきた人たちが、土や地面、土壌に目を向け始めています。そして、一緒に土に触れるソフトの体験がコミュニティを育み、地域をつなぐことを証明していっているんです。
こうした「身体性」をともなう環境や場のつくり方、さらには組織やコミュニティのあり方は、従来の建築的な発想とは異なるものであり、今後ますます大切になってくると思います。
阿座上さん:
様々な組織や人が協力して、その地域に「庭」をつくるという発想は面白いです。庭だからこそ、当然そこにグリーンが入ってくる。グリーン・ワイズさんが、自然の叡智を持ち込むこともできそうです。
石川さん:
まさにそうですね。最近、地域に「コミュニティガーデンをつくりたい」とか、「管理できない土地を地域の共有財産として活用できないか」といった相談が増えてきています。そうした場所のあり方や、そこに植えるべき植物については、グリーン・ワイズさんのような植物の専門家と一緒に考えていきたいですね。
阿座上さん:
以前、農業とコミュニティについて研究している方に話を聞いたのですが、農業でできる共通体験には「収穫祭」のようなものがあると言っていました。ただ、都市で暮らしていると、農業に触れられる人は限られると思います。それと比べて街のなかにある「庭」は、より多くの人が関われる仕掛けになりそうですね。
宮下さん:
種類にもよりますが、野菜は基本的に収穫時期が決まっていますよね。一方で、庭なら野菜だけでなく様々な種類の植物を植えることができ、四季を通じてイベントや体験をつくりやすい。自分が暮らす都市のなかで植物や生き物と触れ合い、環境について考える機会を生み出せる場所になると思います。庭を活用することの意義は、今後ますます大きくなると感じました。
都市と自然に手触り感を取り戻す「境界」の引き方を考えたい
阿座上さん:
「植物と都市と0次産業」は難しいテーマでしたが、「庭」というキーワードによって考えを深める方向が見えてきたように感じました。今日の対談を経て、お二人のなかに残ったことや、今後探求していきたいテーマがあれば、お聞かせください。
石川さん:
ふと、「境界」という言葉が浮かびました。人類が経験してきた産業化や都市化とは、境界を超えていくことだった、とも捉えられると思います。グローバリゼーションもその一例で、境界がどんどん消え、地球全体をひとつとして考えるようになりました。そして今、私たちはその地球のキャパシティの限界に直面しています。
一方で、かつての日本は、もっと小さな境界を意識していました。山間地の古いことわざには、「この裏山は何人分を養える」といった表現が残っています。つまり、暮らしを自分たちの境界内で維持するという感覚を持っていたことがわかります。
世界がつながっていくことは素晴らしいですが、その一方で、地域に目を向ける感覚や手触り感を取り戻すことも大事です。今こそ、新しい「境界の引き方」を考えるタイミングなのかもしれないと思いました。
阿座上さん:
境界を引き直し、そのなかでコミュニティが機能する。例えば、食べ物をまかなうといった考え方ですね。都市のなかに「庭」をつくることは、そうした境界を考え直すためのひとつの鍵になりそうです。宮下さんはいかがですか?
宮下さん:
今日改めて感じたのは、都市において「本当の自然」というものが、自分から求めにいかないと触れられない存在になっていることです。そして、だからこそ自然に触れられる場所に自ら飛び込んでいくことの大切さです。
その体験を通じて「自分も地球の自然の一部であり、生き物のひとつに過ぎない」と実感できるようになる。その視点を持つことで、「自然や周りの人たちに対して還元できるものは何か」という考え方が生まれてくるのではないかと思います。
グリーン・ワイズとしても、私個人としても、「人間が自然の一部であることを実感できる体験」を通じて、環境共生の社会を目指していきたいと改めて思いました。
石川さん:
都市も自然もつくって終わりではなく、その後どう管理し、どんなコンテンツを生み出していくかが重要ですよね。その部分を創造的に考えていくことが、0次産業につながると思います。そうした試行錯誤の取り組みに、お金や人がついてくるような仕組みはもっと考えていきたいですね。
阿座上さん:
「庭」を通じて、自然や都市に手触り感を取り戻せる可能性があること。そして、そうした活動にお金や人がついてくる仕組みが、0次産業を成り立たせるヒントであることなど、様々な視点で考えることができた対談でした。今日はありがとうございました。

PROFILE
Fumiaki Sato
編集者・ライター・ファシリテーター。「人と組織の変容」を専門領域として、インタビューの企画・執筆・編集、オウンドメディアの立ち上げ、社内報の作成、ワークショップの開催を行う。趣味はキャンプとサウナとお笑い。