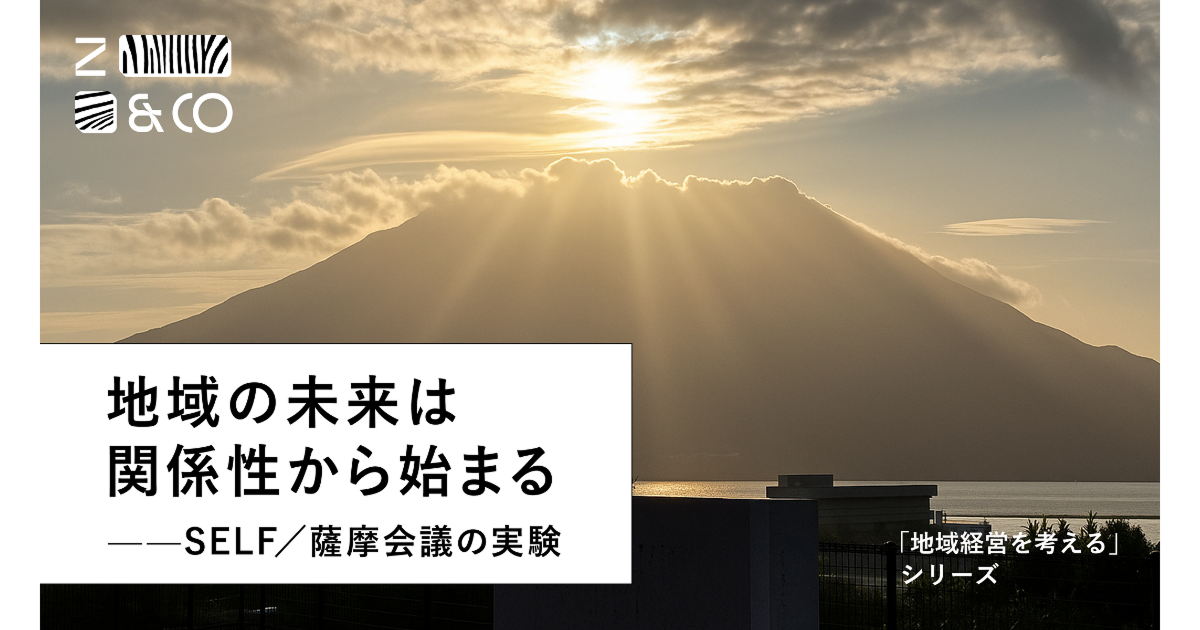2025.02.26 ZEBRAS
海の生態系が抱える社会課題とは。ブルーインパクトの研究内容と、シーベジタブルの実践から注目分野『0次産業』の可能性を探る

私たちの暮らしは農業・林業・漁業といった「一次産業」に支えられています。昨今では人手不足などが問題視され、高付加価値化やDXの議論が活発にされていますが、それでは根本的に解決しない課題も存在します。それは、一次産業の土台である「自然や生態系自体が失われつつある」こと。
日本では近年、こうした自然や生態系のリジェネレーション(再生)自体を産業とする『0次産業』という概念や取り組みが、同時多発的に見られるようになりました。そこで、Zebras and Company(以下、Z&C)では、『0次産業』の現在地を探るべく連載をスタートします。
連載第一弾で着目するのは「海」の領域です。環境問題や生物多様性のフィールドは「森」であると認識されがちですが、実は「海」が環境に与える影響も大きいことが知られています。海洋や水資源を持続可能に利用しながら経済成長、社会的包摂、環境保護を同時に実現する経済モデルは「ブルーエコノミー」、それによる影響は「ブルーインパクト」と呼ばれ、人類の未来を考える上で欠かせないテーマとなっています。
そこで今回は、一橋大学大学院社会学研究科でブルーインパクトを研究する佐藤真陽さん(以下、真陽さん)、事業を通じて海の生態系の再生を目指す合同会社シーベジタブル共同代表の友廣裕一さん(以下、友廣さん)と一緒に、海の課題と可能性について考えていきます。ブルーインパクトとはいかなるものか。その先駆けであるシーベジタブルの実践とは。Z&Cの阿座上陽平さん(以下、阿座上さん)がファシリテーターとなり、ゼブラの視点から『0次産業』の可能性を探ります。
佐藤真陽
2000年生まれ、秋田県出身。一橋大学大学院社会学研究科修士課程在学中。立命館アジア太平洋大学在学中、プラスソーシャルインベストメント株式会社のスタッフとして、主に立命館ソーシャルインパクトファンドのサポート業務に従事し、社会的インパクト投資について学ぶ。2024年8月より一般社団法人IMPACT SHIFT理事に就任。現在は、これまでの学びを活かし、社会学・評価学を軸に、社会的インパクト評価と海の社会課題を研究をしている。
友廣裕一
合同会社シーベジタブル共同代表
1984年生まれ、大阪出身。早稲田大学卒業後、全国70以上の農山漁村を訪ねる旅へ。各地の暮らしに寄り添いながら、どんな人たちがどんな想いで生きているのかを学ぶなかで、2009年に蜂谷潤さんと出会う。室戸での活動に加えて、東日本大震災以降は一般社団法人つむぎやを立ち上げ、宮城県石巻市・牡鹿半島のお母さんたちと浜の弁当屋「ぼっぽら食堂」や、鹿の角を使ったアクセサリー「OCICA」などの事業も運営してきた。人や組織をつなぎながら、新たな海藻食文化をつくるべく駆け回る。
ブルーインパクトに不可欠な「ストック」と「評価可能性」の観点
阿座上さん:
今日は、いま海の生態系で起きている変化と、そこに人がどう関わっていけばいいか聞いていきたいと思います。まず、海の現状について研究している真陽さん(佐藤真陽)から、研究の内容について教えてもらえますか?
真陽さん:
私が現在研究しているのは、社会的インパクト評価についてです。特に、社会学と評価学の観点から、海の社会課題に対するインパクト(ブルーインパクト)をどう考えていくべきかを探求しています。
海の課題というと、以前は「温暖化で北極の氷が溶け、しろくまの住処がなくなる」といったシンプルな問題設定がされていました。しかし、現在は時間軸も変化したことにより「氷が溶けて海流が変わったため、特定の地域で取れていたブランド魚が他の場所でも取れるようになり、地域ブランドがそこなわれた」といったように課題がより複雑になったんです。
海の課題はとんでもなく複雑です。食文化や食の安全性、生物多様性、観光、さらには海で働く人たちの人権問題や移民問題、領土問題など多種多様な要素が絡み合っています。そのため、ひとつの課題を解決する取り組みが、他の課題を深刻化させることもあり、どの課題から解決すべきか、どんな政策提言をすべきか、どの取り組みにインパクト投資をすべきかの判断ができない状況になっています。
そこで、現在取り組んでいる研究では、海にまつわる会社、事業、団体の取り組みが生み出すインパクトを明確化するために、我々は海の社会課題をどのようにとらえるべきなのか調査しています。
阿座上さん:
海の課題や生態系が複雑ななか、取り組みのインパクトをどのように評価していますか?
真陽さん:
全体を捉えることは難しいので、具体的には地域や文化で区切って調査しています。そのエリア内の生態系がどのような課題を抱えているのか、そこでどのような活動が行われ影響を与えているのかを調べ、その「価値」を分析していくんです。
「価値」を分析するうえで重要なことは2点あります。1点目は、海洋資源を資本と考え、一時的な財の増減(フロー)だけでなく、残高の増減(ストック)を見ることです。例えば、ある漁業振興政策によって漁獲金額が高まったとしても、それが未来の海洋資源を不可逆的に毀損するものであれば、その政策はプラスであるとは言い切れないと判断すべきなのかなと個人的には思います。
2点目は、評価学の先生方がよく議論していることですが、「測定可能性(Measurability)」から「評価可能性(Evaluability)」に変えていくということ(*1)。大雑把にいえば、「ごみが何トンある」と測定するだけでは、「清掃活動を行った地域の海岸ごみの総量が50%減少したが、流入するごみの量は依然として多い」といった根本的な解決にならないこともあります。そのため、何をどう評価するのかを明確にすることが重要だと思います。海も常に生態系が変化しているからこそ、目の前の状況を測定するだけでなく、何を改善するために、どんな海にしたいかを考えていくべきなのではないかと感じます。
海洋生物などは個体数の測定が難しく、かつ、特定の海域における測定ができたとしても、そこから海全体の影響について分析することが難しいのがブルーの領域。だからこそ、測定にとどまらず、「そもそも何を価値として、どのように評価すべきか」から議論することが必要だと思います。
阿座上さん:
そうした研究を通して、どのような未来を実現していきたいと思っていますか?
真陽さん:
海の課題を構造的に捉え、それぞれの課題解決が、現在(フロー)と未来(ストック)、量的と質的、特定の海域と海全体、といった様々な観点でどのようなインパクトを生み出しているのかを明らかにすることです。そうすることで、効果的な施策を増やすことや、政策提言・インパクト投資の方針決定の土台を整えていきたいと思います。
*1 米原あき.(2021年).「SDG 教育目標にみる理念志向ターゲットの評価に関する一考察:測定可能性(measurability)から評価可能性(evaluability)へ」を参照
種苗生産から新たな食文化づくりまで手がけるシーベジタブル
阿座上さん:
海にまつわる活動を見てきたなかで、真陽さんは「海藻」に着目していると聞きました。シーベジタブルの話を聞く前段として、ブルーインパクトにおける海藻の重要性について教えてください。
真陽さん:
近年、海藻はブルーのなかでも大きなトピックのひとつになっていると感じます。特に、ブルーカーボン(海洋生態系に取り込まれる炭素)において、海藻による炭素吸収の重要性が高まっていると思います。。今までは炭素を吸収するものといえば「マングローブ」が注目されていました。ただ、マングローブは気候的な条件によって生息する場所が限られています。その点、海藻は日本中の海に生えているので、脱炭素に向けた取り組みも展開しやすいとされやすいのではないでしょうか。。
実際、ジャパンブルーエコノミー技術研究組合(JBE)が運営主体として管理する独自のクレジット「Jブルークレジット®️」を発行する企業のなかにも、海藻や藻場の事例が多くみられます。。ブルーエコノミーの観点でもそうですし、脱炭素、地球温暖化、環境問題を考えるうえでも、海藻は大きな切り口のひとつになっていくと考えられます。
阿座上さん:
では、ここからは友廣さんに話を聞いていきます。まずは合同会社シーベジタブルの事業概要を教えていただけますか?
友廣さん:
シーベジタブルは、磯焼けにより減少しつつある海藻を研究し、環境負荷の少ない陸上栽培と海面栽培によって蘇らせる種苗生産技術を持つ会社です。また、料理人のメンバーも加わり、海藻を使った新たな加工品や食べ方の開発もしています。研究や生産といった上流の部分と、加工や流通、調理法の提案といった消費サイドの両輪を回すことで、食文化を守りつつ海をより良くしていこうとしているんです。
阿座上さん:
海藻のサプライチェーン全体にアプローチしているんですね。創業の背景やこの事業に取り組むようになった経緯を教えてください。
友廣さん:
シーベジタブルを創業したのは2016年。きっかけは、河口の水温上昇により高知県四万十川の「天然すじ青のり」の収穫量が減ったことで、事業の先行きに不安を感じたアオノリを使用しているメーカーから相談を受けたことです。2016年の数年前からスジアオノリの収穫量は半減を繰り返し、値段は倍々に増えている状況でした。
僕らに相談がきたのは、それ以前に取り組んでいた事業の関係で、前例の少ない海藻の陸上での栽培技術を持っていたからです。これは、もともと海藻を餌とするアワビの生産のために、共同創業者の蜂谷が取り組んでいたもので、海藻を陸上栽培し、アワビの餌にするというもの。アワビが育つ過程で排出される窒素や有機物が溶け出した排水を、再度、海藻を育てるのに使うという「複合養殖」の技術でした。
蜂谷のこの案は、あるビジネスプランコンテストで大賞を受賞し、市のバックアップを受けながら実証研究をすることになりました。シーベジタブル創業前の4〜5年、アワビの養殖事業をメインで取り組んでいたんです。
阿座上さん:
そこから「海藻養殖」に方向転換したのはなぜですか?
友廣さん:
アワビは出荷できるまでに3〜5年ほどかかるので、事業として成り立たせるのが難しかったんです。
そんなときに、先ほど話したメーカーからのご相談をいただき「すじ青のりならできる」となって海藻の会社を二人で創業しました。また、蜂谷が地下海水を用いることで、コストを下げながら量産する技術も確立できたのもあって、陸上での生産事業を広げていくことにしたんです。
僕らの初めての大きなお客さんはオタフクソースさんでした。そのあとポテトチップスやふりかけ用のアオノリを必要とする企業様など長期の取引契約を結ぶことができたんです。急激に収穫量が減っていたアオノリをなんとか復活させるために、1年で複数箇所を立ち上げるといったスピード感で生産拠点を増やしていきました。
阿座上さん:
アオノリの陸上生産の技術で、日本ののり塩ポテトを救ったんですね。
友廣さん:
食文化を守ることができましたし、陸上での栽培は漁船漁業などと比べて作業負担や危険性が少ないので、拠点のある地域の高齢者や障がいを持つ方の雇用を生み出すことにもつながりました。
海面に浮く「養殖藻場」が海の生態系を再生し、新たな雇用も生み出す
阿座上さん:
そもそものところを聞きたいのですが、海藻が取れなくなってしまう「磯焼け」が発生する原因はなんなのでしょうか?
友廣さん:
磯焼けの原因はいろいろとあるのですが、たくさんの地域を実際に潜って見てきた経験として、大部分は、魚が海藻を食べ尽くす「食害」によって発生します。その一番の要因は水温の上昇です。そもそも海藻は、水温が低くて魚やウニなどの藻食動物が活発ではない時に芽生えて育ち、水温が高くなってきたら食べられるという周期があります。
しかし、最近は温暖化により、地域によっては水温が3〜4度上昇したことで、藻食動物が一年中活発に活動して、幼い状態の海藻を食い尽くしてしまうんです。海藻がなくなると、そこに住む魚や、海藻を餌とするアワビなどの貝類、海藻に付着する小型生物やそれを捕食する生き物などもいなくなるので、生物多様性は失われていきます。
阿座上さん:
食害による磯焼けの問題に対してどのようなアプローチがあるのでしょうか。シーベジタブルの取り組みについても教えてください。
友廣さん:
現在、対策として日本中で行われているのは「藻場造成」の取り組みです。海藻の群落である藻場ができるには、岩など安定した基盤が必要になります。そこで、海底に人為的な基盤を築き、そこに天然の海藻を根付かせようとしているんです。また、漁師に依頼して、魚と同様に食害を引き起こすウニを駆除していく取り組みも行われています。
しかし、これらは魚の食害の対策にはなっていませんし、小さな天然藻場が守れたとしても継続性も拡張性も担保するのは難しいのが現状です。そこで、シーベジタブルでは、広範囲で展開可能な新たなソリューションとして「養殖藻場の造成」に取り組んでいます。
養殖藻場とは、海面で海藻を栽培し、一時的に「海面に浮かんだ藻場」をつくる取り組みです。この藻場は海に浮いているのでウニに食べられることはないですし、水温の低い時期や海域を選んでつくるので、魚の食害も受けづらい。それでも食害がある場合は、カゴで囲むなどの対策が可能です。
現在、日本で種苗生産技術が確立していて供給可能な状態になっている海藻は4種類しかありませんが、これらの栽培適地とされる漁業権が設定されている海域は、すでに新規では参入できないほど利用されています。一方、それ以外の海域は耕作放棄地のように空いている。そこで、僕らは新たな種苗生産技術を開発し、漁師さんたちと連携しながら、日本中の放棄されている海域を養殖藻場で埋め尽くそうとしています。
阿座上さん:
海面に浮いた養殖藻場によって生態系が回復するということですね。
友廣さん:
磯焼けで魚がいなくなった海で栽培試験をしてみたところ、目で見て明らかに魚が増えました。ただ、このエビデンスが世の中に存在しなかったので、一般社団法人グッドシーという法人を立ち上げて、公益財団法人日本財団から支援をいただいて生態系調査を進めてきました。北海道で昆布、瀬戸内でひじき、九州でトサカノリを栽培し、珪藻の種類や、ワレカラ・ヨコエビなどの小型の葉上動物、魚などの生物資源量の変化の定量調査を約1年間かけて行ってきました。
その結果、たとえば瀬戸内海のひじきの養殖藻場では、ワレカラやヨコエビ(珪藻を餌とする小型の甲殻類)などの葉上動物が1haあたり2億個体多く存在することが確認されました。比較対象となる養殖藻場外にはほぼ存在しなかった生物たちです。さらに、それを食べにくる魚の量が、養殖藻場外と比べて最大7倍になりました。まだ調査は1年だけなので、ここから数年かけて調査拠点や海藻の種類も増やしながら、より詳しく調査をしていくつもりです。
阿座上さん:
育った海藻は収穫すると思いますが、そうすると魚の餌がなくなってしまうんでしょうか?
友廣さん:
そもそも多くの海藻は1年で枯れてしまう単年性なので、水温が上がって枯れて消失する前に人間が収穫、加工、流通して食すのは自然の理にかなっている。そこで漁業者さんたちの経済的に成り立たせることで持続的に取り組める点も、養殖藻場のメリットです。
漁業権の関係で養殖藻場をつくるには、漁師さんたちの協力が不可欠です。藻場造成のように補助金に頼るのではなく、彼らが儲けられる仕組みをきちんとつくることで取り組みは持続していきます。海藻を食べれば食べるほど、養殖藻場が増えて生態系が豊かになり、経済的にも回収できる。かつ、海藻を食べる側もミネラル豊富な海藻で健康にもなるし、養殖藻場のある地域側も働き口が増え、特産品として地域に波及した経済効果を生むこともできます。
養殖藻場は、海に関わるみんなが幸せになるモデルだと考えています。
長期的視野にたち、エコシステム全体の価値を捉えていく
阿座上さん:
まさに、自然や生態系のリジェネレーション自体を産業とする「0次産業」の好例だと思います。真陽さんは、この事業についてどのように見ていますか?
真陽さん:
あるべきブルーエコノミーだと思います。ブルーエコノミーという言葉に統一的な定義はないですが、2017年に世界銀行は「持続的な海洋資源の利用を通じた経済成長、生活の改善や、海洋生態系の健全な保全がもたらす雇用」としています。ポイントになるのは、海洋環境の改善・保全と経済成長を両立させることです。
海と、海に関わるステークホルダーすべてにとってwin-winの状況をつくるのが非常に難しく、そのバランスが崩れると「生態系が一気に崩れて、産業もろともなくなってしまう」のがブルーの怖いところなのかなと個人的には思います。シーベジタブルの取り組みはその点を考慮したうえで、特定の人がひどく悲しんだり苦しんだりすることなく、生態系全体にとってプラスに向かうように設計されているのが素晴らしいです。
また、シーベジタブルは、海藻の種苗生産から、養殖、加工、流通、食といったエコシステムが一元化されているので、それぞれの影響を分析することができる。海の生態系を理解し、海にまつわる他の課題を解決するヒントにもなるかもしれないという意味でも、非常に価値ある取り組みだと思います。
友廣さん:
真陽さんが言ってくれたような「シーベジタブルのエコシステム全体の価値」を評価し、広く理解してもらうことが、これからは必要だと思っています。
真陽さん:
もし、シーベジタブルさんが海藻に特化したインパクトレポートを出してくれたら、インパクト投資をする側が出資の割合を検討できたり、隣接する他の課題に取り組む人たちが、自身の持ち場でできることを考えられたりするはず。自分たちの活動のインパクトを発信していくことは、社会課題の解決を目指すエコシステム全体にとってプラスになります。
阿座上さん:
ゼブラ企業にも同じことが言えます。ゼブラ企業が取り組んでいる社会課題の中には、まだ認知されていないものもあり、事業の価値を測定しづらい場合も多くある。インパクト投資で用いるセオリーオブチェンジ(TOC)などで、可能な限りインパクトを測定することによって、事業の価値を伝わりやすくし、周りの人が関わる余白を生み出すことが大切です。
友廣さん:
価値をしっかり伝えることの大事さは、僕らも感じています。昨年の秋に日本橋三越本店と伊勢丹新宿店で行った、海藻の新たな食体験を通じてその可能性に触れるフェア「EAT & MEET SEA VEGETABLE」。食料品フロア全体の120以上の有名店が、海藻を使った170以上の新商品を開発して期間限定で販売してくれたのですが、これも事業の価値に共感してくれたバイヤーのみなさんのおかげで実現しました。一般的ではない「海藻が主役のフェア」をやることはリスクが大きかったと思いますが、「売れるとわかっているものではなく、世の中にない価値を広げるのが百貨店の役割だ」と力を貸してくれたんです。
また最近では、パナソニックHDさんとの共同実証も決まりました。パナソニックHDさんのロボット技術やIoT技術、設備開発の知見と、僕らの培養・栽培技術を組み合わせて、ネイチャーポジティブの実現や食糧供給の安定化に向けた可能性検討を実施していきます。
阿座上さん:
すでに多くの仲間を巻き込めていると思うのですが、今後、さらにどのような人たちにブルーの領域に関わってほしいですか?
友廣さん:
企業でいえば、新たな海藻の利活用を一緒に考える仲間が増えてくれると嬉しいです。海藻は懐が深くて、食以外にも「新素材」といった観点で、バイオプラスチック、肥料、飼料、医薬品、エネルギーなど、さまざまな事業開発の可能性を秘めています。他業種の人たちがどんどん入ってきて様々な「出口」ができれば、海の課題解決が促進されていくはずです。海藻で事業開発を行っていきたい企業のみなさんと、共創型のプログラムも立ち上げる予定です。
また、一般の人たちには、海藻の新しく美味しい食べ方を楽しんでもらいたいです。現在、海藻のほとんどは和食でしか食されていません。平成の28年間で「一人あたりの海藻の消費量が50%減少した」という調査結果もあります。でも、調理法によっては洋食でも美味しく食べることができます。みんなで、新しい海藻の食文化をつくっていけたら嬉しいです。
阿座上さん:
真陽さんからは、これからブルーに関わろうとしている人たちに持ってほしい考え方を聞きたいです。
真陽さん:
笹川平和財団海洋政策研究所が発表している論考によると、「ブルーエコノミー」という言葉が出てきたのは最近で、それまでは「オーシャン/マリンエコノミー」という言葉が使われていた。その違いは、ブルーのほうが「非利用価値」にまで目を向けている点といいます。(*2)また、ブルーエコノミーには、今は市場がなく価値はわからないが、生態系 の保護によって生じる魚の生育場としての機能や、将来世代の消費できる財も価値として存在すると述べられていました。
「インパクト」というと、どうしても1年後の成果など短期的なものに目が向きがちですが、海にまつわる活動は、短期間で価値が証明されるものばかりではありません。目の前の取り組みが、5年後、10年後、15年後にどのような影響を及ぼすかという長い目線を持ち、関わっていけたらと思います。
*2 笹川平和財団海洋政策研究所「ブルーエコノミーの定義と評価手法―オーシャン/マリンエコノミーとの違いに注目して―」を参照

PROFILE
ゼブラ編集部
「ゼブラ経営の体系化」を目指し、国内外、様々なセクターに関する情報を、一緒に考えやすい形に編集し、発信します。