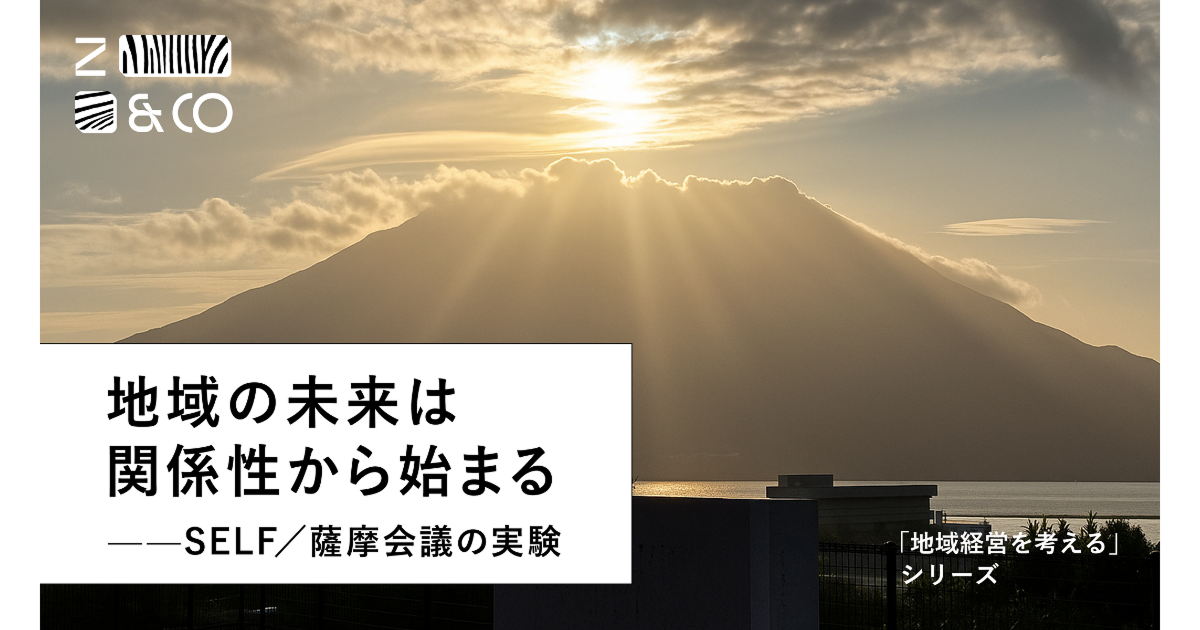2025.02.28 ZEBRAS
「支店こそが銀行」スウェーデンの銀行が短期的利益を追求せずとも、半世紀以上成長を続けるワケ〜鍵は地域密着経営と行員への長期的利益還元

154年の歴史を持つスウェーデンのメガバンク「Svenska Handelsbanken」
Svenska Handelsbanken(『スウェーデン商業銀行』の意)は、スウェーデンを代表する銀行の一つ。投資銀行業務、保険や年金を含む消費者向け銀行業務など、幅広く銀行サービスを行っていますが、特にビジネスに対する金融取引を行う商業銀行としての顔が強い銀行です。
1871年にストックホルムで設立され、今年7月で創業154年を迎えます。従業員数1万人以上、総資本1800億クローナ(2兆5000億円強)以上、総資産は3.76兆クローナ(約530兆円)、自国やイギリスを中心に世界に440の支店を抱える押しも押されぬ大銀行ですが、同行の特色は規模よりもその安定性。
Global Financeにより繰り返し「欧州で最も安全な銀行」の評価を得ており、Fitch Ratingsによる格付けはAA。歴史的にも、多くの銀行の経営が立ち行かなくなった世界恐慌時も、今世紀の金融危機においても、同国でほぼ唯一顧客や政府、中央銀行からの援助を一切必要としなかったことを誇りとしています。
また、顧客満足度の高さ、信用損失率の低さ(いわゆる貸し倒れの率、通常0.5-1.0%とされるが同行は0.04%を保っている)などで有名なほか、石炭火力発電、禁止兵器、核兵器の関与するビジネスには投資しないなど、サステイナビリティへの配慮でも知られています。
最大の方針の柱は「分権」、おまけとしての「退職時の利益の分配」
そんな同行の安定性を支えている最大の柱とみなされているのが、その分権型の経営構造です。
「支店こそが銀行(Branch is the Bank)」という哲学のもと、多くの場合、行員10人以下の各支店に最大の自主裁量権を置き 、支店の経営(人材採用・融資の是非・商品販売方針など)における本社からの介入を最小限にとどめています。年間の予算も本社では立てず、業績管理は各支店からの報告に基づいてなされます。
支店の評価基準も、本社が数値目標を設定することなく「相対的評価」によってなされ、規模よりもコストインカム比が他の支店や地域の競合他行よりも優れていることが評価されます。
支店間での自然な競争とモチベーションアップを図るために、収益性を視覚化する独自のITシステムが導入されており、こうして生まれるコスパのよい支店の集合体こそが「優れた銀行」である、という考え方なのです。
そんなことをしたら業績欲にかられた支店長が、コストカットのために無茶な人員削減をしたりするのでは…という心配は無用。同行は揺るがない本社の方針として「長期的成長」と「持続可能性」を堅持しており、四半期や一年ごとの業績は重視しないことになっています。
本社の方針として「株主よりも顧客優先」を明確に打ち出しており、毎年の配当を気にして目先の利益に囚われることのない、安定性を評価する投資家だけが株主となっています。
また行員のモチベーションを長く保つため、従業員に対する「長期的な」利益還元システムも。銀行全体の収益の10%は、収益分配を担当する財団「Oktogonen Foundation」に管理され、従業員は「退職後に」その時点の銀行の業績に応じた分配を、年金の形で受け取れるようになっています。
こうして、短期的な利益を目的として将来にしわ寄せが予想されるような戦略を取ることはしなくともよい、また、したくない仕組みになっているのです。
一方で、銀行全体の業績が将来の自分が受けられる分配に響いてくるため、個人競争で足を引っ張りあうことよりも、助け合ってチームでの業績の底上げを目指す土壌も生まれやすくなるという狙いも。
コストインカム比向上のためには取引の拡大ではなくコストカットが奨励されていますが、その基礎となるのが各支店の「地域密着型経営」。
先述の信用損失率の低さは、ひとえに支店が地域の文化、状況、顧客を熟知していることに支えられています。融資の是非を決める際のリスク分析は時間も経費もかかりますが、もともと地域の顧客をよく知っている支店の行員が判断すれば、それらのコストが大幅にカットできます。
また地元と密接につながり、顧客満足度にこだわって経営することで、多額の広告費をかけずとも口コミで顧客が増えます。商品販売に関しても、外部機関に市場調査を依頼したり広告を打ったりして経費と時間を費やすよりも、地元住民のニーズを熟知している支店の判断に任せる方が効率的です。
こうして支店数が増加し、提供できるサービスを拡大していく有機的な成長こそが同行の定義する「成長」であり、それは本社の設定する数値的な目標の達成を支店に強いて行われるものではない、というのが同行の基本的な経営哲学です。
経営哲学は1970年代のCEOによる改革
同行がこのような経営方針を固めたのは1970年代のことで、背景には同行が経験した経営陣退任・新CEOによる改革劇がありました。
1960年代に社会主義的な価値観が世論に色濃くなり、銀行や資本家、実業家などに対する反感が高まる中、商業銀行として「実業家の仲間」の印象が強かった同行にも批判的な目が向けられます。そんなさなか1969年に外国為替取引で規制違反が発覚し、経営陣が総辞職を余儀なくされることに。
後任としてCEOに就任したのが、哲学博士であるとともに経済学者で、経済系のシンクタンク会長を経て、当時はスウェーデン北部の小さな地方銀行の取締役だったJan Wallander氏(1920-2016)でした。
同氏のリーダーシップのもと、同行は顧客のための銀行としての改革を推進し、1970年から1972年にかけては子会社として8つの地方銀行を設立、各支店をエリアごとに統括する権限を本社から移行しました。
中央予算編成の重要性を格段に下げ、各支店からの報告に基づいて財務管理を行うシステムを導入する一方、それ以前に追及されていた取引量の拡大よりもコストインカム比に比重を置くことも決定されました。
先述の退職後の利益分配制度が取り入れられたのもこの時期です。また、同氏が就任した1970年に同行初のATMの利用を開始しています。
同氏による改革は、特に権限を手放すことになった本社勤務の社員から相当な反発も買ったといいます。しかしその後、度重なる金融セクターの規制緩和や不況、金融不安といった経済にとって不安定な時期が来るたびに、抜群の安定性と信頼・適応力を誇る同行は、取引の(結果的な)拡大・他行の買収・支店の拡大を繰り返し、現在のメガバンクへと成長を遂げました。
Wallander氏の信念の背景には、小さな地元密着型の地方銀行での勤務経験があったと考えられています。同氏は、現場こそが顧客のニーズを最も把握しており、分権型の方が適応力もレジリエンスもあって効率的だと洞察を得ていたのです。
CEO就任当時彼は支店の現場を回って、その結果、各現場では顧客と良好な関係が築けているのに権限がないために、躯体が大きく現場の情報も把握していない本社の意思決定を待つ必要があり、迅速で適切な融資やサービス提供のチャンスを逃していると確信しました。
その後、改革を進めるうちにも顧客はカスタマイズされたサービスを求める時代になり、本社が決めたマニュアル化された対応しかできない他の大手銀行が顧客を逃していく様子を尻目に、同行は着実に成長していきました。
同行の成功は「分権」「地域密着」「予算なき経営」の可能性を示すモデルケースとして、現在では銀行セクターのみならずビジネス界全体に参照されています。
「持続可能性」を徹底した結果「成長」を続ける同行の軌跡は、「拡大・収益増」だけではないこれからの時代の「成長」を模索する私たちの道筋を照らしてくれる気がします。
文:ウルセム幸子
編集:岡徳之(Livit)http://livit.media/

PROFILE
ウルセム幸子
3児の母、元学校勤務心理士。出産を機に幸福感の高い国民の作り方を探るため、夫の故郷オランダに移住。現在執筆、翻訳、日本語教育など言語系オールラウンダーとして奔走中。