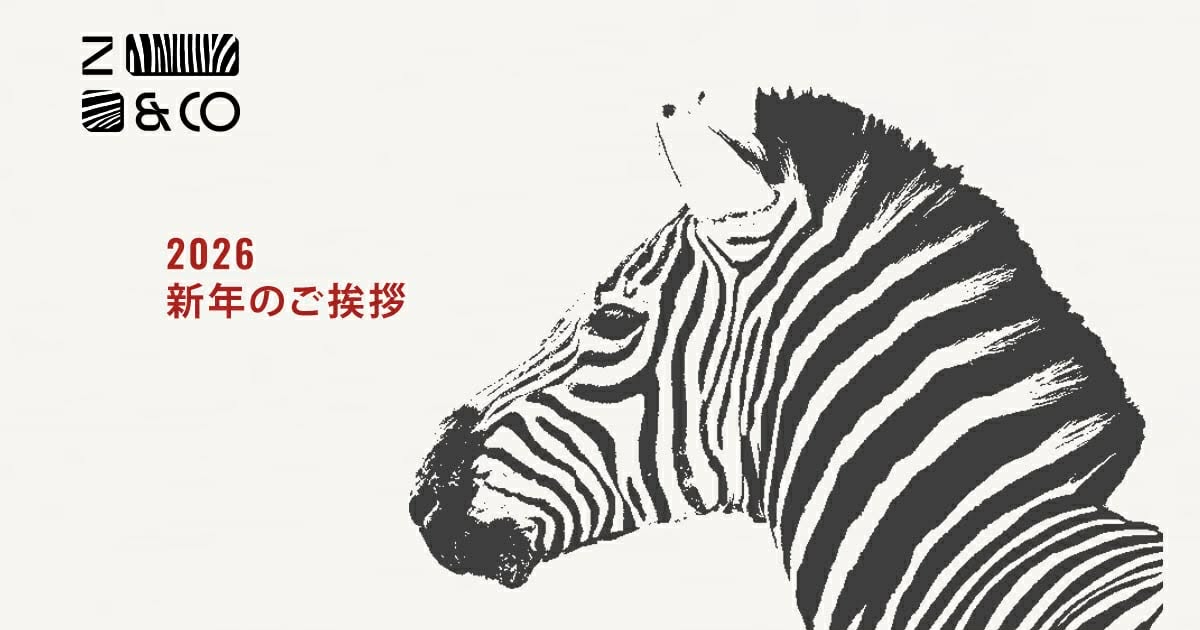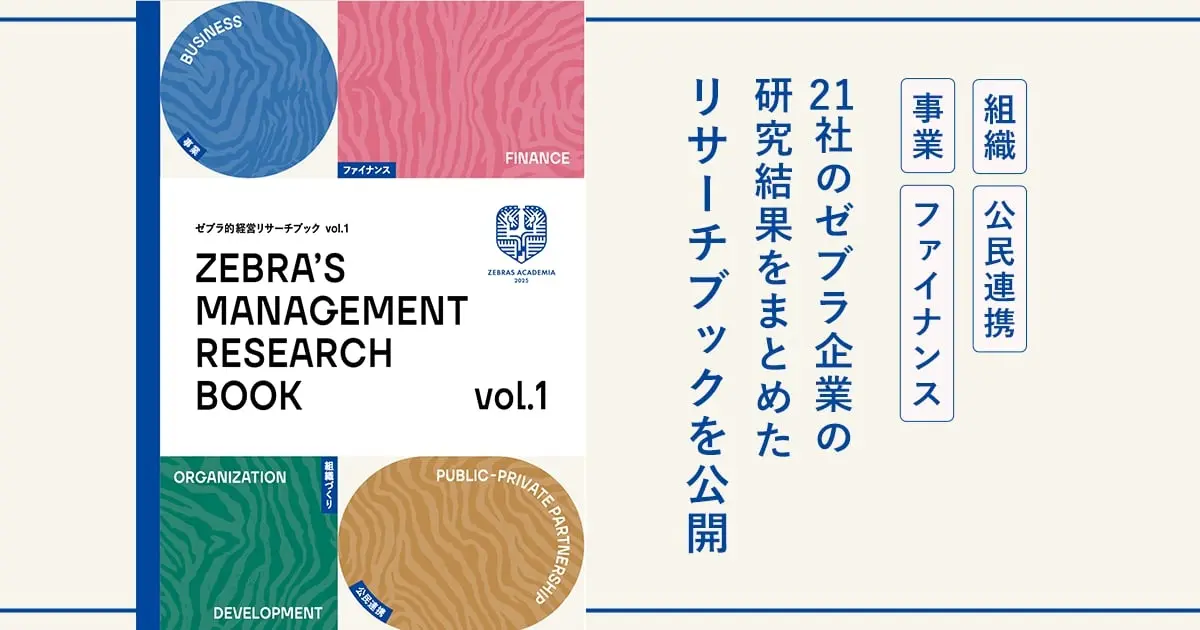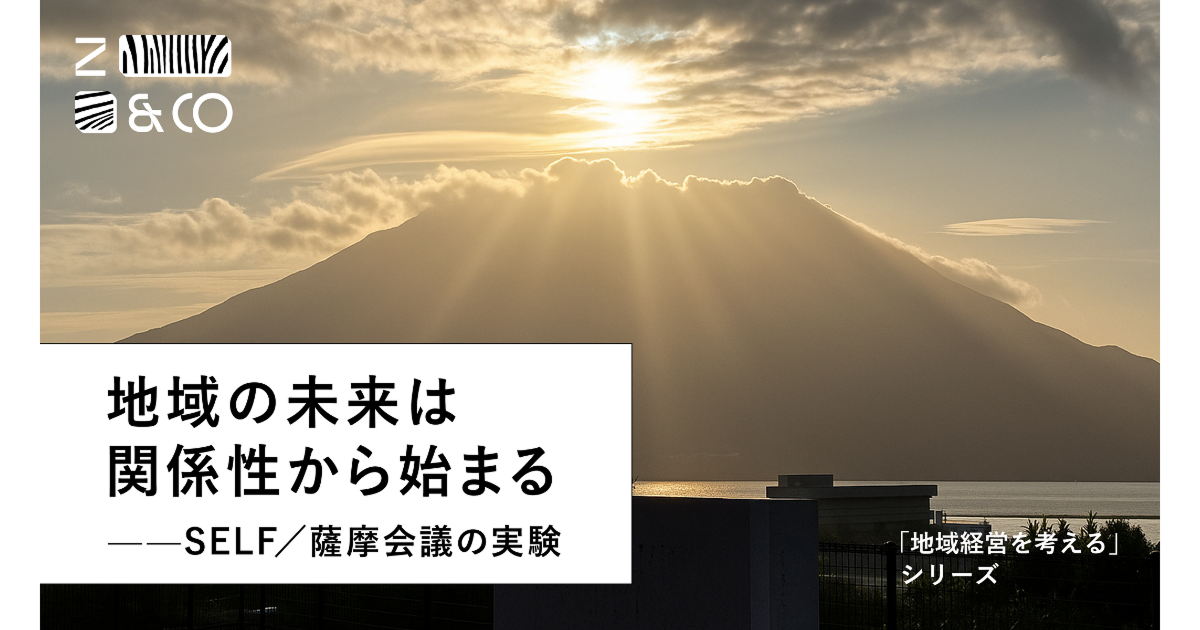2025.03.12 ZEBRAS はじめてのゼブラ
【創業4周年】ゼブラ経営を「広げる」から「確立する」へ。メンバーの成長と、社会実装に向けた新ステージに突入する5期目への期待

2025年3月12日、Zebras and Company(以下、Z&C)は創業4周年を迎えました。創業当初に描いた構想が少しずつ実現し、ムーブメントが広がるなかで迎えたこの節目。Z&Cのメンバーは何を感じ、どんな未来を思い描いているのでしょうか——。
今回のインタビューでは、4期目を振り返りながら、各メンバーの学びや成長、そして5期目に向けた意気込みを聞きます。これまで広げてきたゼブラ経営の考え方を、より社会に根付かせていくために、Z&Cはどのような一歩を踏み出そうとしているのか。
会社の方針や新たな取り組みに対する考えに加え、日々の仕事や関係性のなかで生まれた変化、個人の思考やスタンスのアップデートについても語ってもらいました。「Z&Cで働く人はどんなことを考えている?」「5期目をどんなステージにしていこうとしている?」。そんな視点から、楽しく読んでいただければと思います。
ゼブラムーブメントの担い手が、Z&Cから仲間たちへと広がった
——4周年おめでとうございます!まずはこの1年で特に印象的だったこと、手応えを感じたことをそれぞれ聞かせてもらえますか?
田淵良敬(以下、田淵さん):
先日、経済産業省中小企業庁と1年間取り組んできた「地域の社会課題解決企業支援のためのエコシステム構築実証(以下、ローカル・ゼブラ推進政策)」の最終発表会がありました。会場には250〜300人が、オンラインでも200人以上が参加し、全国20地域の企業がそれぞれの取り組みを発表。その様子から、「ゼブラムーブメント」が僕らの手を離れて広がっていく手応えを感じました。
以前は「うちの会社はゼブラ企業と名乗っていいんですか?」と言っていた経営者が、実証を通じてゼブラ企業として自信を持って活動する。そうした主体的な動きが、企業だけでなく、支援機関の間にも生まれているのを実感しました。
田中苑子(以下、苑子さん):
最終発表会では、田淵さんが最後に少し話しただけで、私たちは登壇していません。それなのに会場では、「ゼブラ」という言葉を使いながら地域の可能性について熱く語る人たちが多くいました。
また、前後にあった前夜祭と後夜祭でも、地域同士のつながりが生まれていました。それぞれの地域で活動していたゼブラ経営者が想いや知見を共有し、またそれぞれの地域に帰っていく。参加者に話を聞くと、「横のつながりができたことが一番よかった」という声が多かったです。
——初の取り組みであるローカル・ゼブラ推進政策が、いい形で幕を閉じたんですね。たまちゃんや菜さん、阿座上さんは、何が印象的だったでしょうか?
玉岡佑理(以下、たまちゃん):
昨年の5月に入社してから一番関わってきたのは、親ゼブラ(*1)である日建設計のみなさんと一緒につくった共創型社会環境デザインプログラム「FUTURE LENS」です。昨年末に無事リリースし、徐々に形になってきたことに手応えを感じています。
最初の段階から、「日建設計、ゼブラ企業、地域の人にとって何が一番いいのか?」を考えながら進めてきましたが、リリース後の反響は想像以上で、プレエントリーはすぐに100件以上集まりました。親ゼブラと連携したムーブメントづくりを前進させる一歩として、日建設計が持つ専門性や知見がゼブラの領域に入ることで生まれる変化が楽しみです。
阪本菜(以下、菜さん):
そんなたまちゃんが入社してくれたことも、Z&Cにとって大きな変化でしたよね。フルタイムメンバーが5人になり、組織として動きやすくなりました。私からしても、頼れるお姉さんが増えて嬉しいです。
仕事で印象的だったのは、昨年6月に開催したZ&C初のカンファレンス「ZEBRAHOOD 2024」です。コロナ禍以降、初めてゼブラ企業に関わる人たちがリアルに集まる場ができました。会場ですれ違った参加者同士が「あなたも来ていたんですね!」と声をかけあっていたり、偶然の出会いもたくさん生まれました。準備は本当に大変で、当日前後の記憶が飛んでいるんですが、やり切れてよかったです。
阿座上陽平(以下、阿座上さん):
みんなが話してくれたように、新しい取り組みへの挑戦を通じてZ&Cメンバー全員が成長しているのが、印象的でした。メンバーだけでなく、ゼブラファミリーのみなさんにとっても、多くの変化があった年だったと思います。
自分の思い描く理想の世界が「ゼブラ」というコンセプトによって可視化され、それに共感してともに挑戦する仲間が増えていく。そして、例えばローカル・ゼブラ推進政策のように、新たな取り組みをリリースした際、予想を超える反響を得ることができる。その結果、「自分の理想の世界をつくれるんだ」という実感ややりがいを得る人が増えていく。
そんな可能性を示し続けることこそが、僕や田淵さんの役割であると、改めて実感した1年でした。
*1 「親ゼブラ」とは、ゼブラ的経営を実践しながら全国規模で事業を展開するゼブラ企業。「兄ゼブラ」とは、地域や産業のリーダー的存在として、子ゼブラの規範となり共創を促す中規模なゼブラ企業。
主体性の発揮、ゼブラへの理解の深まり。メンバー3名の成長
——Z&Cメンバーの成長や変化は気になりますね。それぞれの視点から語ってもらったうえで、他のメンバーから見た印象も聞かせてください。
菜さん:
この1年を通じて、ゼブラムーブメントやゼブラ経営者について、自分なりの考えを深めることができました。以前は、阿座上さんや田淵さんの話から学ぶことが多かったのですが、ZEBRAHOODなどのプロジェクトに関わるなかで、少しずつ自分の意見を持てるようになりました。
また、外部のプロジェクトマネジメント講座を受講したり、インパクトの未来を模索する交流型カンファレンス「IMPACT SHIFT」の実行委員を務めたりと、新たな挑戦もしました。社外の同世代の人たちと働く機会が増え、そのなかで自分が貢献できる部分を見つけられたので、仕事が以前にも増して楽しくなりました。
田淵さん:
菜さん、本当に変わりましたよね。特に、コミュニケーション面での成長が大きい。自分の意見を伝えることへの抵抗が減り、仕事上の悩みも抱え込まずに話してくれるようになりました。おかげで、何が壁になっているのかを周りの人が把握しやすく、解決もしやすくなったと思います。
加えて、圧倒的に主体性が高まりました。自分自身の仕事はもちろん、僕や阿座上さんをプッシュして、物事をどんどん前に進めてくれる。働くスタンスが整ってきたことで、安心して仕事を任せられるようになりました。
——新卒入社3年目の菜さんの着実な成長が感じられました。たまちゃんは、どんな変化や成長を感じていますか?
たまちゃん:
入社1年経ってませんが、大きく3つ変化がありました。ひとつは「地域」や「ゼブラ企業」に対する理解が深まったことです。視察で秋田県の男鹿に行ったり、『薩摩会議』で鹿児島の阿久根に行ったりしました。そのなかで、地域の企業の生態系についてや、それぞれの人や企業が実現しようとしていることを肌で感じることができたんです。
もうひとつは、「ファイナンスのあり方は多様である」と実感できたこと。ゼブラ企業のファイナンスに関わるなかで、「お金を出す側の視点」「受け取る側の視点」「それがどう事業につながるのか」などを考えることができました。Z&Cが翻訳した書籍『ファイナンスをめぐる冒険』によって、オルタナティブなファイナンスを体系的に学べたことも大きかったです。
阿座上さん:
たまちゃんは、新しい領域のことでも、すぐに吸収してアウトプットに落とし込むのがうまいですよね。コンセプトを理解しつつ、8割くらいのアウトプットはパッと出てくる。残りの2割は、経験を積めばさらに精度が上がるんだろうなと思います。
たまちゃん:
ありがとうございます。3つ目の大きな変化は、「自分なりのスタンスを持つ」ことを意識するようになったこと。投資案件の事業精査に関わっていると、「YES」とも「NO」とも言い切れないケースが多くあるんです。限られた情報や経験をもとに、絶対的な正解がないなかで自分なりの答えを導き出す必要があります。だからこそ、「自分はどう考えるのか」「何をよしとするのか」といった軸を持つことが大切だと実感しました。
——「ゼブラ企業とはこういうもの」と決めつけず、それぞれが考えを深め、探求することを大切にしているのは創業当初から変わらないですね。苑子さんはいかがでしょう?
苑子さん:
この1年は、「探索」がテーマだったと感じています。もともと地域や自然に触れることが好きでしたが、去年はゼブラ的な視点で地域や自然を見るようになりました。greenz.jpが開催する「リジェネラティブ・デザイン・カレッジ」に参加し、人と自然の関わりについて学んだこともあって、体験から吸収できる情報の質と量が大きく広がりました。
また、ゼブラ経営者とのMTGにひとりで参加したり、イベントやアクセラレーションプログラム等で起業家の方と話したりする場面も多い1年でした。これまで聞いてきたことや経験してきたことを、改めて自分なりに言語化する機会を通じて、ゼブラに対する理解もより深まったと思います。
田淵さん:
苑子さんは、「意思を持って物事を進める」ことができるようになってきていると感じます。もともと器用な人なので、頼まれたことを正確にこなすのは得意。それに加えて、ひとりで動く場面が増えたことで、仕事を自分ごととして捉え、より主体的に進めようとする意識が一層強まったように感じます。
より素直に、自然体に。組織の成長とは、経営者の成長である
——創業メンバーのお二人にも聞いていきます。阿座上さんの学びはいかがでしたか?
阿座上さん:
去年の目標は、「これまで関わりのなかった領域の人たちとも関係を築く」ことだったんですが、国交省に友人ができたり、金融業界で想いを共有できる人が増えたりと、結果的に達成できたかなと感じています。そのひとつの要因として、自分自身が「なぜゼブラを広めたいのか」という根本的な想いを語るようになったことが影響しているのかもしれません。
僕自身、成長を通じて社会をよりよくし、自分らしく生きられる人を増やせる事業や会社を増やしていきたいと考えています。そして、今はそれを「ゼブラ」という言葉で表現していますが、必ずしもゼブラという形にこだわる必要はないとも思っている。そんな想いを率直に話すようにしたら、より自然に共感して興味を持ってもらえるようになりました。
菜さん:
阿座上さんはこの1年、以前にも増して楽しそうに働いていましたよね。朝から夜までMTGがびっしり詰まっている日が続くのに、ずっと楽しそう(笑)。ゼブラムーブメントに火がつき、Z&C以外の人たちがゼブラを広げ始めてくれたことも、楽しさの要因のひとつだと思います。阿座上さんが楽しそうなので、社内の雰囲気もさらに明るくなりました。
——素直な言葉を語ることで、社内外に想いやワクワク感がより伝播しているようですね。田淵さんにとっては、どんな1年でしたか?
田淵さん:
経験という意味で大きかったのは、去年5月からZebras Unite(ゼブラの概念を提唱したアメリカ発祥のコミュニティ、以下ZU)の社外役員をやらせてもらったことです。ZUはステークホルダーが多く複雑で、意思決定やコミュニケーションの難易度が高い組織。役員として限られた時間と情報のなかで決断を迫られる経験が学びになりました。
あとは、自分自身の変化として、以前よりも「感情を大切にする」ようになりました。どうしても頭で考えすぎたり、最善の答えを出そうとする思考が強かったのですが、最近少しずつ、自分の感情を素直に感じ取り、それを起点にコミュニケーションや行動をとれるようになってきた気がします。
阿座上さん:
たしかに、より自然体に近づいている感じがしますね。創業当初のような気負いが少しずつ和らいできたのかもしれません。仕事もプライベートも、大きな変化があったと思いますが、そのトランジションをうまく乗り越えたように見えます。自分のペースをつかみながら、新たなステージに向けた準備を整えられたんだなと。
「経営者の成長=組織の成長」だと思っているので、僕と田淵さんがしっかりと成長を実感できているのは、とてもよかったです。
一過性のムーブメントで終わらせない。5期目は新たなステージへ
——ゼブラ企業の成長を支えるZ&C自体が成長すること、そして何より経営者自身が成長することを大切にしているのが伝わってきました。5期目のZ&Cの取り組みと、それぞれの楽しみなことや目標について教えてもらえますか?
田淵さん:
冒頭でも話したように、5期目はZ&Cのステージが変わるタイミングだと思っています。創業当初に描いたことが実現してきたなかで、それをより良くするのはもちろん、新たな動きを生み出していこうとしています。
投資やファイナンスの領域で新しい仕組みをつくることも、その一環。具体的な構想は現在検討中ですが、事業自体も新しい展開を生み出していくためのファーストステップになる1年にしたいと思います。
また、個人的な目標としては、「感情を大切にする」ということをさらに進めていきたいです。実際に身体で体験したこと、学んだことを自分の中に落とし込んでいくことを意識していきたいと思います。
菜さん:
今年は、ゼブラ的なファイナンスや事業開発、地域企業のあり方など、Z&Cが研究してきたものを土台にゼブラ企業の実践者たちとともに考えるカンファレンス「ゼブラアカデミア(仮)」を開催予定です。どんな場になるのか、準備のプロセスも含めて、今から楽しみにしています。
また、私自身は今年の7月で、入社3年が経過します。これまで社内のプロジェクトで培ってきたプロマネ力などを活かして、社外のプロジェクトにも関わる1年にしたいです。社外も含めて貢献できる幅を広げていければと思います。
苑子さん:
今年は、4年目までのZ&Cの取り組みをまとめた「インパクト・ジャーニー・レポート」もリリースします。Z&Cは多角的な取り組みをしているので、外から見ると少しわかりづらい部分もある。レポートによって活動や影響を整理して発信できるのが楽しみです。
自分としては、先ほど話した「主体的に動く」ということを、より意識していければと思います。その先に、自ら動いて社会に影響を与えていこうという主体者を増やし、「個人が社会を変えられる」という実感を持てる社会を目指していきたいです。
たまちゃん:
私は、ゼブラ的なファイナンスの体系化や普及が進むことにワクワクしています。ゼブラアカデミアなどを通じて、ゼブラ企業やこれからゼブラ企業をつくろうとする人たちと一緒に考えていけるのが楽しみです。
入社1年目は、地域やゼブラについて学び、物事を考えるための基礎を培う日々でした。2年目は、投資案件やプロジェクトのなかで、自分の意思やスタンスを明確にしながら、より主体的な動きを増やしていければと思います。
——最後に、Z&C全体の抱負もふまえ、阿座上さんの目標を教えてください。
阿座上さん:
まず個人の話として、最近改めてクリエイティブの重要性を強く感じるようになりました。ムーブメントづくりに10年以上関わってきましたが、思いだけでは伝わらないものを表現し、望ましい認知を築くうえで、クリエイティブの力は欠かせないと実感しています。ゼブラ企業をはじめ、周りの人たちがクリエイティブを武器として活用できるように、根本的な考え方や扱い方を伝えていきたいと思います。
Z&Cとしては、田淵さんも話していたように、創業初期から描いてきたことがようやく実装され始めたタイミングです。親ゼブラである日建設計との「FUTURE LENS」が始まり、兄ゼブラであるウエダ本社と協働するミドルマネージャー向けの伴走型育成プログラム「Work Cross」もスタートしました。
ウエダ本社の岡村充泰さんが「ゼブラ企業は単年度ではなく、3カ年で計画を立てたほうがいいのでは」と話していたのですが、その考え方がしっくりきています。この3年で実現したものはたくさんありますが、現状維持のままでは「そういう取り組みもあったね」と、ただの流行りのワードで終わってしまう。
だからこそ、次の3年は「ゼブラ経営を広げる」というところから、エコシステムの構築も含めて「ゼブラ経営を確立する」へ、より深く実装するための取り組みを進めたいと思います。今年は、その動きを本格化させる最初の年。新たな展開を楽しみにしていてください。

PROFILE
Fumiaki Sato
編集者・ライター・ファシリテーター。「人と組織の変容」を専門領域として、インタビューの企画・執筆・編集、オウンドメディアの立ち上げ、社内報の作成、ワークショップの開催を行う。趣味はキャンプとサウナとお笑い。